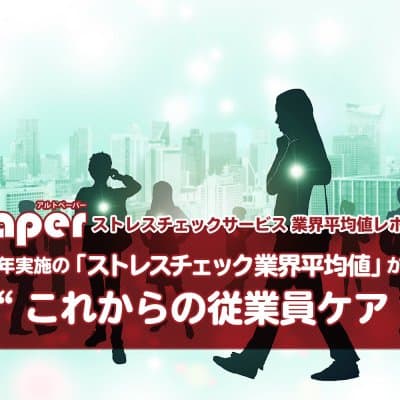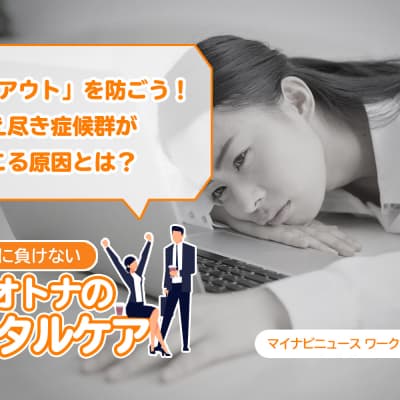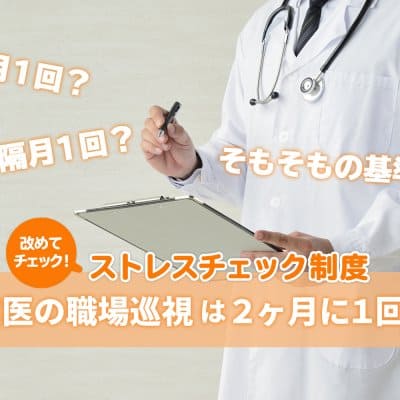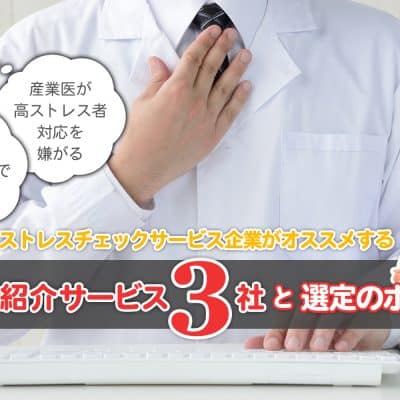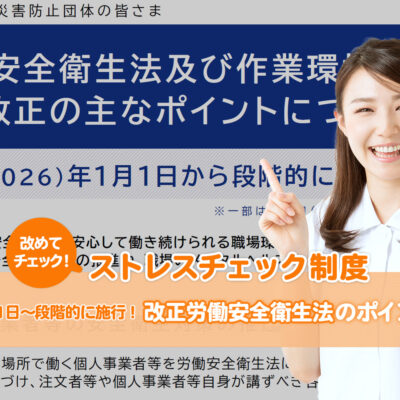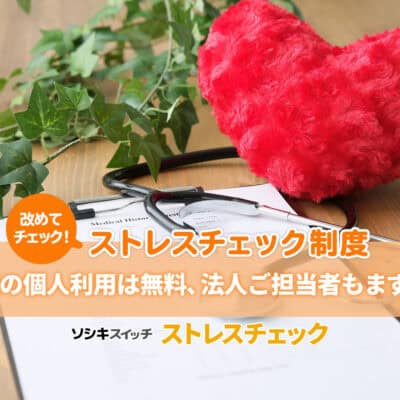年に一回行なわなければならないストレスチェックですが、なかなか経験や知識の共有は難しいもの。
厚労省の提供している企業向けのマニュアルもありますが、実際に実施しようとなると「誰が何をやっていいの?」「この会社に合った基準はどれ?」と疑問がわいてくることでしょう。
義務と定められているストレスチェックには、企業が用意しなければならないものがいくつかあります。
その中でも今回は、当社が委託を行う中でお問い合わせの多かった「実施者」「実施事務従事者」について、比較と説明をいたします。
必要なのは「産業医」・「実施者」・「実施事務従事者」
企業が義務とされるストレスチェックには必ず設置しなければならない役職があります。
- 実施の詳細を労基署に報告を行う「企業と契約した選任産業医」
- ストレスチェックの実施・結果の確認を担う「実施者」
- ストレスチェック実施の事務実務を執り行う「実施事務従事者」
企業・組織によってはこの方々に「ストレスチェック制度担当者」などさらに監督・実務を行う方が加わることもありますが、基本的にはこの3つの役職を設置するよう指針で決められています。
この中で一番耳にするのは「産業医」ですね。
ストレスチェックが義務となる50人以上の企業なら「産業医の選任義務」があるため、必ず1人は選任されています。
「実施者」「実施事務従事者」の2つについてはどうでしょうか。
多くの方が耳慣れない単語かと思われます。ストレスチェック制度開始から欠かさず実施している企業でも、混同されている方がみられるのもこの2つです。
「実施者」とは「資格をもった専門家」のこと!
ストレスチェックは企業の安全配慮義務や国の定める労働安全衛生法の遵守に関わります。
「実施者」は実施されるストレスチェックが「専門的な見地から適切か意見する・対応する」役職です。
適切かどうかの判断を行うのにあたり、心理についての専門的な知識と職場のメンタルヘルスに対する一定以上の理解が求められるため、ストレスチェック実施者には次の資格を有するものと法律で定められています。
- 医師
- 保健師
- 厚生労働省が定める検査を行うために必要な知識についての研修を修了した
歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
(※平成30年8月9日に歯科医師及び公認心理師が追加されました)
(参照: 厚生労働省令第九十四号 )
どれも国家資格、および所定の研修を必要とするものです。
実施者は、医師の資格を持ち実際の企業の内情や職場環境を把握している「選任の産業医」が適任とされています。
契約形態や業務の量によっては、産業医では実施者の業務が行なえない場合があります。
その場合は産業医とは別に「実施者」を設けることが可能です。
社内の保健師など資格を持った従業員にお願いする、外部企業に委託するなど方法を提案し、衛生委員会で決議しましょう。
「実施事務従事者」は社内の実務担当者
「実施事務従事者」はその名の通り「実施に必要な事務を行う」担当者です。
ストレスチェックにまつわる事務は、従業員の氏名や受検状況、実施結果といった本人の同意無しに閲覧できない「要配慮個人情報」の取り扱いが主になります。
そのため、事務に関わる担当者を限定し、ストレスチェックに関する情報を閲覧できる人を最小限・最低限にし個人情報の保護を図っています。
「実施事務従事者」になるのには特別な資格などを取得する必要はありません。
<ややこしいストレスチェック実施事務従事者の職務>
先述した通り「実施事務従事者」とは、ストレスチェック実施者の指示のもと書類の配布やデータ入力などの事務を行う人のことです。
実施者と同じ情報を取り扱うため人事権を持たない者に限りますが、社内からストレスチェック実施者の事務作業を補佐してもらう担当者を任用できます。
ストレスチェック実施にあたっては実施・実施後のみならず、準備や通知など多くの事務処理を行わなければならなりません。書類の配布や結果通知を迅速・正確に行うには実施する会社について普段からよく知っている人が適任です。
実施事務従事者は労基署などに報告する必要はありません。
ただし、実施事務従事者にはストレスチェック実施者と同様に守秘義務があり、また、実施事務従事者が誰なのか社内に公開しなくてはなりません。
「実施者」と「実施事務従事者」の名称が近しいこと、業務内容と名称が異なっていることなど混乱する要素が多い部分ですのでしっかり把握しておきたいですね。
また実施事務従事者は必ずしも置く必要はありませんが、その場合は実施者となる産業医や有資格者の方がデータの入力や書類の作成等の事務を一手に担うこととなります。
ストレスチェックに関われない「人事権」の範囲
まず、ストレスチェックを受ける労働者の「人事権」を持つ立場の人はストレスチェックの実施者、実務にたずさわることはできません。これはストレスチェックの結果が人事や昇格に影響を与えるのではないか、という不安・懸念が出てきてしまうことで労働者が正直に回答できない事態を防ぐためです。
ここで問題となる「人事権」とは 、
「労働者の人事を決定する権限を持つ」
「もしくは人事について一定の判断を行う権限を持つ」人 を指します。
部長・課長といった課内の人事や業務を取りまとめる人の他に、部下を持ちその業務や成績を監督する人も対象になるでしょう。
ストレスチェックは社の衛生管理者や人事や総務・労務といった部署が担当となる事例が多くみられますが、その場合でも同様です。
見方を変えれば 人事を取り扱う部署でも、人事権のない従業員ならば実施事務従事者になることができます。
実施事務従事者でなくてもできること
実施事務従事者に「人事権がない」という要件が付いているのは、「個人情報を管理するため」です。また、きちんとした管理や保管を行うためにも、実施事務従事者は必要な人数に限るよう指針が出ています。
とはいえ、限られた実施事務従事者でストレスチェックに関わる全ての事務を行うのは負担が大きいもの。
実施事務担当者以外の方が手伝える業務はあるのでしょうか?
<人事権のある人/実施事務担当者以外の従業員ができること>
・ストレスチェックの準備(計画や周知方法の検討、決定)
・衛生委員会での質問紙の選択の検討
・衛生委員会での高ストレスの範囲の決定の検討
・ストレスチェックの委託先を決める
・質問用紙の配布、ストレスチェックの実施方法の説明 など
実施事務担当者が守秘義務を負うのは「個人情報を含む事務」についてです。
個人情報の含まれない「事前の準備」や「スケジュールの決定」は人事権のある人でも行うことができます。回答する前の調査票の配布・内容や実施方法の説明など実施に関する事務の中にも、実施事務従事者以外が行うことができる事務は多くあります。
実施事務従事者の他に「制度担当者」「事務補佐担当者」を設けることで、負担を減らし「滞らないストレスチェック」が実施できます。
工夫次第で事務の安全性もアップ!
ストレスチェック実施準備は人事権のある人でも行えますが、実施後の結果にかかわる事柄に触れることはできません。面接指導の申し出を受付すること、実施記録の管理などは実施事務従事者が取り扱うべき事務です。
しかし、 結果の通知などは封筒に入れて封をするなど「本人だけがわかる方法」がとられるよう工夫を行えば、担当者以外の従業員でも事務を手伝うことは可能です。
他にも「朝礼で全員に面接指導を勧奨する」「結果の見方や面接指導の申し出方法を説明する」といった個人に限らず全体に働きかけるようなもの・ストレスチェックについて理解を深めるような働きかけは人事権を持つ人が行うことで効果がより高まるものです。
人事権のある立場の方が職場の従業員の状況を知るために衛生委員会やストレスチェックに関心をもつことは大変有意義です。
人事権があるからストレスチェックに関わらない、関わってはならないということではなく、労働者の不利益の防止のために役割を分担することが大切です。
ストレスチェックの実施者がいないときは?
ストレスチェックを行う際に実施者を決めるときは、国家資格の定めがある関係もあり、まず産業医に依頼することになると思われます。
けれども少なくとも50人以上のストレスチェックにかかわること、結果の判定や面接指導など産業医の負担は大きく、多忙やスケジュールの兼ね合いで実施者になれないことがあります。
特に産業医が嘱託産業医ですと、会社として頼みにくい、あるいはその産業医の他の業務や病院の規定との兼ね合いから断られる可能性もあります。
- ストレスチェック実施者をどうやって探してよいのかわからない
- 規模が大きく、ストレスチェックの対応が業務に影響する
など自社で対応が難しい場合は、外部の機関に委託することも認められています。
ストレスチェックは、実施後にも「個人情報の保管」や「高ストレス者の選定後の対応」など実施後の結果を踏まえた対応・事務が続きますので、適切な委託先を選ぶことができれば、担当者の負担の軽減にもつながります。選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
| 初出:2019年8月29日/ 編集:2023年04月17日 |