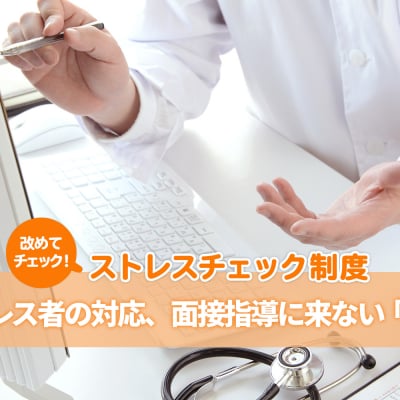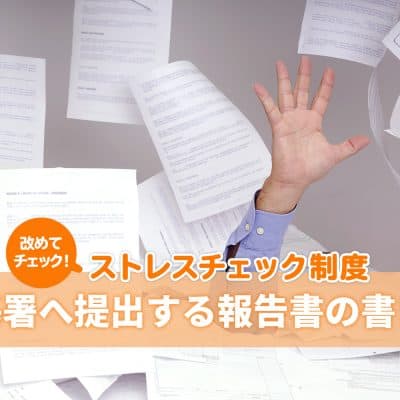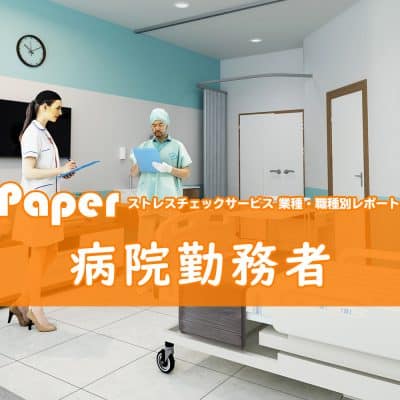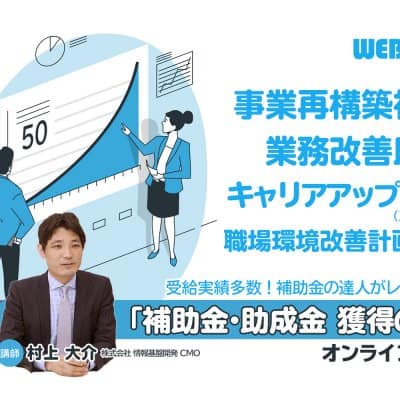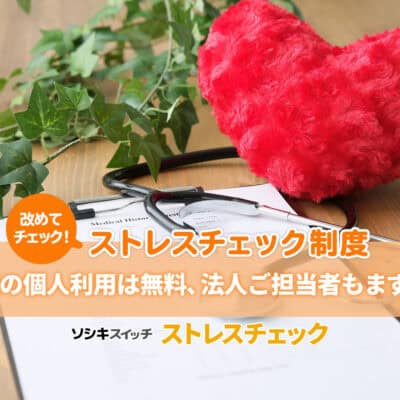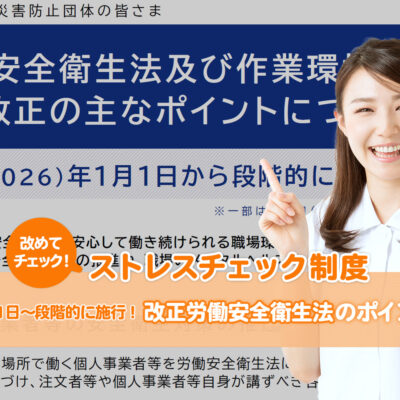集団分析をせっかく実施したのに
「分析結果に基づいていない・いつもの改善案しか出ない」
「改善案を立てたのに、なんだかみんなが非協力的・目標がいつも達成できない」
ではもったいない!
集団分析をすぐ職場環境改善に活かすためには、分析の方法だけではなく「実施の準備」や「目標の立て方」にもちょっとしたコツが必要です。
集団分析を職場改善案に上手に活用するための、人事・労務ご担当者が実践できる “コツ” について、2021年2月9日に開催したエムスリーキャリア共催「職場改善・産業保健オンラインセミナー」で解説した内容から抜粋してご紹介します。
信頼できるデータが取れていますか?
職場改善の対策案を考える際に、用いるデータが正確であればあるほど「結果の出る対策」へとつながります。そのためには分析や検討の方法だけでなく、いかに正確なデータが得られるかに関しても注意をしましょう。
特に「受検率」は大きな指標です。
80%以上あれば十分に信頼できるデータと取れますが、なるべく90%以上あることが理想的です。「ストレスチェックの実施」の周知・励行は毎回しっかり行いたいですね。
「受検率が低い」ことの裏側には、
「ストレスチェックの結果の取り扱いに不安を感じる」
「受検はしたけど、回答方法がわからなかった・設問を飛ばしてしまった」
という従業員がいることも考えられます。
ストレスという「個人の内面」を取り扱う以上、「この回答によって評価が変わるのでは?」と感じる人もいることでしょう。
「見えない」「感覚的な」データを採取する際にはなるべく素直に偽りなく答えてもらうことがデータの前提条件になります。また、不完全なデータが多ければ多いほど分析結果の信頼性も下がってしまいます。
結果の取り扱いには、不安を感じる人がいることを念頭に実施方法・結果によって不利益な取り扱いが生じないことを事前に、充分に周知しましょう。
数値化されたデータは図示・グラフ化しましょう!
ストレスチェックは「見えないストレスを定量化」できるシステムです。得られたデータはより分かりやすくなるように「グラフ化・図解化」をしましょう。
各点数をグラフにすることで、直感的に把握しにくい数字データも視覚化されて比較・整理がしやすくなり、数字の意味や傾向・状況が人事労務以外の部署担当者でも直感的に理解しやすくなります。
お勧めは「総合健康リスク」と「高ストレス者割合」を用いた「分布図」の作成です。
各部署のストレス原因が「職場」「個人的背景」のどちらにあるのかと、「対応の優先度」との2軸で表現され、同じデータ・同じ傾向にあるような部署のストレス状況を一目で把握できます。

持続的な職場改善策の実施を目指しましょう!
職場環境改善は、短期目標で達成できるものが少ないものです。
「継続して続けられる」「習慣として定着させる」ためには、「できる目標」を設定し、成果が実感できる・達成感が得られる環境下でモチベーションを維持する必要があるでしょう。
職場環境改善の目標、特にストレスや人的関係に関わるものは「一般的・イメージ的」なものでストップしてしまいがちになります。
継続のためには、イメージ的な目標からさらに一歩、より具体的に踏み込んだ「ステップ」を設けましょう!
明日からできる・誰でもできることから小さくステップを設定することで、「自分でもできた」「今日もできた!」という達成感が生まれます。
「自分で変えることができる・会社は変わることができる!」という実感がより大きな目標に挑むベースになります。
また、より具体的で実行可能なステップを立てるためには、目標の立て方に注意が必要です。
参加人数の大きなグループになるとデータはより「平均」に近くなり、特徴が見えにくくなります。
また、自部署と近しい部署と比較すると、
「あのデータの特徴は○○さんでは?」
「▲▲部の傾向はあの部特有のものだから、うちの部署の参考にはならないだろう」
と特徴の要因を個別のものとしてとらえてしまうケースがあります。
目標を立てる際には、自部署が今会社の中でどの位置にいるのかを見つけることが大切です。
そのためには、「一つ上のサイズ」のグループとの比較が役立ちます。部署⇔部署だけではなく、部署⇔所属部門/部署⇔部署のある地域・似た業務内容でまとめたグループで比較分析を行ってみましょう。
| 初出:2021年01月29日 / 編集:2023年04月12日 |