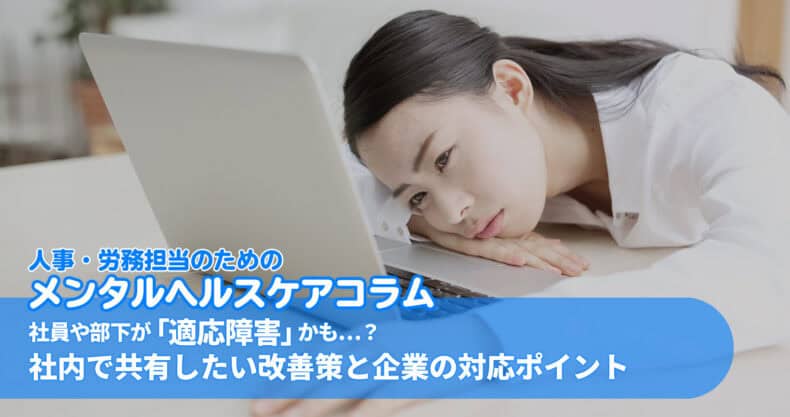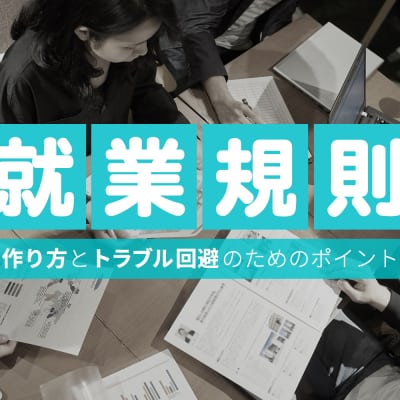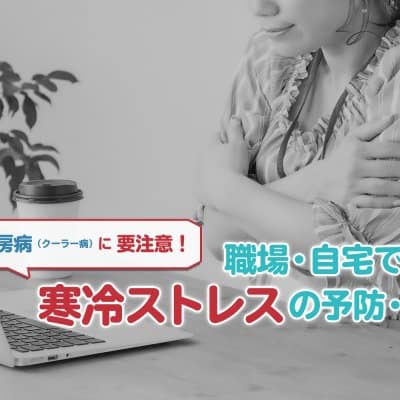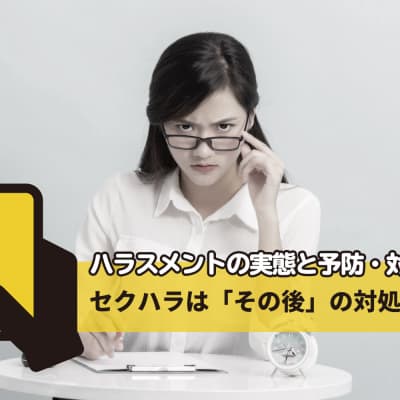突然ですが、皆さまの会社にこのような方はいませんか?
●例1:最近配属が変わった同僚が、遅刻してくることが増えた。新しい部署では十分な引き継ぎもなく、これまでとまったく異なる業務なのでプレッシャーを感じているそうだ。出勤しようとすると吐き気・動悸がすると言っている。
●例2:新規プロジェクトのチームに配属された社員。意欲的で、他のメンバーとの関係もよく、チームの中心として成果をあげているようだった。これまでは基本的にテレワーク中心でやり取りをしていたが、新しい上司がプロジェクトに参入してからは出社が原則に。すると会議や業務中に腹痛で頻繁にトイレに駆け込む様子もみられるようになった。表情が硬く集中力も落ちている。
……もしかしたらその症状、「適応障害」かもしれません。
季節の変わり目や新年度のはじまり、また大型連休明けなど一時的に気が緩むタイミングは、心身の不調に悩む人が増える時期でもあります。
特に有名なのは、皆さんもよくご存じの「五月病」ですよね。
実は五月病は、いつ誰にとっても起きる可能性のある「適応障害」の一種。そう思うと、少しだけ身近に感じませんか?
ですが、適応障害は正しい理解と対処がないまま長引いてしまうことによって、うつ病への移行や職場に適応できず孤立してしまうリスクなど、本人にとっても会社にとっても深刻な問題に発展しかねないのです。

今回は、見落としがちな不調のサインや適応障害発症の引き金となる要因、社員が健康な生活を取り戻すために人事労務担当者が知っておきたい、対応のポイントをご紹介します。
意外と知らない「適応障害」とは?
実はあの五月病も適応障害の一種
環境が変わることは、良くも悪くも「刺激=ストレス」になります。
特にその刺激によって「がんばるぞ!」とやる気に溢れている人ほど要注意。
適応障害とは、ある状況や出来事にストレスや苦痛を感じ、気分や行動面にうつ病に似た症状や不安感、逃避行動等の症状が現れる状態を示します。うつ病との違いは、ストレスの原因から離れると症状が改善すること。他の精神疾患では説明がつかず、またそのストレスの原因がなくなると、その症状は6ヶ月以上は続かないとされています。
例えば、冒頭で紹介した五月病。大型連休などでちょっと仕事から離れ、体と心がゆるむと疲れやストレスからなんとなく体調が悪い/会社に行きたくない、出社が憂鬱と思う/なんだか朝の支度に手間取る……など様々な心と身体の変化が生じます。これら環境の変化から生じるいわゆる「五月病」は、医学的には「適応障害」の一種です。
以前は新しい環境に置かれる方や、新入社員に多いとされていましたが、テレワークの普及や、オンラインツールを活用した新しい就労環境が定着したことから、近年では同じような症状・気分の変化を訴える報告が増えているようです。
このように在宅勤務やテレワークといった環境に慣れたからこそ、出勤などの「ちょっとした変化」がトリガーになることも懸念されます。深刻になるとうつ病や他のメンタルヘルスの不調のきっかけとなる「適応障害」、アフターコロナの新しい生活様式の中で今注意が必要な不調です。
適応障害のケアは「ストレスから離れる」が重要
生活リズムを整えて回復力を養えるよう配慮
適応障害は
1:ストレスをもたらす環境を変える(減らす・取り除く・受け止め方を変える)
2:ストレスへの対応力を養う
の2点を心がけた生活と環境を整えることで回復をサポートすることができます。
「ストレスをもたらす環境」を変えよう
適応障害の改善は「ストレスから離れる時間を作る」ことから。
ストレス要因から離れることができると自然と不調が改善することがあります。
いつから不調なのか、何がその原因なのか、本人とともに見つめなおしてみましょう。
通勤であれば時間をずらす、苦手な業務であれば誰かにヘルプを出す・得意な人に教えてもらう等、物理的にストレスの要因から距離をとる対策が回復への大きな一歩になります。
しかし職場ややらなければならないことから完全に離れるのは難しいものです。
ストレスの要因が就労環境や人間関係にあれば、改善まで長い時間が必要になることもあります。

なるべく休む時間はきちんととり、仕事と生活のメリハリを明確にするのも一つの解決策です。
決まった時間・タイミングでストレスの要因に触れることで、思考の切り替えをスムーズにし、より早くその環境に慣らすことができます。
また、調子が悪い時には物事をネガティブに捉えてしまいがちですが、「自分が今調子の悪い時期にあること」を自覚することで、落ち込みを減らすことができます。
他にも、
・休憩時や終業後に楽しいこと(趣味やちょっと豪華な食事など)を設ける
・仕事に対して無心になる、没頭できる作業を見つける
・「行くだけでOK」と自己肯定のハードルを下げる
といった「こんなささいなことで?」というものも、立派なストレス対処法になりえます。
重要なのは「ストレスを認識する、ストレスに向き合う」ことです。
本人が「原因がわからない」と思っている場合には、誰かに一度不調の原因や自分の感じていることを話し、整理してみることで見えてくるものもあるはずです。もし周りに不調を抱えていそうな方がいる場合は、一度声を掛けてみてはいかがでしょうか。
回復力を高める生活リズムを取り戻そう
現在感じているストレスを減らす・取り除くこととともに、ストレスの受け止め方・ストレスからの回復力を改善し「ダメージに強く」なることも重要です。
まずは崩れがちになる生活の基本的な部分から整えていきましょう。
・朝起きて夜眠る生活リズムを整え、日光を浴びる習慣をつける
・決まった時間に、栄養のバランスが取れたメニューの食事を摂る
・1日に30分程度、運動を行い軽く汗をかく
・なるべく日付が変わる前に就寝し、6時間以上のまとまった睡眠時間をとる
・入浴や洗顔など身だしなみに目を向け、爪や肌などの手入れに注意する
「栄養のある食事」「適度な運動」「良質な睡眠」は体と心の回復に欠かせません。
カフェイン・甘いもの・刺激物やお酒煙草などの嗜好品の取りすぎや暴飲暴食、休日の寝だめなどの過度の睡眠は逆に生活を崩してしまうので注意です。
生活が整い体力や心の余裕が戻ってきた時が環境改善のチャンス!
・趣味やレジャーに着手してみる
・タスクを見直して、プライベートの時間と仕事のバランスを調整する
・並行して複数に取り組む環境から、一つひとつの仕事に集中する環境へ
・人との交流を増やして、相談できる場所を作る
など、環境の変化を乗り越えるための「よりどころ」を増やす取り組みを少しずつ始めるとよいでしょう。
社員や部下が「適応障害」に!
企業はどうする?対応のポイント

異動や転勤は企業として指示を出すもの。それによって発生するストレスが社員のパフォーマンスを落とさないようにサポートするのも安全管理の一部です。
特に環境の変化が引き金になる適応障害に、企業はどう対応したらよいでしょうか。
第一にストレスを取り除くサポートを
慣れない環境にいることで起こりがちな適応障害は、第一に「環境になじむ」ためのサポートが有効です。
特にコロナウイルスなどで研修や配属が遅くなってしまった新入社員は、同期や先輩との関係性が構築されておらず不安やわからない業務に行きづまったときに孤立してしまうケースがみられます。
勤務時間内で、顔合わせや気軽に業務の説明・レクチャー・質問ができる時間を設けるなど制度的に交流が持てるようにすることがおすすめです。
本人から素直な意見が聞ける環境であれば、苦手な業務やつまずきが深刻化する前に対応することができます。
この制度があると、人事異動や業務変換などで途中から参加する社員の適応障害の予防にもなります。
また、在宅勤務から出社になった社員へのサポートには、「慣らし期間」を設けるのが良いとされます。
本格的に週5勤務を始める前に2週間ほど週2~3で出勤日を設ける週を作り、生活習慣や勤務のリズムを取り戻す時間を設けることで不調につなげない、スムーズな出社復帰を行えます。
不調を感じる社員の対応としても「出勤と休みのバランスをとる時間」は効果があるでしょう。
ワークライフバランスの見直しを並行して
感じているストレスに対して心身の反応・回復がきちんと行えていないことが適応障害の本質です。
業務や職場から受けるストレスに対して、身体や心が回復するための「時間」がちゃんととれているかどうか、企業側の視点からも改めて確認が必要でしょう。
把握できていない残業が多くなっていたり、慣れない業務が過分にのしかかっていませんか?
また、プライベートな事情(介護や結婚などで環境が変わった、繁忙期・年末調整などの特殊な事務が発生している等)で帰っても休めていない社員がいる可能性があります。
本人としては「がんばればできる!」と思いたい部分もあるでしょうが、身体を壊さないこと・健康で能力を最大限発揮してもらうことが企業として最優先の事項です。
業務量や得意なこと・苦手なことを元にした負担の再分配を行い、「本人の能力内で終わる」仕事量を目標に調整を行っていきましょう。
“話せる”場所に、企業自身がなること
適応障害を抱える従業員は、それぞれに原因は異なるものの「強いストレス」を感じています。
まずは企業がその原因になっていないか、ストレスを吐き出せる・つらいと感じていることを言葉にできる場所を設けましょう。
先の業務環境を整える点にも通じますが、不安やわからない点をすぐに誰かに聞くことのできる環境やタイミングはどの業務を行う時にも重要です。
意見を表現しやすい方法は個人個人異なりますから、会話だけでなくSNSやチャットツールなど「コミュニケーションの取りやすい環境」の選択肢を広げてあげることが大事ですね。
また、働く中で感じるストレスだと同じ部署の人間には吐き出しにくいこともあるでしょう、社外相談窓口や社内で地域別のコミュニティなどを周知紹介するなど部署や業務の垣根を超えた関係の構築を促してはいかがでしょう。
メンタルケアにおける企業組織の強みは、何においても「同じ境遇の人間が複数いる=相談できる人の選択肢がある」事です。

適応障害やストレスから来る不調は感染症のように一度罹患すれば免疫ができるようなものではありません。
決して他人事ではなく、誰もがなる可能性が十分ある「身近な、不調の入り口」であることを理解していただければと思います。
社員が適応障害になった場合には、本人のつらさに耳を傾けて根気よくその回復をサポートできるよう企業の配慮として何ができるか一度考えてみませんか。

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
〔参考文献・関連リンク〕
- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所:
知ることからはじめよう こころの情報サイト
「こころの病気について理解を深めよう」
「こころの病気を知る」 - 日本医療・健康情報研究所/創新社:「五月病」に対策するための5つの方法 今日から始めるストレス対処法
- すぐに役立つ暮らしの健康情報-こんにちわ2010年5月号:メディカル・ライフ教育出版
| 初出:2020年10月15日 / 初出:2025年1月31日 |