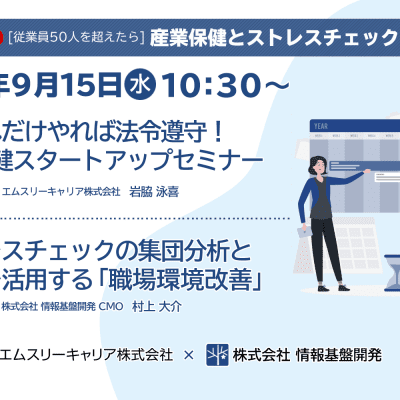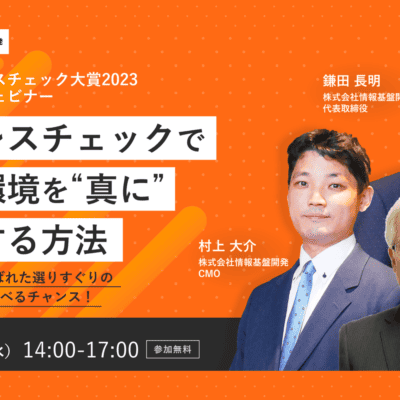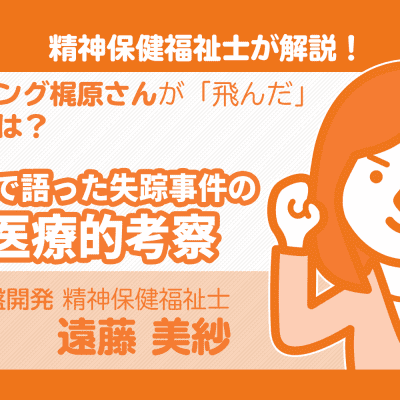「職場のメンタルヘルス対策の推進」を含む改正労働安全衛生法が2025年5月14日に公布され、ストレスチェック実施の全事業場義務化(従業員50人未満の事業場についてストレスチェック実施を努力義務とする附則の撤廃)が決定しました。
8月20日に厚生労働省管轄下で「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」を再開。11月20日に開かれた第9回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会では、協議の中で「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」にも触れ、同マニュアルの来春公表に向けた準備が着々と進められています。上記を受けて、関連セミナー編集版の再配信を【2025年12月15日(月)18時】まで期間延長致しました。
※再配信視聴の受付は終了いたしました
従業員50人以上の事業場に義務付けられているストレスチェック。2015年12月の労働安全衛生法改正により義務化されてから、まもなく10年目を迎えます。
「企業の義務としてストレスチェックは年1回実施しなければならないもの」という認識は浸透してきた一方で、せっかくストレスチェックを実施しても結果の活用の仕方が分からず、やりっぱなしになっている、高ストレス者となった社員が医師の面談を受けてくれないなど、「本当にストレスチェックは効果があるのか?」「ストレスチェックを実施しても意味がないのでは?」といった声が聞かれるのも実情です。
人事・労務のご担当者からも、ストレスチェックの有効性(エビデンス)に関する疑問・質問や、従業員のメンタルヘルス対策や職場環境改善の方法についてのご相談が度々寄せられます。
長年に渡りストレスチェック制度の検証や実効性向上に尽力され、ストレスチェック制度の第一人者の一人として知られる、北里大学医学部・公衆衛生学教授の堤明純氏によると、ストレスチェックは「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、ストレスへの気づきと対処の支援、職場環境改善に関しては、エビデンス(科学的根拠)が多数出てきている」といいます。
では実際のところ、ストレスチェックにはどのようなエビデンスがあるのでしょうか?
ストレスチェックにエビデンス・有効性はある
ストレスチェック制度は、労働者の心理的な負担の程度を定期的に測ることで、「従業員のセルフケア」と「事業者による職場環境の改善」を促し、従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを主な目的としています。
これを「一次予防」といいます。この一次予防に関するエビデンスは、実は数多くあります。ストレスチェックを実施した企業や労働者からの聞き取り・分析調査などからわかってきました。
例えば、調査対象者の約50%がストレスチェック受検により「自身のストレスを意識するようになった」と回答し、半数以上の事業者が「社員のセルフケアへの関心度の高まり」を実感したという調査や、ストレスチェック実施とその結果をもとにして職場環境改善を行ったことによって、ストレスが減ったり、パフォーマンスが向上したという結果も出ているようです。


いずれもセミナースライドから抜粋
なぜ「ストレスチェックは意味がない」と言われるのか?
では、なぜ「ストレスチェックは意味ない」と感じる人が多かったり、今一つ効果を実感できていない現状があるのでしょうか。
そもそもストレスチェック制度は、職場のメンタルヘルス不調の「一次予防」を主眼としたメンタルヘルス対策の一部です。そのため、ストレスチェック単体での効果や、客観的な数値指標を使ってその効果を測るというよりも、ストレスチェックの実施結果を集団分析してその職場特有の課題を明らかにし、職場環境改善を通じて総合的な対策を講じることで効果が見込めるもの、という前提があります。
また、ストレスチェック制度を活用してストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然防止するために、職場環境改善を行うことで得られる「一次予防」の効果に対してはエビデンスが出ている一方で、ストレスチェックを実施することによって高ストレス者を見つけ出し、医師面接等を通じてメンタルヘルス不調者への対応を行う「二次予防」のエビデンスはまだ少なく、今後さらなる分析・調査が待たれます。
しかも、現状では「高ストレス者」と判定された人のうち、医師面接を受けた人の割合は1割に満たないという厚生労働省のデータもあり、さらに別の調査では、高ストレス者と判定されても「何も行わなかった」と回答した方の割合が半数を超えていたことなどから考えても、ストレスチェックをただ実施しただけではメンタルヘルス不調者を減らすことにはつながらず、ストレスチェック後の対応にもまだまだ課題があるといえそうです。
つまり、ストレスチェックを実施して高ストレス者を割り出し、医師面接の機会を提供しただけでは意味がなく、効果も限定的ですが、ストレスチェックと併せて、従業員のセルフケア対策や管理監督者研修などを行い、メンタルヘルスに関する意識を高めることや、ストレスチェックの集団分析を活用して職場環境改善を行うことで、きちんと効果がある・意味があるものにしていくことが大切なのです。
義務だから実施するだけでは意味がない
―ストレスチェックのデータを活用した職場環境改善が効果的
冒頭で言葉をお借りした、北里大学医学部・公衆衛生学教授の堤明純氏は、厚生労働省公表の『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』では検討会の委員として作成に携わり、全国の事業場がストレスチェックを含むメンタルヘルス対策や、集団分析を活用した職場環境改善に取り組む際の参考となるよう、業種や事業場ごとの課題や解決のための工夫例をまとめています。
弊社のセミナーにも度々ご登壇いただき、ストレスチェックのエビデンスや、ストレスチェック実施後の集団分析データを活用した職場環境改善の具体例をまじえて、取り組み方を詳しく解説していただきました。
ポイントは、
- ストレスチェックで見かける「仕事のストレス判定図」は、エビデンスが積み重なったグラフ
- 『職場環境改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクションチェックリスト)』の活用の仕方
図表の見方に加えて、それぞれの企業・事業場の既存の資源を活用しながら、低コストで改善できる優先対策を検討するのに有効なアドバイスをいただきました。
また、実際の企業の現場で行った従業員参加型の職場環境改善の事例は、多くの職場でも応用できるヒントが詰まっています。
ストレスチェックをやりっぱなしにするだけでは意味がないと感じているけれども、「何から始めればいいのか分からない」「課題に対して、どのように対応すれば改善につながるのか分からない」といったお悩みをお持ちの人事・労務担当者の方々にも、きっとためになるはずです。
ストレスチェック制度等の見直しでどのような検討が進められてきたのかについても言及していますので、この機会に是非ご視聴ください。
● 登壇者プロフィール

【講師】
堤 明純(つつみ あきずみ)氏
北里大学医学部公衆衛生学 教授
厚生労働省「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」検討委員会 委員
日本産業ストレス学会 理事長
自治医科大学医学部卒業。岡山大学大学院 衛生学・予防医学分野 助教授、産業医科大学 産業医実務研修センター 教授を経て、2012年より北里大学医学部にて教鞭をとる。日本産業ストレス学会 理事長、日本産業衛生学会 副理事。労働とストレスの健康的な影響とその予防や、労働者の健康の社会格差・メカニズムの解明とコントロールに関する研究などに精力的に取組んでいる。
専門分野は、産業医学、公衆衛生学・健康科学、疫学・予防医学。
受賞歴に日本行動医学会「第17回内山記念賞」(2015年)、令和3年度「厚生労働大臣 功績賞」(2021年)、令和4年度「中央労働災害防止協会 顕功賞」(2022年)、日本産業衛生学会「学会賞」(2023年)ほか。令和7年度「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」功労賞を2025年7月に受賞。
主な著書(共著)に『公衆衛生学:社会・環境と健康』『基礎から学ぶ健康管理概論』『行動医学テキスト』、『職場におけるメンタルヘルスのスペシャリストBOOK』、『職場のラインケア研修マニュアル』など。
オンラインセミナー再配信の視聴は、下記フォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。
お申し込み完了後、視聴方法などを記載したメールを送付致します。
当記事は、2024年8月21日にライブ配信で行った堤明純氏登壇オンラインセミナー&質問会再配信に伴い、講演トピックスの一部を抜粋して23分弱に再編集したミニセミナーです。
関連セミナー編集版配信を【2025年12月15日(月)18時】までご視聴いただけます。
再配信視聴後、視聴者アンケートにご回答いただいた方へ下記の特典資料を提供致します。
● ストレスチェック制度の効果検証に係る文献情報 ※PDF
※同業サービスご提供の方からのお申し込みはご遠慮ください
この機会に是非ご視聴ください。
〔参考文献・関連リンク〕
- 情報基盤開発:
堤明純氏登壇オンラインセミナー&質問会「ストレスチェック義務化10年目を総括 有効性、制度見直しなど堤教授にズバリ聞く!」(2024年8月21日開催)
M-ORIONプロジェクト特設ページ - ニッセイ基礎研究所:
職場におけるストレスチェックの現状~ストレスチェックの効果検証と、小規模事業所の実施や集団分析の実施が議題に - 厚生労働省:
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
第9回資料(2025年11月20日開催) - 首相官邸:
令和7年3月14日(金)定例閣議案件
| 初出:2024年09月19日 / 編集:2025年12月15日 |