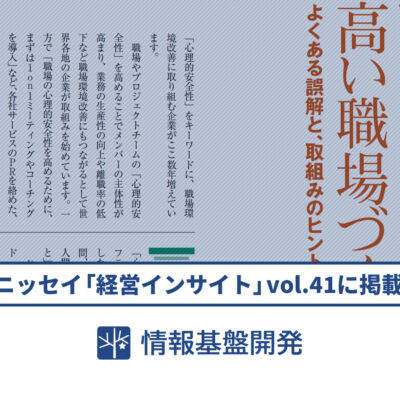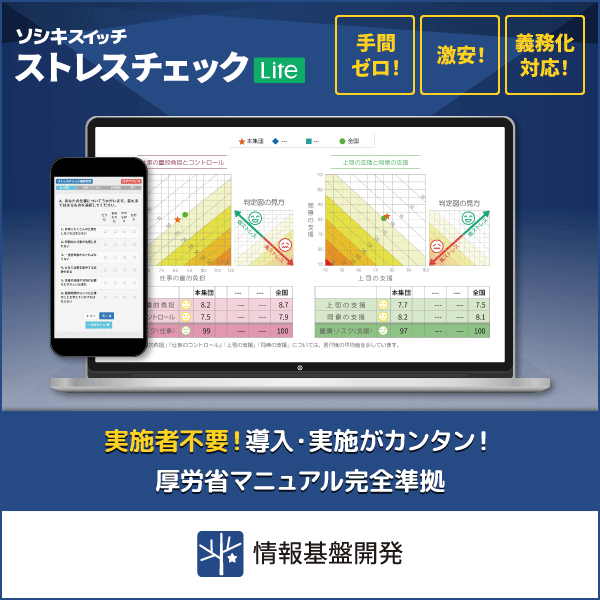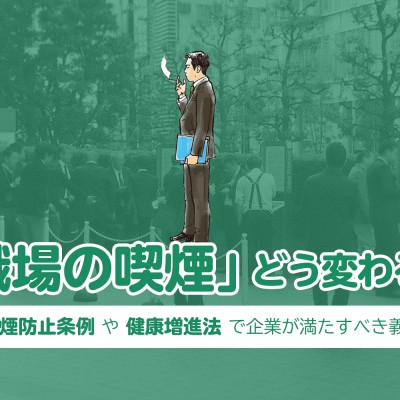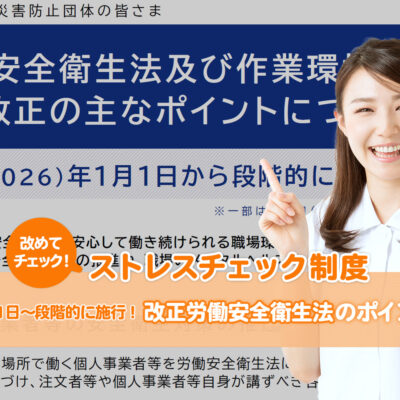自分自身では気づいていない認識や見方のゆがみ、「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」を知っていますか?
「えっ!?これもアンコンシャス・バイアスに入るの?」
「こんなの『常識』でしょう?」
と思ってしまっていることこそが、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)です。
働き方の多様化やダイバーシティー(多様性)の理解、ジェンダーの問題などへの取り組みが企業に求められる時代、このアンコンシャス・バイアスへの気づきと対処は、個人にとっても組織にとってもポジティブな効果をもたらすと注目されています。
誰もがもつ「アンコンシャス・バイアス」とは?
アンコンシャス・バイアスとは、無意識の偏見や思い込みのことです。
私たちの脳は、育った環境や過去の経験などの影響を受けて、知らず知らずのうちに偏ったものの見方をしています。
普段の生活の中で、次のように感じたことがある方はいませんか?

ある一定のことがらや社会集団に対して抱く「共通と思うイメージ」を、社会心理学では「ステレオタイプ( 類型化 )」といいます。この無意識のうちにあるステレオタイプが言動・判断・感情に現れてしまい、現実とネガティブなズレを生じる状態が「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」です。
ステレオタイプ自体はすべてが悪いものとは限りません。 どこにでも・誰でもが持っている「当たり前・常識」ともいえます。
ステレオタイプやバイアス(先入観・思い込み)が生まれるのは、「柄が違っていても、猫だ」「カラスと鳩が見わけられる」など、対象の要素をカテゴリー分けして素早く認知・判断するために発達した脳の機能によるものです。
偏見がハラスメントにつながる危険性
人や物の特徴をカテゴリーに分けて認識しやすくすることは、便利ではありますが、それゆえ極端になりやすいものです。例えば、「男性は論理的で、女性は感情的」「看護師は優しい女性が多い」などのように職業・性別・人種などその人の目に見える要素と個人の性質や行動とを根拠なく結びつけてしまい、無意識のうちに「同じ特徴をもつ人には共通にあてはまる」と考えてしまう原因になりがちです。
さらに、厄介なのは「その社会・環境では、当たり前」とされているために、自分では気づきにくいこと。これがアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)にハラスメントやトラブルの危険が潜んでいる理由です。
本当は一人ひとり性格も考え方も異なるにもかかわらず、自分の中にある固定観念やイメージがもととなって「〇〇なはずだ」と思い込んでしまうクセを私たち人間が共通して持っていること。それに気づくことがまずは必要です。
2025年6月には労働施策総合推進法の改正が公布され、カスハラ、セクハラをはじめとする「職場のハラスメント対策強化」が打ち出されました。今後「人間の間違ってしまいがちなクセ」を知ることはますます大切になってくるのではないかと思います。
ちょっとした気づきと工夫で、日ごろのコミュニケーションや職場の人間関係に変化がみられるかもしれません。
アンコンシャス・バイアスの具体例
アンコンシャス・バイアスにはさまざまなものがありますが、ここでは職場で起こりがちな例をあげてみました。
次のようなことに、思い当たりはありませんか?

繰り返しになりますが、アンコンシャス・バイアスは、わたしたちの本人の意図や思考とはまた別のところで、過去の経験やまわりの価値観から影響を受けた「偏見」のこと。そして、いつのまにか「当たり前の常識」となって、言動に現れてしまうものなのです。
そのため、「自分は人種で差別しない」「男女平等に取り扱えている」と日頃から思っている人であっても、実際のケースになると疑問に感じることもなく、偏った見方をしてしまう・受け入れてしまう可能性があります。
さらにバイアスは国籍や人種、出身地、性別に限らず、年齢・学歴・役職や経済状況……、私たちが何かを「区別する」ときのさまざまな見方・考え方と深く関わっています。
「最近の若者は…」「シニア世代は…」「派遣社員は正社員より〇〇だ」などのよくある言い回しも、実は偏見を含んでいることに気づく必要があります。
アンコンシャス・バイアスが生まれやすい状況
では、どのようなときに特に偏見が生じやすいのでしょうか?
Googleの社内教育「Unconscious Bias @ Work」では、次の4つの要因があると分析しています。
<アンコンシャス・バイアスを生む4つの要因>
1.ステレオタイプとの不一致
2.少数派に対する固定観念
3.不十分な情報
4.認知資源の制約
(出典:Google Unconscious Bias @ Work)
職業イメージは特にステレオタイプと結びつきやすい傾向にあります。
「保育士や看護師は女性の方が向いている」
「システムエンジニアは男性の方が向いている」といったイメージは根強く、採用や配置に影響することもあります。
また、少数派(マイノリティ)やあまり身近ではないもの対してはより強く固定観念を抱きやすい傾向にあります。
「保守的な日本企業に外国人求職者が応募してきた際、社風に合わないと採用が見送られる」
「女性の多い職場で「前例がないからと男性の育休取得が却下される」
など、当事者に差別の意識がなくても、結果的にバイアスが働いてしまうこともあるのです。
特にまだ詳しく相手のことを知らず十分な情報がない場合に、限られた情報や短時間で判断する必要があったり、従業員などの個人に対して興味を持ち向き合う努力がなければ、無意識の偏見で相手を判断してしまう可能性があるといわれています。
アンコンシャス・バイアスは、無意識だからこそありふれていてとても厄介なのです。
誰かに指摘されたり、意識するきっかけがなければ、自分が偏見を持っていることにも、その偏見で無意識に人やものごとを判断してしまっていることにも気づくことができません。もし適切に対処しなければ、気づかぬうちに差別やハラスメントにつながり、組織のパフォーマンスや従業員一人ひとりの心身の健康に大きな影響を与えてしまう場合もあるのです。
ハラスメント対策の第一歩は、自分のバイアスに気づくこと
もし、あなたの上司や組織のリーダー的な立場にある人が、次のような行動をしていたら、あなたはどう感じるでしょうか?
眉をひそめる。腕組みをする。目を見ずに軽くあしらう発言をする……
悪気はまったくないかもしれませんが、おだやかな気持ちはしないですよね。
では、
「育児中の女性は仕事の負担を軽くした方がよい」
「男なのに育児をしなきゃいけないのは大変だから責任のあるポジションから外してあげよう」
と言われたらどうでしょうか?
もしかしたらその人のなりの優しさや常識的な配慮からの発言かもしれませんが、不快な気持ちになったり、「ここでは自分の思うような働き方を実現するのは難しい」「休暇や休業を申請しづらい」など、ストレスに感じる人もいます。場合によっては、ハラスメントの訴えや離職などの深刻な問題につながることもあるのです。
アンコンシャス・バイアスは、どんな組織にも、私たち一人ひとりの中にもある身近なもの。
まずはバイアスがあると知ること、意識をすることが大事です。
そして、組織全体で「無意識の影響」に対し、取り組んでいく必要があります。
冒頭でもお伝えしましたが、「アンコンシャス・バイアス」への気づきを促す研修は、近年、さまざまな企業や組織、自治体職員の研修にも取り入れられはじめています。
「もしかしたら、これはアンコンシャス・バイアスかも?」
「無意識の振る舞いや言葉がけが、ハラスメントにつながってはいないだろうか?」
まずは一度立ち止まって、振り返ってみることからはじめてみませんか?

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
〔参考文献・関連リンク〕
- 一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所
- 日本の人事部:アンコンシャス・バイアス
- 日本健康学会誌:「アンコンシャス・バイアスという見えない壁」
- Google Cloud Japan:
Google の Unconscious Bias @ Work 〜偏見を排除し共通認識を確立、共通の言語で議論を行うための土台作り〜
| 初出:2021年02月26日/編集:2025年9月29日 |