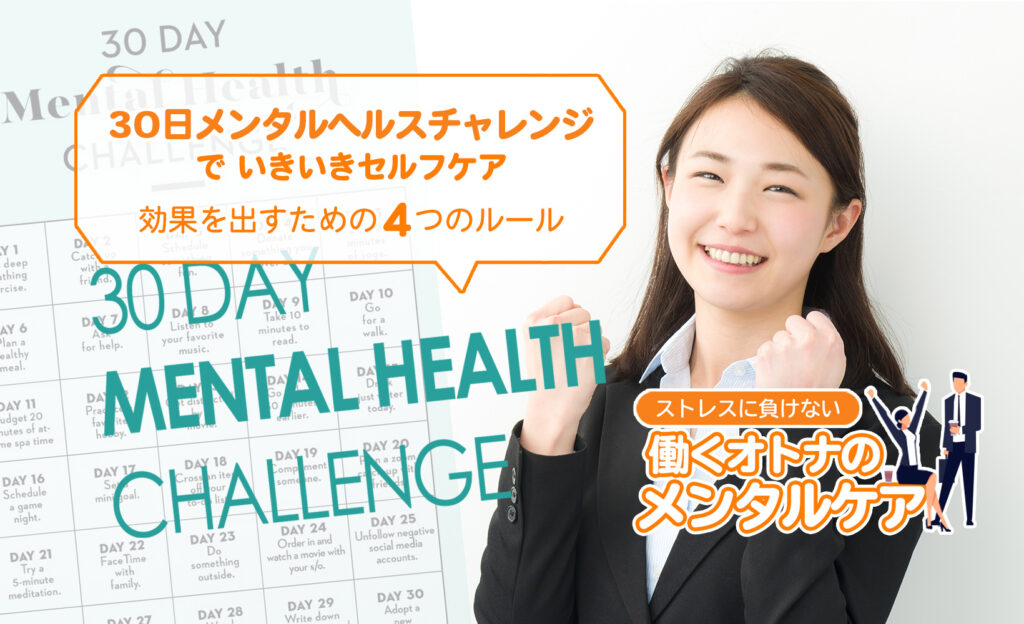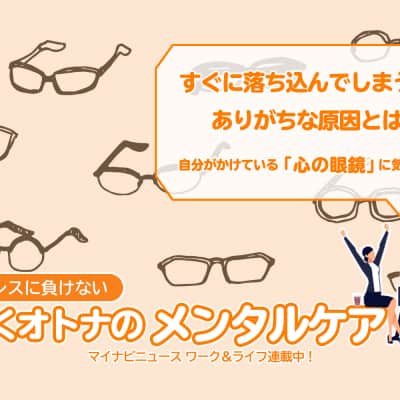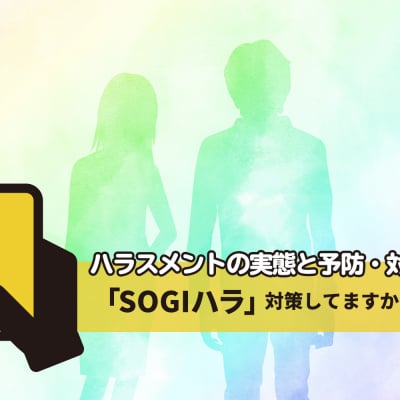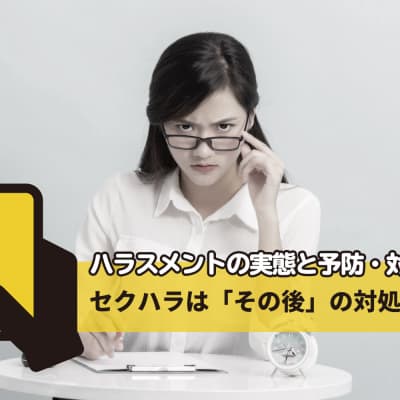毎日さまざまなニュースが飛び込んできますね。
相談室にも「なんとなく疲れて眠れない……」「なんだかずっとイライラしている」という人が増えています。その疲れは繰り返す不穏なニュースによる「不安疲れ」かもしれません。
目に見えないニュースやメディアに振り回されない、心のキーポイントをご紹介します。
人間は「見えないものが不安」
人間の基本的な思考パターンの一つに「問題やトラブルを避けるために準備をしたい」というものがあります。簡単なものだと「道にあいている穴を避ける」など、普段から無意識に行っている行動にもみられます。
「道にあいている穴を避ける」というのは穴が見えているからできることです。先の見えない将来や、未知のウイルスとの遭遇いったどういう行動をしたらいいのかわからない状況では、落ちつかなさを抱えたままになってしまいます。
ワイドショーや繰り返し流れるニュースで、ずっと「よくわからない情報」を見続け、不安を感じると生物の体の中もとても「不安定」な状態になるので、ついつい自分が感じている日常のイライラや不満を強く感じてしまいがち。
不安や心配の多くは、「こうなるのではないだろうか」という事実ではない予感や憶測から生まれます。なるべく早く何に対して不安を感じているのか、「不安の正体」を突き止めて安定させてあげましょう。

「ニュースを見て不安になった」なら、どんなニュースを見たのか、そのニュースのどこが嫌だ・怖いと感じるのかを言葉にしてみてはいかがですか。対象をはっきりさせることで、不安の落ちつかなさを「何とかしなくちゃ」「何ができるかな?」という行動力に変更することができます。
「疲れちゃったな……」と感じるときは、一日の中で2時間、ニュースやSNSから離れて音楽・読書・映画やスポーツなどの「楽しいことを積極的にする時間」にしましょう。ぬいぐるみや生花など、五感に訴える「かわいい」「カラフル」なものに触れていると気分も自然とほがらかになりますよ。
おすすめはお風呂やお茶など、「香りと触感を楽しめる」レクリエーションです。生活の中からちょっとした楽しみを見つけるチャンスになるかもしれませんね。
デマを広げないための「こげたすし」

不安に対して「何かしなきゃ、したい」と思ったときこそ、気を付けなければならないのが「誤った情報・根拠のない噂」です。心が不安定なときは「納得したくなる、信じたくなる情報」や「周囲でよく耳にする情報」につい頼ってしまいたくなるため、普段は冷静な人でも、情報の真偽を確かめるゆとりがなくなり、デマに影響されやすくなってしまいます。
自分にそのつもりがなくても、「○○に効く!」と取り組んだことに意味がなかったり、良かれと思って情報を広めたらデマを広げる手伝いをしてしまったり……なんてことがあると疲労感も倍以上に感じるでしょう。
「これは」と思う情報に出会ったら、SNSやメッセージを送る前に一度画面を閉じて大きく深呼吸。その後あらためて、デマを広げないための「こげたすし」を確認してみてください。
- こ:【厚労省などのパブリックな機関が発信している情報か?】をもう一度確認
- げ:【限定的な表現(○○だけ!・××なら!)】は要注意
- た:【確かな証拠や根拠があるか】一度自分で確かめる・人に会って聞いてみる
- す:【すぐにシェア!】はデマの決まり文句
- し:【友達の知り合い・「信頼できる人から聞いたんだけど」】はちょっと待って
※弊社自作の標語です
「当たり前の生活」が今一番大事
WHO(世界保健機関)がコロナ禍に際して公表したリーフレット「COVID-19流行によるストレスへの対処」をご覧になったことはありますか?
健康情報に限らず、根拠の不確かな情報を目にする機会が増えたように感じてしまう状況にあることは、現在もそれほど大きな差はないのかもしれません。
リーフレットには「この状況では悲しみやストレス、恐怖、怒りを感じるのは普通のことです」として、事実確認・健康的な生活・人との関わりを保つことの重要性を訴えています。
「親しい人とちょっとした雑談をして笑いあう」「外に出て日差しを楽しみながら運動をしてみる」「おいしい食事を楽しむ」「夜はぐっすり眠る」……。そういった「当たり前の生活」こそが健康、ひいてはウイルスに負けない心と体を作る基礎。不安を感じる生活が長引いてしまい、体の抵抗力が弱まり、より心が過敏になってしまう……というサイクルは、東日本大震災のときにも問題になりました。そういった「焦げつき」を避けるためにも、不安を乗りこなし、新しい季節を迎えましょう。
不必要な焦りや不安で疲れてしまわないよう、楽しみを捨てず、ほがらかに暮らしていきましょう!

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
〔参考文献・関連リンク〕
- WHO(世界保健機関):COVID-19流行によるストレスへの対処法
- 日本精神神経学会: 2019 年新型コロナウイルス(2019-nCoV)に対する日本での反応:メンタルヘルスへの影響と高リスク集団
| 初出:2019年09月26日 / 編集:2025年05月28日 |