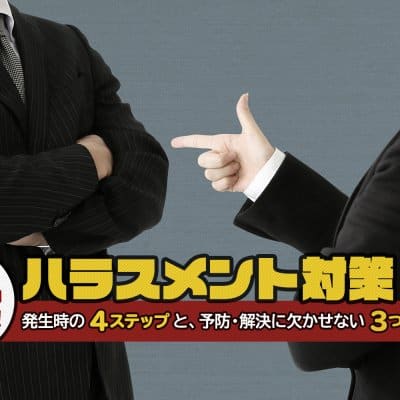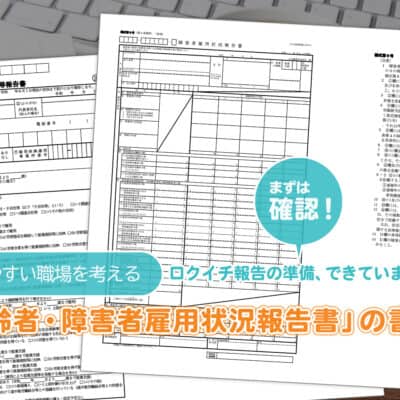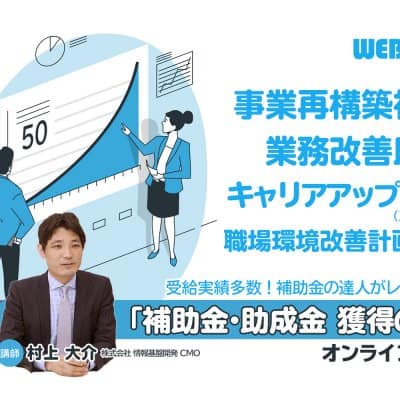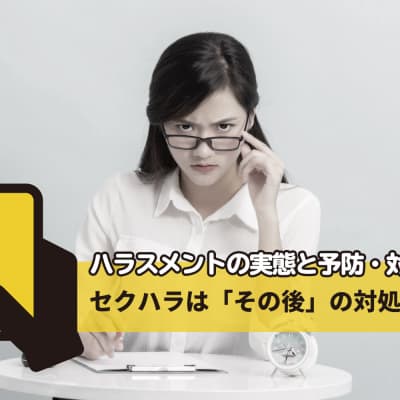2018年、障害者の法定雇用率の引き上げがより一層本格的に取り組まれることとなりました。
現行の規定では民間企業は2.2%、都道府県等の教育委員会では2.4%、国・地方公共団体は2.5%となっています。対象となる企業も従来の50人から「45.5人」に広げられ、今後各所で障害者の方と一緒に働く機会が増えていくことと思われます。
社会の流れとしても、障害の有無に関係なく一人ひとりの個性を生かして働けるようになることが求められます。けれど今の日本社会では障害のある人と接する経験が少なく、職場での接し方や悩みを抱えているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「企業として配慮を行わなければならないけど、自社環境ではどうしたらいいのか」……そんなお悩みを持つ企業担当者にお勧めしたいのが 【精神・発達障害者しごとサポーター】です。
この記事では「精神・発達障害者しごとサポーター」がどのように役立つのか、資格の詳細や期待できる効果について解説します。それぞれの個性を持った従業員が快適に働けるように、コミュニケーションで悩んでいる方は参考にしてはいかがですか。
サポートがあれば障害も個性に。
働ける人を増やす「知識の応援」を
「精神・発達障害者しごとサポーター」は「精神・発達障害についての正しい知識と理解を持って、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者」として同じ職場で働く方に対し、障害に対する正しい知識と対応・サポートを周知紹介するための制度です。
「どのような配慮をしたらいいのかわからない」「どのようなサポートが必要なのかわからない」 ……精神障害や発達障害を持つ方と一緒に働いた時、とまどった経験はありませんか。部下をまとめるような立場にある方はどんな業務をお願いすればいいのか、どう伝えればいいのかといったことでも悩まれたかと思います。
コミュニケーションに特性があるといっても、業務の遂行に関する能力には支障がないという方がほとんどです。業務の内容や方法さえ整えれば抜群の集中力を発揮してくれたというケースも数々報告されています。
「障害のある方が業務をきちんとこなし、その能力を存分に発揮できる環境を作るための応援」、それが「 精神・発達障害者しごとサポーター 」の目的です。
サポーターのメリットは、働く人・働いてもらう企業
双方の「安心」になる
グローバリゼーションが進む日本社会、よりよい社会参加を目指して国をあげての障害者雇用の促進が行われています。その活動の甲斐もあり精神障害や発達障害を抱える方の就業数も増えているものの、「半年以上、年単位で仕事を継続できる人材」という意味での評価は難しく、「人材の定着」「継続的な就労」が充分成されているとはいえない状況です。
精神障害や発達障害を持つ方が離職してしまう要因には様々なものが考えられますが、「精神障害や発達障害を持つ方たちが働きやすい環境が整っていない」ことが少なからず影響しているのではないでしょうか。
物理的な配慮を必要とする身体障害と異なり、精神障害や発達障害を持つ方へは「コミュニケーション方法」の配慮が求められます。特に感覚が鋭敏であったり人との関係の築き方に特性があるような方だと、「作業環境や業務指示の方法を他の人と変える」「普段の会話やコミュニケーションが独特であることを理解する」といった配慮も必要になります。
同僚となる周囲の方たちの理解とサポートが求められる場面も多いでしょう。
社内にサポーターを設けるメリットとして、「配慮の具体的な検討や実施がスムーズになる」「障害者本人と周囲のコミュニケーションを円滑化する」といった点が挙げられます。
障害が持つ特性についての正しい知識や基本的な対応方法を身につけたスタッフがいることで、どのような配慮を企画すればいいのか・業務や指示のどの点を改善すればいいのかといったことの客観的・具体的な計画が可能になります。
能力を発揮できる環境があれば、「長期的に活躍してくれる人材」としての成長も目指せるでしょう。
また、受け入れやすいコミュニケーション方法などを客観的に説明できるというのも大きなプラスに働きます。声のかけ方、スムーズな業務を行うための配慮、どんなことが苦手でサポートが必要なのかといったことを社内サポーター(先輩スタッフ)から説明してもらえることで、障害を持つ本人と周囲との摩擦を減らし職場に対する安心感を持ってもらうことができます。
サポーターの知識は求人や採用を行う時にも求められるでしょう。精神障害や発達障害のある方に対する基礎知識や必要なサポートの視点から、就業内容の説明をわかりやすく伝え求職者が求める支援やサポートをうまく聞き取るための「補助」が行えます。
職場内では同僚の精神障害者や発達障害者の業務上の悩みを相談しやすくなる、仕事の連携が取りやすくなる、障害のある方への対応に合わせることで健常な方の業務の効率化も進む……など、障害の知識を生かした職場環境の改善が見込めるでしょう。
養成講座は受講料無料!
全国の労働局・ハローワークへ相談を
「精神・発達障害者しごとサポーター」になるためには、特別な資格は必要ありません。
厚生労働省が行っている養成講座を受講すれば、サポーター活動が開始できます。
講座は90分程度で、講座の内容は主に「精神障害や発達障害の基本的な知識や必要な配慮について」となります。受講対象者は「現在企業に雇用されている」方ならだれでも、現在障害のある人と一緒に働いていなくても受講は可能です。
養成講座を受講するとネックストラップやシールといった意思表示グッズがもらえ、精神障害や発達障害に関して一定の知識と理解があるということを職場で示すことができます。
養成講座は各都道府県のハローワークや商工会議所などで 月に1回~2回 のペースで開催されています。養成講座の日程や参加申し込みは厚生労働省または各労働局のホームページから確認しましょう。
ハローワークから事業所へ講師を招く出張講座なども企画されています。詳しくはそれぞれの都道府県労働局へお問い合わせください。
企業としてもサポーターの推進を
知ることは誰でもできる“応援”です
障害の有無にかかわらず「働きやすい職場作り」は、人材の多様性や人手不足の解消につながります。
「障害がある方も働きやすい」ということは、組織の「一人ひとりを大切にする」という態度の表明にもなります。特に配慮が必要ということでクローズアップされていますが、 障害とされている「特性」も本当は私たちが当たり前に持っている 「個性」 の延長線上にあるものです。配慮や特別な対応の中には、障害に関係なく普段の生活や業務に取り入れれば業務の効率化に役立てることができるものもあります。
精神障害や発達障害を持つ方がのびのびと働ける環境は、「誰もが働きやすい」環境。多様な働き方や背景を許容できる企業は人材流出の防止や活躍に良い影響があるでしょう。
企業は従業員が精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を受講することに対して積極的になってみてはいかがでしょうか。
〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省:精神・発達障害者しごとサポーター
- 厚生労働省:障害者雇用率制度
- 厚生労働省:障害者雇用対策
| 初出:2019年12月12日 |