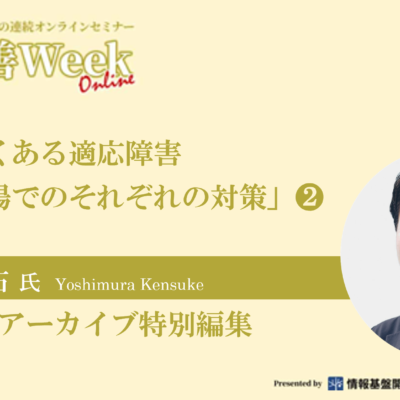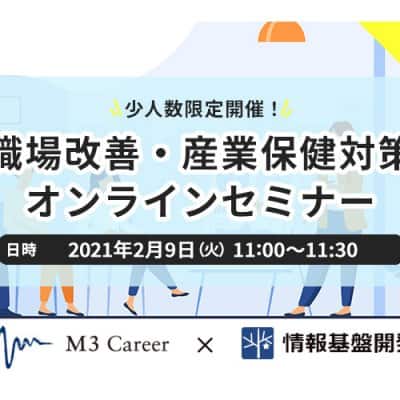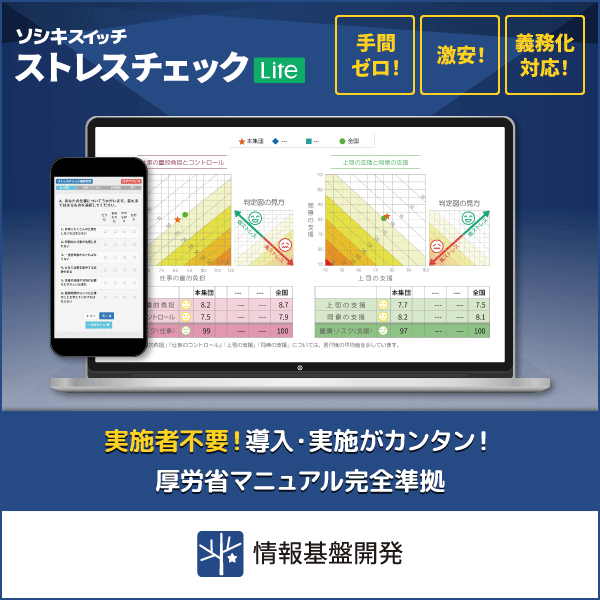従業員数が50人以上の企業で実施が義務となっているストレスチェック。
従業員の個人情報や心理的な部分を取り扱うため、慎重にならなければいけない処理もあります。初めて担当になった方は、どこから手を付けてたらよいのか分からず戸惑うこともあるかもしれません。
「何から取り組んでいいかわからない」
「どこまでが企業の義務なの?」
「外部委託する場合、どこまで自分たちで対応しなければならないの?」
と、多くの疑問が出てくるのではないでしょうか。
そこで、今回は “ストレスチェック虎の巻”【手順編】。
ストレスチェックの実施手順で、最低限押さえておきたいポイントをまとめました!
<人事・労務担当者が押さえておきたい4つのポイント>
①実施
②周知・勧奨
③結果通知・説明
④労働基準監督署へ報告
ストレスチェックは実施しただけでは終わらず、労働基準監督署への報告までが義務となります。うっかり実施をし忘れていたり、報告を怠ったりすると、場合によっては罰則の対象となることも……。しかし、この4つのポイントを押さえておけば、大丈夫です。企業として、担当者が行わなければならない点がわかります。従業員数が50人以上になりストレスチェックの義務の対象となった企業や、新しくストレスチェックを担当することになった方は必見です。
それでは、ストレスチェック実施の流れをみていきましょう。
①ストレスチェックの実施
ストレスチェックを実施するにあたっては、まず組織としてストレスチェック導入の方針を決定し、役割分担を決め、従業員に周知するという準備が必要です。準備の大まかな流れは次のとおりです。
実施の準備:
- 会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
- 次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
- 話し合って決まったことを社内規定として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。
- 実施体制・役割分担を決めましょう。
これらは職場の衛生委員会の場で話し合って決めます。
実施体制・役割分担は、下記の項目に沿って決めていきます。
<ストレスチェック実施準備のチェックリスト>
- ストレスチェックは誰に実施させるのか。
- ストレスチェックはいつ実施するのか。
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
- 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
- 集団分析はどんな方法で行うのか。
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より抜粋
― ストレスチェック実施は誰が担当になるのか?
ストレスチェックを実施するためには、「実施者」「実施事務従事者」「面接指導を実施する医師」が必要です。
- 実施者
ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、(厚生労働大臣が定める研修を受けた)歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師の中から選ぶ必要があります。 - 実施事務従事者
実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。
- 面接指導を実施する医師
ストレスチェックの結果で「高ストレス」と判定された従業員の面接を行います。
その他、ストレスチェック制度の計画をしたり、進捗状況の把握・管理をする「ストレスチェック制度担当者」を配置する企業もありますが、法令上は 「実施者」「実施事務従事者」を決める必要があるとされています。
― どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか?
ストレスチェックの調査票で最も一般的に使用されているのは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」です。基準となる「3つの領域(①仕事の要因、②心身のストレス反応、③周囲のサポート)」の質問項目が含まれていれば、57項目に限らず、衛生委員会等での検討を踏まえて独自の項目を追加することもできます。
最近では、ハラスメント対策などより職場環境改善に活用しやすい内容を追加した「新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)」を導入する企業も増えています。
「どの調査票を使ったらよいのか分からない」「せっかくやるなら職場環境改善に役立てたい」などと考え、自社の負担を少しでも減らしつつもストレスチェックをより効果のあるものにするために、外部に委託するケースも多くみられます。
②ストレスチェック実施の「周知・勧奨」と③「結果通知・説明」
ストレスチェック実施の準備が整ったら、会社としてストレスチェックを行うこと、その目的、具体的な日時や実施方法を従業員全体に周知し、積極的に受けてもらえるように受検を勧めましょう。
その際に大切になってくるのは、ストレスチェックがどのような目的で行われ、どのような意味があり、きちんとプライバシーが守られた状態で行われるものであることを伝える丁寧な説明です。
担当者の方は、下記のストレスチェック実施後の対応と合わせて、プライバシーの保護についても理解しておく必要があります。
実施・実施後の対応:
- 対象の従業員に質問票を配布し、ストレスチェックを実施。
- 記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収。
※第三者や人事権を持つ職員が記入済みの質問票や回答内容を閲覧することは禁止されています。 - 回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、「高ストレス」で医師の面接指導が必要な者を選びます。
- 結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から本人へ直接通知されます。
※結果は企業に伝わるものではなく、本人に通知されるものです。企業側が結果を知るには、必ず本人の同意が必要です。 - 結果は、医師などの実施者(または実施事務従事者)が責任をもって保存します。
※企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することも可能ですが、第三者に閲覧されないように、実施者(または実施事務従事者)が鍵やパスワードを管理しなければなりません。
ストレスチェック制度は、「労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組み」です。この点を念頭におき、情報の取り扱いに留意しなければなりません。ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者・実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となりますので、十分な注意が必要です。
また、不利益な取り扱い防止についても厳しく規定されています。ストレスチェックの結果から「医師による面接指導が必要」と判断された従業員は、本人の申し出により面接指導を受けることができます。面接の申出に限らず、そもそもストレスチェックの受検も従業員の任意であるため、受検や面接指導の申出の有無、結果を事業者側に提供しないことなどにより、解雇や雇い止め、不当な動機・目的による配置転換など、不当な取り扱いを行うことは禁止されています。
④労働基準監督署への「報告」
ストレスチェックと高ストレス者の面接指導の実施結果は、労働基準監督署に報告しなければなりません。所定の様式『心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書』に記入し、毎年1回行います。ストレスチェック実施と労基署への報告はセットで覚えておきましょう。
労働安全衛生法では、ストレスチェックは毎年行わなければならないと定められていますが、労働基準監督署への報告書提出に期限は特に定められておらず、事業所ごとに設定して構わないとされています。しかし、不要なトラブルを避けるためにも、ストレスチェック実施後なるべく速やかに提出することを心がけたほうが安心です。
また、ストレスチェックの実施者を外部に委託する場合も、「事業者が選任した産業医」が結果を確認し署名をする必要がありますので、担当者の方は手順を把握しておきましょう。
『心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書』の様式 は厚生労働省サイトからダウンロードできます。
2025年1月から電子申請が原則義務化される予定もあり、「e-Gov電子申請」未登録の法人は登録手続きを進めておかれることをお勧め致します。
※記事末【参考文献・関連リンク】「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果 参照
外部に委託してもOK!
「ストレスチェック実施者をどうやって探してよいのかわからない。」
「ストレスチェックの対応が通常業務に影響し、負担になっている……」
など、自社で対応が難しい場合には外部の機関に委託することも認められています。ストレスチェックは実施後にも個人情報の保管や高ストレス者の選定後の対応など、実施後の結果を踏まえた対応・事務が続きますので、適切な委託先を選ぶことができれば、コストダウンにもつながります。
外部委託業者はそれぞれ特徴があります。
高ストレス者の対応が手厚い、分析が迅速、独自のサービスを行うことができるなど自社に合った委託先を選定するためにも、まず社内でストレスチェックに必要な項目や実施イメージをつかんでおくことが大切です。
4つのポイントを押さえてストレスチェックを実施
<人事・労務担当者が押さえておきたい4つのポイント>
①実施
②周知・勧奨
③結果通知・説明
④労働基準監督署へ報告
以上、担当者が行うべきポイントにしぼって、ストレスチェックの流れを解説してきました。全体像と担当者の役割がなんとなく掴めたのではないでしょうか。
労働安全衛生法では、ストレスチェックの結果の集団分析を行うことが努力義務とされています。ストレスチェックはやりっぱなしで終わるのではなく、組織の体制に応じて「その結果を部署ごとやグループごとに分け、経年で比較・分析することで職場環境改善につなげる」仕組み化を法人側で主体的に行っていかなくては効果を実感することができません。どの集団が、どういった状況でストレス負荷が高くなっているのか等を把握することで、離職防止や従業員エンゲージメントを高めるための対策に活用することができます。
ストレスチェックは、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みですが、働きやすい環境を整え、企業の生産性を向上することも大切な目的のひとつです。
ここまで見てきたように、ストレスチェックの実施には準備から実施後の対応まで、やらなければならないことがたくさんあります。企業の義務(※50人未満は努力義務)とはいえ、担当者の方にとってはなかなか負担も多くなってしまいます。それだけでなく、せっかく実施したストレスチェックも、適切な対応・対策ができなければ組織の課題を解決することは難しいでしょう。
実際に導入準備をする中で、「集団分析や結果の見方がわからず、今ひとつストレスチェックを活用できていない……」「外国人の従業員のストレスチェックはどうするの?」など、さまざまな疑問やお悩みも聞こえてきます。
外部に委託する企業が増えているのは、そのような背景が少なからずあるのではと思われます。
ストレスチェック実施のお悩みは、
情報基盤開発にお問い合わせください
おかげさまで、昨年2024年単年度の導入実績4,800社・150万人!
厚生労働省マニュアル準拠、実施者代行や医師面接代行、産業医紹介等のオプションサービスも豊富な「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(旧称 AltPaperストレスチェック)のご利用を是非ご検討ください。
下記のフォームより、最新の「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」サービス案内資料のダウンロード、ならびにお気軽にお問い合わせください。
〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省:
ストレスチェック制度導入ガイド
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申結果
ストレスチェック制度に関する法令
厚生労働省令第九十四号 通知
改正労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度について
ストレスチェック制度の実施状況
ストレスチェック制度関係 Q&A - e-Gov電子申請:電子申請について
| 初出:2018年08月30日 / 編集:2024年08月14日 |