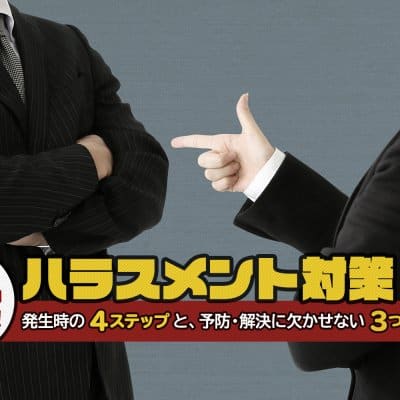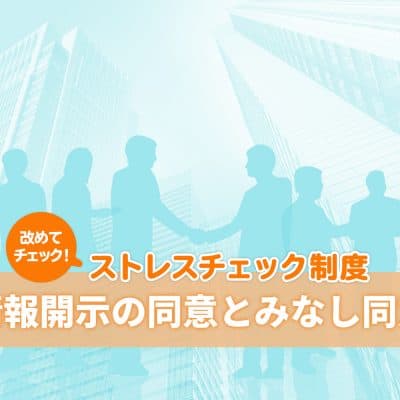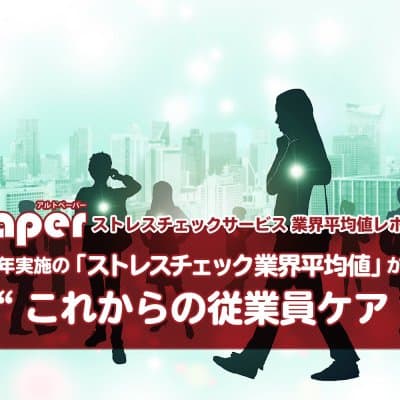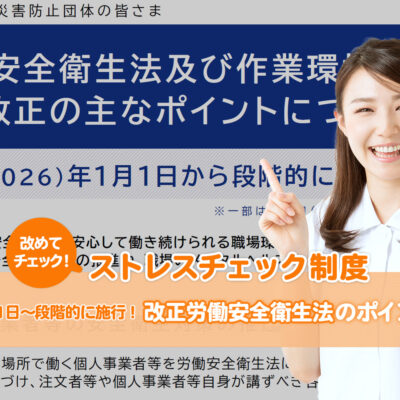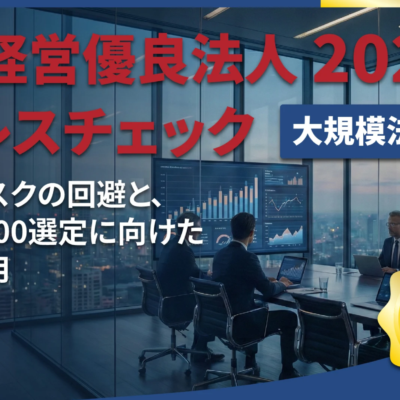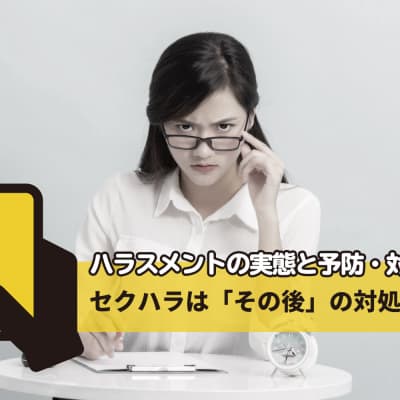ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)を目的としています。
一次予防のためにはまず「環境」を整えること。
環境を整えることで従業員のストレスを減らし、生産性や職場の働きやすさを向上させるねらいがあります。そのためにも改善策の検討材料となる「データ」は欠かせません。
ストレスチェックは「改善のためのデータ採取」という一面も備えています。
よりよい改善策を考えるためにも、ストレスチェックは全従業員に受けてもらいたいもの。同じように実施する健康診断と違って、ストレスチェックは「心の健康状態」という非常にデリケートな部分を取り扱うため、従業員には参加義務はありません。
また会社は従業員本人の同意がなければ結果も見ることができないため、「本当はケアが必要な人が、もっといるのではないか?」と心配されている企業担当者のお話も伺いました。
労使双方にメリットのあるストレスチェックですが、個人情報の取り扱いや実施後のケアに関しても慎重な配慮が定められているとはいえ、そもそもストレスチェックとはどういうものなのかをよく知らないと、従業員にとっては参加に抵抗があって当然でしょう。
しかし、ストレスチェックを会社の発展につなげるためには従業員の協力が欠かせません。
そのためには何よりも制度を理解してもらうことが重要です。
「効率的な予防」のために、受検率UPをねらって「効果的な周知」に取り組んでみましょう!
ポイント1:ストレスチェック制度の目的を明示する
自分の会社でストレスチェックを行うとき、従業員にどのように説明していますか?
ストレスチェックを「うつ病予防」や「メンタルヘルスの不調を見つける」と説明していたら……ちょっと立ち止まってみてください。ストレスチェックの目的を「メンタル不調者の発見」と考えてしまっている従業員がいるかもしれません。
またストレスチェックの結果によって、不利な取り扱いや不当な人事評価をされてしまうのではないかと心配する従業員もいるでしょう。
ストレスチェック制度では心の健康の問題という非常にデリケートな内容を取り扱います。
専門知識や制度についてきちんとした理解がない場合、ストレスチェックの目的について端的に説明するのは難しいでしょう。言葉選びを間違うと、様々な誤解が生じる可能性があります。
まず周知の第一歩目は「ストレスチェックはメンタルヘルスの不調者を発見することが目的ではない」という点を知ってもらうことにあります。
「セルフケア」や「職場環境改善」という言葉を使って、「自分のストレス状態に気が付くこと」「セルフケアのヒントのため」ということを初めに説明しましょう。
冒頭でも述べた通り、ストレスチェックは不調を未然に防ぐ「一次予防」が目的です。
口頭説明・ポスター掲示など方法は何でも構いません。不安に感じる従業員まで情報がいきわたるよう、折に触れて繰り返し説明を心がけましょう。
ポイント2:結果の取り扱いについて説明する
ストレスチェックは「事業者」が行う制度です。
実施責任者は事業者(社長等)、制度担当者には人事部の方(人事部長等)がなるケースが多いと思われます。
実施事務従事者には人事権がない方が就くよう定められていますが、業務内容的に総務や人事といった部署の方が中心となることが多いのではないでしょうか。
したがって、社長や人事部長等の人事権をもつ人にストレスチェックの結果が伝わり、評価につながるのではないかと心配する従業員がいるかもしれません。
ここで強く説明してもらいたいのが、「個人情報は企業が見ることはできない」というポイントです。
個々の従業員のストレスチェックの結果を取り扱う実施者は医師や保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師の有資格者です。これらの人達には職業倫理として、「個人情報に関する守秘義務」が課せられています。
また、同じようにストレスチェックに関する個人情報を取り扱う実施事務従事者にも、ストレスチェックの指針で守秘義務を守るよう課されています。
企業によっては実施事務従事者についた従業員にも守秘義務について誓約書を書くようフローを設けていたりします。
ストレスチェック実施後の結果においても、しっかりと個人情報は保護されます。
ストレスチェックの結果は健康診断の結果と同様の「要配慮個人情報」です。個人情報保護法に基づいて、受検した本人の同意なくしては企業や上司、同僚などに開示されることはまずありません。
同意をとる方法についても指定があり、直接本人から同意を得ていない包括方式やオプトアウト方式を用いることは禁じられています。「従業員が自分の結果を見たうえで、同意するか決めることができる」方法以外では、本人の意思に反した通知や提供はされません。
企業にデータが提供される際も、同じ部署・グループなど「集団」として個人の結果がわからないような分析方法を用いて提供されます。
安心して受検できるよう、どのような分析方法で結果を出しているのか、誰が、どんな情報を取り扱うのかわかりやすく説明するパンフレットなどを作ってみてもいいでしょう。
同意の取得方法については、具体的に使用する予定の同意書を提示するなど、特に丁寧な説明が求められます。
ポイント3:労働者が不利益な取り扱いを受けることがないことを再確認する
ポイント1でも説明した通り、従業員がストレスチェックを受検しない大きな理由は「ストレスチェックの回答によって不利な扱いを受けるかも」という不安です。
厚労省の公開している「ストレスチェック指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)」や、労働安全衛生法では労働者が不利益な取り扱いを受けることがないように事業者が行ってはならないことを文章で明確に定めています。
具体的には以下の5つです。
- ストレスチェックを受けないことを理由に不利益な取り扱いを行うこと
- ストレスチェックの結果について、事業者への通知に同意しないことをもって不利益な取り扱いを行うこと
- 医師による面接指導の申し出を行うことにより不利益な取り扱いを行うこと
- 面接指導の申し出を行わないことにより不利益な取り扱いを行うこと
- 面接指導の結果によって、解雇・雇い止め・退職勧告・不当な配置転換を行うこと
長時間労働の医師面接と違って、ストレスチェック後の高ストレス者に向けた医師の面接指導は本人の申し出がある場合にのみ実施されます。また、面接指導の結果として行われる就業上の措置についても、なるべく速やかに実施するよう取り組みましょう。
この「就業上の措置」があったことを理由にする不利益な取り扱いについても「行ってはならない」として保証されています。
これらの点を改めて確認することができれば、従業員は安心して受検することができるでしょう。
そのために一番有効な周知方法は「前例を作ること」です。
しっかり説明をすることも重要ではありますが、どうしても従業員には「会社の言葉」として受け取られがちです。「ストレスチェック後の医師による面接指導や意見書の措置がきちんと行われた」、「面接や業務上の配慮を受けても評価が落ちなかった」という実績、一緒に働いている身近な人からの言葉が一番重みをもって響きます。
今まで積み重ねたストレスチェック実施経験や、適切な配慮が活きるポイントです。
従業員の多くは、自分が不利な評価をされる可能性があることに非常に敏感です。少しでもそのような可能性があれば、ストレスチェックを受検しないという選択をするでしょう。
したがって、ストレスチェック制度の目的や労働者に対する配慮、結果の取扱いについてしっかり説明し、理解を促すことによって受検率の向上が期待できます。
多くの従業員にストレスチェックを受検してもらい、集団分析を実施して職場環境改善活動を行い、生産性の向上につなげましょう。
| 初出:2017年10月22日 / 編集:2023年04月17日 |