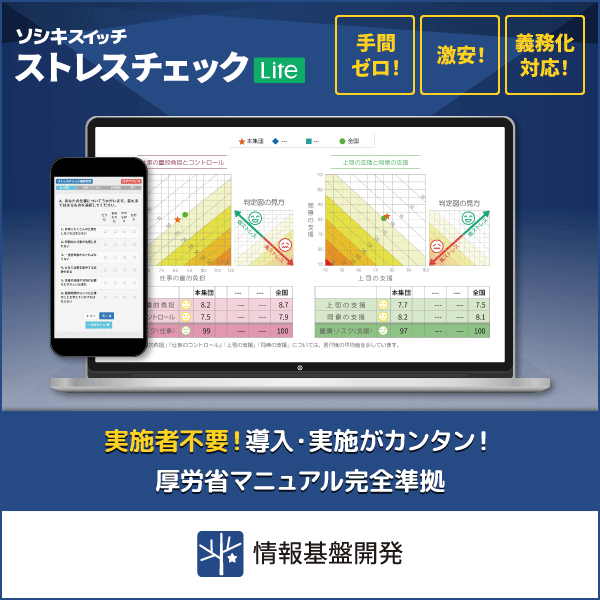ストレスチェックは実施した後もしなければならないことがあります。
特に「労働基準監督署への報告」は、会社の義務にもなるので書き方や記載内容が本当に合っているのか気になりますよね。
今回はこの記事で、ストレスチェックの報告書の書き方や産業医の署名捺印がいるかどうか、提出先はどこか、さらに外部委託した際はどうすればいいかなどについて解説します。
まずはしっかりとした報告書を作成し、不備がないようにしましょう。
ストレスチェックとは?
ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、企業はその検査結果をもとに職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを主な目的とした「心の健康診断」です。
「常時使用する労働者が50人以上の事業場」では、年に1回ストレスチェックを実施することが義務となっています。(労働者数50人未満は努力義務)
「仕事について」「心身の状態について」「周囲との関係について」の3つをテーマにした質問に答えることで、全国の労働者のストレス状態と比較して自分がどれくらいストレスを感じているのかを知ることができます。検査の結果、「高ストレス」と判定された従業員から申し出があった場合は、産業医など医師による面接指導を実施すること、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き必要に応じて就業上の措置を講じることも事業者の義務です。
報告書テンプレートは厚労省でゲット
ストレスチェックの報告書は様式が決まっています。労基署の方で機械による読み取りを行うので、専用のテンプレートで作成しましょう。
ストレスチェック報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。このテンプレートは 厚生労働省のHP に掲載されています。
お手持ちのパソコンにダウンロード・保存してから使用します。
また機械で読み取りを行うために、印刷に使用する用紙は白色度80%以上の用紙を使い、コピーしたものを提出・使用しないようにして下さい。
これらの注意はダウンロード画面に移動する前に、注意事項として表示されます。よく読んでご利用ください。
報告先は事業所「担当の労基署」へ
提出先は所轄の労働基準監督署になります。
労働基準監督署は各都道府県にいくつか設置されていますので、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署を確認の上、ストレスチェック報告書を提出しましょう。
事業所ごとにストレスチェックを行った場合、行った事業所それぞれを管轄する労基署への報告が必要になります。
本社でまとめて提出をしたい場合、「本社で、全社分のストレスチェックを一括で行う」こととなります。
また、ストレスチェックの実施が義務付けられているのは50人以上の事業場です。50人未満の事業場は努力義務にとどまり、報告の義務も今のところありませんが、厚生労働省は実施を推奨しています。
ストレスチェックの結果報告書は、e-Govからの電子申請も可能です。e-Gov電子申請はデジタル庁が運営する、行政手続をインターネット上で申請・届出することができるサービスです。ストレスチェックの結果報告書の他にも、産業保健関係の書類申請ができるので、テレワークなどでも直接労基署に出向かずに申請することができるので便利です。
なお、 e-Gov電子申請の利用にあたっては、「e-Govアカウントの登録をするか、GビズID、または他認証サービス(Microsoft )のアカウントのいずれか」の準備をしたうえで、アプリケーションのインストールが必要ですので、あらかじめ確認しておきましょう。
報告書はなるべく「事実を」「速やかに」
ストレスチェックの報告書様式には、あらかじめ記入欄が設けられています。
実施内容を欄に沿って記入すれば報告書は完成です。
主に書く内容は以下の通りです。
- 労働保険番号
- 対象年
- 事業の種類や名称
- 検査を実施したもの
- 在籍の労働数
- 検査を受けた人数
- 面接指導を受けた人数
- 集団ごとの分析の実施の有無
- 産業医の氏名
スムーズな記入のために、保険番号や事業内容など企業の基本情報は実施前に確認しておきましょう。また記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままでもかまいません。実際の状況に即して記入するようにしましょう。
特に、以下のポイントについては記入間違いがないよう気を付けましょう。
★「検査を実施した者」の欄は、検査を実施した「実施者」について該当する番号を記入します。
ストレスチェックは事業場選任の産業医、もしくは所属する医師等が行う以外に、外部に委託することも可能です。その場合も、実施者の所属状況についてそれぞれ1~3の番号が割り振られていますので、該当する番号を記入しましょう。
★「検査を受けた労働者数」の欄は、報告対象期間内に検査を受けた労働者の実人数を記入します。
ストレスチェックの実施前後に採用・退職があった場合も、社員数ではなく「実際に受検した人数」を記入すると覚えておけば大丈夫です。
注意しなければならないのは一年度内で複数回ストレスチェックを実施している場合ですが、その時も「報告を行う実施に参加した受検者」を記入しましょう。
何度ストレスチェックを受検しても、参加をしたならば「1名」としてカウントされます。
★「産業医の氏名」の欄及び「事業者職氏名」の欄は、企業と契約した産業医の氏名を明記することが必要です。担当者の代筆・印刷でも可能ですが、産業医の選任が求められます。
別途後述しますが、企業の義務となるストレスチェックには「事業所と契約している」産業医は必ず必要です。
必ず自社と契約をしている産業医にデータと報告書を確認してもらいましょう。
「産業医」は産業医の資格があれば
だれでもOK?
ストレスチェック報告書には、産業医の記名が必要です。
実施についてなら、ストレスチェックの実施者や実施後の医師面接は外部企業や契約をしていない医師に委託を行うことも可能です。ですが、外部委託を行った場合でも、50人以上のストレスチェックが義務になる企業であればストレスチェック報告書の産業医欄には「自社と契約した産業医」の氏名の明記が必須となります。
契約をしていない産業医や、外部機関を実施者として実施し報告書を作成した場合についても同様です。
産業医記名欄が空白のままで提出しても、基本的に受理されません。
ストレスチェックを実施し、報告書を作成する際は、前もって自社の産業医に相談しておきましょう。
報告は「なるべく速やかに」提出を!
ストレスチェックを実施したけれど報告が遅れてしまうことは考えられますよね。あまりに長く報告が遅れた場合、ストレスチェックを実施したにも関わらず報告を行わなかった場合として認識される可能性があります。
報告を怠った場合、労働安全衛生法(第120条)により50万円以下の罰則金の支払い義務が定められています。その他にもペナルティがある場合も考えられますので、実施した場合は、速やかに報告書の提出を行いましょう。
ですが、ストレスチェックを実施しなかった場合に課せられるペナルティなどは現在明確に定められていません。
実施が遅れてしまった、実施する余裕がなかった場合に労基署からの連絡や注意が届いた! というケースも見られましたが、今のところ、ストレスチェックを実施しないこと自体についての罰則はないようです。
しかし、そもそも事業場には「安全配慮義務」が定められています。
ストレスチェックも「安全配慮義務」の一環と考える裁判所・労基署がほとんどですので、ストレスチェックを実施しないことは実質的な「労働契約法違反」になるリスクもあるでしょう。もし労災などが起こった場合、企業側に不利な証拠として提出される可能性があります。
産業医が見つからない……など、何らかの事情があってストレスチェックの実施や報告が遅れる場合、事前に労基署へ相談し対応や措置を相談しましょう。
「外部委託」のできること、できないこと
大半の企業のストレスチェックは、人事部や総務部が中心となって実施していることでしょう。ですが「全社一斉に行うこと」「個人情報保護のため限られた人しか事務に関われないこと」から、どうしても業務負担が大きくなります。
もとより通常の人事業務にプラスして行うことになりますから、慣れていない担当者にとっては大変な作業です。またどうしても社内に担当者を置くことで、従業員が「結果を見られるのではないか」といった不安を感じることもあります。
そのため最近ではストレスチェックを外部委託して、人事の負担を減らし業務の効率化を図ることが一般的になってきました。
外部委託をしても、ストレスチェックの基本的な流れ(ストレスチェックを行い、点数の高い人(高ストレス者)をフォロー、改善する)は同じですが、外部委託業者ごとに提供しているサービスではできること・できないことがあります。
外部委託を検討する際は、「必ず自社でやるべきことは何か」を把握し、委託したいことと必要な機能・コストを比較して自社にあった委託先を探しましょう。
———————-
- 自社でやらねばならない事務
・自社のストレスチェック担当窓口の選任
・産業医との契約、選任
・社内規程の整備や従業員への告知、周知
・面接指導を行った医師からの意見聴取、意見書の確認
・ストレスチェック実施報告書の労働基準監督署への提出
- 外部に委託できるストレスチェックの事務
・実施者の代行
・集団分析などデータの作成
・ストレスチェック結果の労働者への通知
・ストレスチェックに対する相談用窓口の設置
・高ストレス者への対応/医師による面接指導・意見書の提出
・ストレスチェック結果の保存
———————-
★外部委託しても職場環境改善は自社の業務
ストレスチェックを外部委託するとしても、大切なことはその後のフォローと社内環境の改善です。
ストレスチェックをして終了ではなく、高ストレス者が出たのであればどうやってフォローするか、ストレスの多い職場の環境を改善するための施策は何かについては自社で考え、継続的に実施していかなければなりません。
けれど社内環境のどこがよくないのか、医療的な視点からみて問題はあるのか、従業員への配慮はどうすればいいのかには、専門的な知識が必要となります。
高ストレス者への配慮や職場の環境改善を考えるとき、法律を把握している「労基署」と自社の環境をよく知っている「選任産業医」が心強い味方となってくれます。
医療のスペシャリストの視点・利益の絡まない第三者の立場で意見をもらうことは、自社の環境を一番客観的に把握することができる機会です。
また労基署や中災防といった団体では、安全管理や健康についての知識を深める講習や安全環境改善策の相談など職場の安全を推進する活動を行っています。
ストレスチェックは産業医と企業と労基署が協力し、自社の環境や従業員の健康について話し合う良い機会なのです。
報告書を作成・提出する際に、一言相談してみませんか。
ストレスチェックの報告までが企業の義務、実施後のフォロー・面談とセットで忘れないように備えておきましょう。
〔参考文献・関連リンク〕
| 初出:2019年10月09日 / 編集:2025年07月15日 |