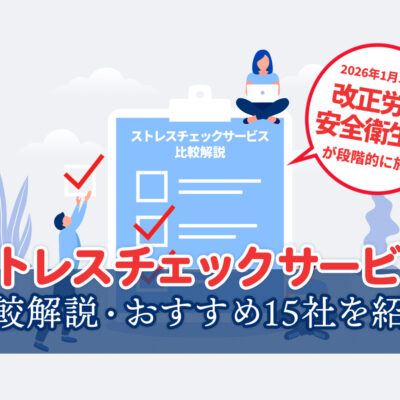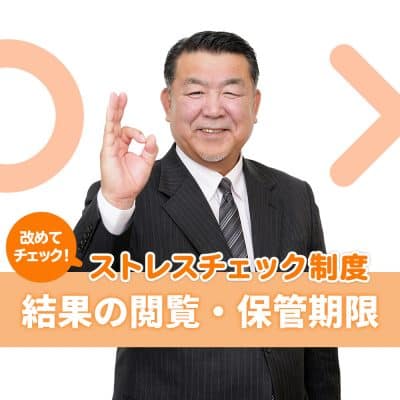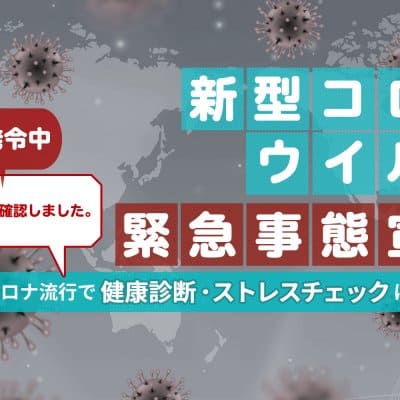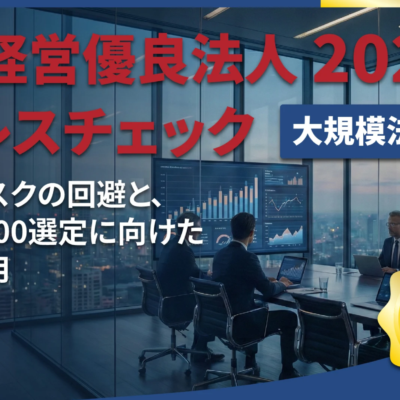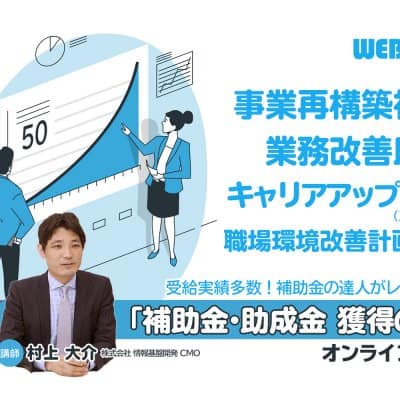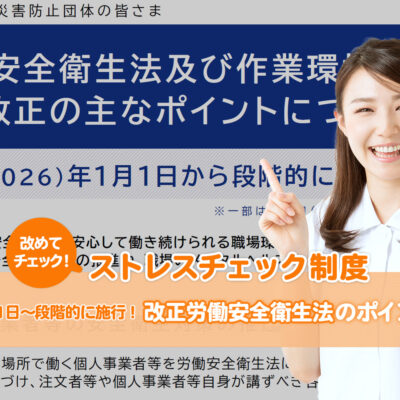ストレスチェック制度が開始されてから3年が経過しましたが、健康診断などの身体的な健康状態と比べて、メンタルヘルスに関する状態を他人に知られてしまうことに抵抗を感じる人は多いのではないでしょうか。
ストレスチェックの結果の取り扱い
ストレスチェック制度においては、労働者が不利益を被ることがないように、個人情報の取り扱いについて慎重な配慮がなされています。このうち、ストレスチェックの結果の事業者への通知に関しては最も慎重に対処する必要があります。
ストレスチェックの実施責任は事業者にありますが、ストレスチェックの結果等、個人情報を取り扱う実務を担当することはできないと定められており、事業者は実施者や実施事務従事者になることはできません。
これは、労働者が自分の結果が事業者の目に触れることにより不利益な取り扱いがなされるのではないかと心配したり、また実際に事業者がストレスチェックの結果に基づいて労働者に対して不利益な取扱いを行うことを防ぐためです。
情報開示の同意を得る際の注意点
労働者が働いている職場環境を理解し、就業上の措置や職場環境の改善を行うために事業者がストレスチェックの結果を参照することは有用です。また、場合によっては労働者の受検結果が事業者に通知されることがあります。ストレスチェック制度においては労働者の個人情報について慎重な配慮がなされていますが、労働者から情報開示の同意が得られた場合は、結果が事業者に提供されることになっています。
ストレスチェックの結果の情報開示に関する同意の取得方法は、本制度の趣旨を考慮して詳細に定められています。
具体的には以下のような留意事項があり、後になって実は同意がなかったなどのトラブルが生じないように、客観的に確認できる方法によることとされています。
(1)同意の取得については、労働者への結果の通知後に実施者より行うことが望ましい
(2)個人別に書面または電磁的方法により行い、結果は5年間保存する
また、ストレスチェックで予想外の結果が出ることにより、事業者への情報開示の意思が変わる可能性があります。したがって、同意を得るのは労働者へストレスチェックの結果の通知を行った後でなければばらないとされており、ストレスチェックに関する事前の案内時やストレスチェックの実施時に同意の有無を確認することは禁止されています。
ストレスチェックに関する同意書について、法で定められた具体的なフォーマットはありませんが、労働者の意思が明確に確認できる方法で同意を得ることが望ましいでしょう。
また、同意するか否かによって不利益な取り扱いをしてはならないことが法令などで定められていますが、労働者がわかりやすいように同意書でも説明で文を入れた方がよいでしょう。具体的には、下記のような様式で同意の有無を確認するとよいでしょう。
ー同意書の例ー
ストレスチェックを受検した方へ
先日実施したストレスチェックの結果はいかがでしたか?
自分のストレス状態については、自分では気がつかない部分も多くあると思います。今回の結果を参考にして、セルフケアに役立ててください。
会社としても、皆さまの結果について個人を特定できない方法によって集団分析を行い、職場環境の改善に役立てるようにしていきます。
さて、今回お知らせしたストレスチェックの受検結果を会社へ通知することについて、「同意する」または「同意しない」のいずれかの項目にチェックしてください。
どちらにもチェックがない場合には、同意しなかったものとして取り扱わせていただきます。
会社へのストレスチェック結果の通知について
▢ 同意する
▢ 同意しない
※ストレスチェック結果の通知に関する留意事項
下記の通り取り扱われますので、安心してご回答ください。
・会社にストレチェックの結果を通知することについて同意したとしても、同意しなかったとしても、回答については人事評価に用いられることはなく、同意の有無により不利益な取り扱いがなされることはありません。
・同意を得て開示されたストレスチェックの受検結果の利用目的は、必要がある場合にこれを参考にして就業上の措置を講じることで、それ以外に利用することはありません。また、ストレスチェックの結果をあなたの直接の上司や同じ部署の同僚に伝えることはありません。
・通知について同意があった場合には、同意の意思の確認書面(この書類)とともに、取扱いには十分に配慮して情報を5年間保存します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
この書面においては、同意するか否かを明確に確認する必要があるので、本人の意思に反して間違えて同意してしまうことがないよう、文例のようにわかりやすい形で記載するようにしましょう。
また、厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルでは、包括同意やオプトアウト方式により同意を得ることは禁止されています。各労働者の意思が確実に確認できる方法で同意を得るようにしましょう。
包括同意とは、例えば衛生委員会等で労働者側代表の同意を得ることで、労働者全員の同意を得たとみなす方法です。
包括同意方式では、集団の意見に流されて積極的に自分の意見を申し出ることの苦手な労働者については意思に反して同意したことになってしまう可能性があります。また、少数意見が黙殺されてしまう可能性もあります。
オプトアウト方式とは、全員に対して期日までに不同意の意思表示をしない限り、同意したものとみなす旨を通知し、意思表示のない者は同意したとみなす方法です。
オプトアウト方式では、説明書をよく読まかった場合や、不同意の意思表示を行うことを失念してしまった場合などには意思に反して同意が得られたとされてしまう場合があります。
労働者によっては、不利益な取り扱いがなされることをおそれて同意することに抵抗を感じてしまう場合も少なくありません。
この点については、制度導入時の説明会や各種案内文などで説明されているはずですが、同意の有無に関する回答をする際に労働者が最も気になる点の1つですので、同意書の例にもある通り、末尾に改めて注意事項として記載するとよいでしょう。
結果の通知方法
ストレスチェックの結果は実施事務従事者が通知することが多いと思われますが、実施事務従事者は守秘義務を負っているので、本人の同意を得ることなく企業に結果を通知することはできません。
また、結果的に高ストレス者であることを推察されるような通知の方法は避けるような配慮が必要です。例えば、高ストレス者以外にはメールで結果を通知し、高ストレス者には社内で封書を配布して通知するような方法では、簡単に高ストレス者が推察されてしまいます。しかし、このような方法による通知は禁止されています。
面接指導の申し出とみなし同意
ストレスチェックを実施し、高ストレス者の中から面接指導の対象者が選定されると、次に実施者から対象者へ面接勧奨の案内があり、面接指導の申し出があれば、実際に面接指導を行うことになります。
この場合、労働者が面接指導の申し出をしたことで、ストレスチェックの結果を事業者に開示することについて同意したとみなされます。
ストレスチェック結果の通知については積極的な同意の意思を確認する必要がありましたが、面接指導の対象者については申し出をしたことによって同意したとみなされるのです。
この場合のみなし規定については運営の簡便化を目的としており、労働者の意思に反して情報が開示されることは制度の趣旨に反します。
規定上、そのような取り扱いができることにはなっていますが、トラブル防止のため、また労使が協力して円滑に制度を運営するために、面接指導の申し出書についても結果の通知に関する同意書と同様に改めて本人の意思を確認する方がよいかもしれません。
面接指導を受ける意思があるのにも関わらず、結果の通知について同意しない場合は、ストレスチェック制度について理解が不十分であることが考えられるので、個別に説明するなどして、しっかりと理解してもらったうえで面接指導を実施するようにしましょう。
上記のように、ストレスチェック制度を円滑に運営するためには、時には制度で求められる範囲を越えて対処することも検討する必要があります。ストレスチェックで得られた個人情報は慎重に取り扱うように配慮し、従業員と事業者側の両者とって有用な制度となるようにしましょう。
| 初出:2017年10月20日 / 編集:2018年09月28日 |