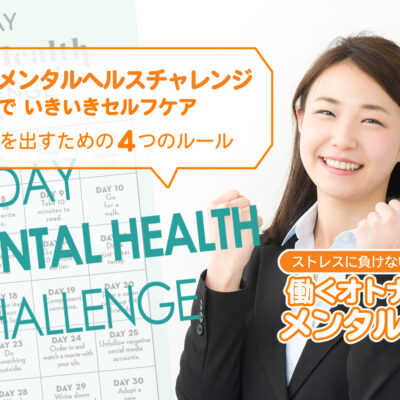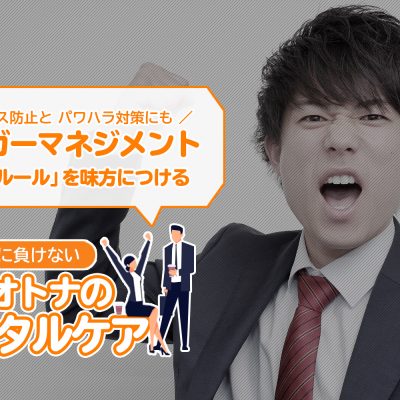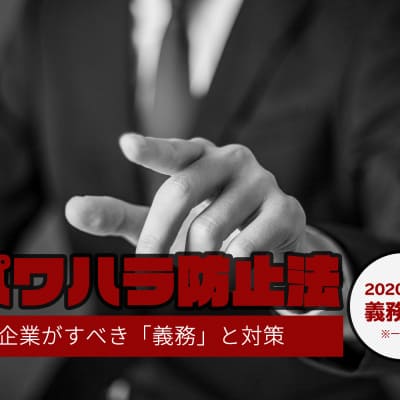季節の変わり目や、職場や学校、ライフスタイルなど環境が変化する時期は、メンタル不調に悩む人が増える時期ともいわれています。
メンタルヘルスの問題を考える時、多くはその「不安」や「気分の落ち込み」などに目が向けられがちですが、実はわくわく感やドキドキ感も含めて、環境の変化は少なからず私たちの心身に影響を与えています。
「転職や異動などで新しい生活がスタートし、新しい人間関係の中で上手くやっていこうと頑張りすぎて体調を崩してしまう……」だけでなく、「昇進や結婚など、周りからは順調に見えるのになぜあの人が……」といったケースもよく耳にします。
もしかしたら、その方は「適応障害」だったのかもしれません。
(※ほかの病気が隠れている場合もあります)
適応障害という言葉は聞いたことはあるけれど、どういった症状が出るのか、何が原因となるのかについては、あまりよく知らないという方もいるのではないでしょうか。適応障害はストレスと深い関わりがあるため、誰にでもかかる可能性があるのです。
今回は、新生活に向けた期待と不安が入り混じる時期にこそ少し心に留めておいてほしい、「適応障害」のお話です。
いつでも、誰にでも起こるメンタル不調「適応障害」とは?

近年は特に、女優さんの活動休止や、スポーツ選手の試合・大会棄権、海外アーティストのカミングアウトなど、著名人やアスリートのニュースを通して「適応障害?うつ病とは違うの?」と話題になる機会も多かったことから、記憶に残っている方もいるかもしれません。
適応障害は、進学や就職、異動や昇進、結婚など……身の周りに起こる変化に上手く適応できず、うつ状態や不安、頭痛・めまい、不眠や胃腸などに症状が現れ、生活や仕事に支障が出てしまう状態です。飲酒量が増えたりギャンブル依存といった形で出てくることもあります。
児童や思春期の子どもの場合は、学校を休みがちになったり、喧嘩が多くなったり攻撃的になったり、問題行動によって現れてくることも多く、大人の場合は不安など、より感情面に症状として現れる傾向にあるという報告もあるようです。
うつ病とも似ていますが、はっきりと特定できる環境要因が引き金となって起こるのが特徴で、ストレスが始まってから3か月以内に症状が出現します。この「特定の環境」が原因となる点がポイントです。
私たちは皆、自分の性格や気質とのバランスを取るために、ときには落ち込んだりイライラしたりしながら、ストレスとなる出来事や環境と折り合いをつけながら「適応」していく力を持っています。それでも負担に感じる出来事や度合い、エネルギーの限界は人それぞれ異なります。自分の中の許容量を超えてしまったり、緊張状態が長く続いたりすれば、バランスを崩してしまうのは当然のこと。
適応障害は、適応力が高い低いということでは決してありません。
原因となるストレスがないところでは元気でいられる場合もあるため、「打たれ弱い、我慢が足りない」など誤解されがちな面があり、適切なケアをしないまま深刻なうつ病に発展してしまうことが実はとても怖いのです。
通常は、強いストレスとなっている原因が解消されれば、6ヶ月以内に症状が改善するとされていますが、ストレス因子が持続する場合は解消は難しく、長引いてしまうため注意が必要です。
季節の変わり目は、自律神経の乱れに注意
冒頭でも少し触れたように、メンタル不調と聞くと「不安」や「気分の落ち込み」などネガティブな感情に目が向けられがちですが、わくわく感やよい意味での緊張感やプレッシャー、期待も含め、環境の変化は少なからず心身に影響を与えています。加えて、寒暖差や気象・気圧の関係、花粉症、ホルモンバランスなど……さまざまな原因で自律神経が乱れると、メンタルヘルスの問題にもつながってくる場合があります。
こういった点からもわかるように、人間の力では防ぐのが難しい自然環境の変化や、特にコロナ禍で長引くストレスの多い状況下で、私たちの心身には知らず知らずのうちに負担がかかっていることもあり、適応障害をはじめとしたメンタル不調は、より身近に、誰にでも起こる可能性があるのです。
では、適応障害の予防や、少しでも不調を感じ日常生活に支障が出てきてしまった場合には、どうしたらよいのでしょうか。

ストレス要因を取り除く、3つのセルフケア対策
回復の近道は、「ストレスの原因を取り除くこと」です。
そのストレスを生む要因から距離を取ったり、環境を調整をしたりすることが可能なのであれば、それがもっとも効果的といえるでしょう。
ただ、そうはいっても環境の変化は年中無休。多かれ少なかれ、私たちの生活から切り離すことはできないものですよね。ましてや、職場や家庭などに関係する特定のストレス要因であればなおさら……そう簡単に除去することは難しいのが現実。多少のストレスと向き合いながら仕事や生活を続けなければならないこともあるでしょう。
そこで、できる対策は大きく分けて3つあります。
①環境を改善・調整すること
まずは原因となっているストレスを軽減することです。
普段より多く休みを取ったり負担を減らしたり、適応しやすい環境やペースを整え、エネルギーを回復する必要があります。可能であれば、休業や配置転換など環境調整は回復に大きな効果があります。
②睡眠と規則正しい生活を心がけること
睡眠とメンタル不調はとても密接な関係にあります。
質の良い睡眠をとって、脳を休めてあげること。日中は太陽の光をしっかり浴びて、栄養バランスの取れた食事を摂ることが大切です。
③相談できる人・場所をつくること
また、「これくらいの不調なら休まずとも大丈夫だろう」などと一人で判断せず、無理をする前に誰かに相談することも大切です。
調子が悪くて会社を休みがちになるなど、すでに日常生活に支障が現れている場合には、医師など専門家の力を借りて症状を和らげることが必要な場合もあります。心身の反応が自分にとってのストレスや許容範囲を教えてくれているともいえるので、ストレスに気づき、「無理をしない」「しっかり休む」など、これをきっかけに自分の視点や意識を少し変えてみる、自分なりの対処法(コーピング)を身に着けることもいいかもしれません。
「自分は大丈夫」「まさかメンタル不調にはならないだろう」などとつい過信してしまいがちですが、環境の変化や人間関係とは切り離せないのが、私たちの日常です。だからこそ、
・いつでも、誰にでも起こりうるものであること
・適応障害は、早期のうちに環境調整を行い、適切に対処・治療することで、早めに回復することが可能なこと
自分や周りの人を守るためにも、心に留めておいていただけたらと思います。
環境の変化が多い時期。
こんなときだからこそ、たまには立ち止まってみる。
知らず知らずのうちに頑張りすぎて体調を崩してしまう前に、少しゆっくり構えてみるのもいいかもしれません。自分のペースで自分と向き合ってみませんか?
〔参考文献・関連リンク〕
| 初出:2024年03月19日 |