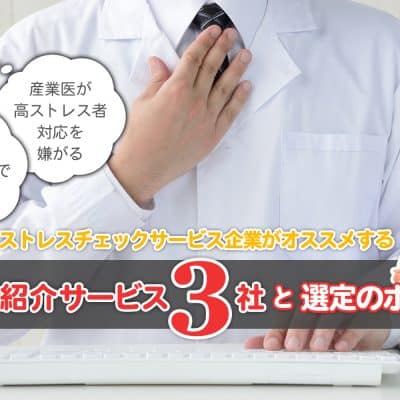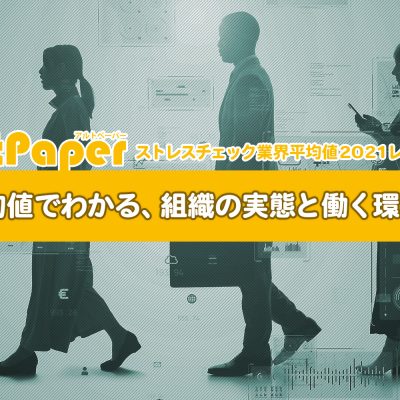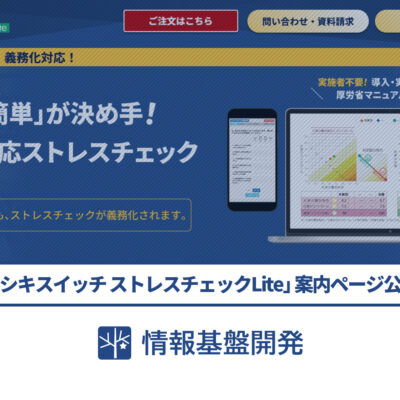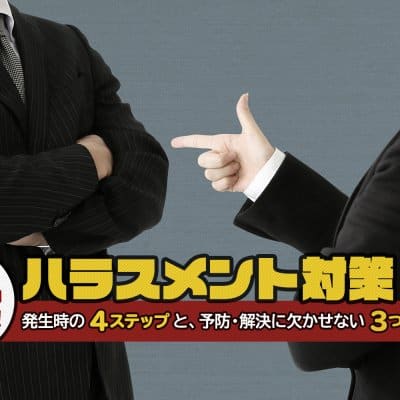熱中症や交通事故といったニュースが連日報道されています。
屋外作業のみならず、事務や室内での業務でも「労働災害」は発生します。
「労災保険ってどんな時に適用されるの?」
「労災保険の申請手続きの方法が不安……」
もしも、を考える際必要になるのが労災保険の給付についての知識です。
労災保険には3つの種類があり、それぞれ認定要件が異なります。
労働者を雇用する事業所はもちろん、労働者も万が一のために労災保険について理解しておくことが大切です。
そこで今回は労災保険の種類から申請方法、申請時に必要な書類、そして労災保険の注意点まで解説していきます。
労災保険とは?
労災保険とは、業務や通勤が原因で怪我・病気になった場合に、被災した労働者に対して保険が給付される制度のことです。
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員など非正規雇用者も対象で、直接雇用されているすべての労働者が適用されます。
3種類の労災保険
労災保険には以下3つの種類があり、それぞれ認定要件が異なります。
- 業務災害
- 通勤災害
- 第三者行為災害
業務災害は仕事中に被災したときに適用される労災保険で、仕事中に怪我したときの「業務遂行性」と、仕事が原因で怪我・病気したときの「業務起因性」の2面性があります。
通勤災害は通勤時に適用される労災保険で、たとえば日用品の購入など最小限の範囲の寄り道であれば認められます。
しかし、たとえば会社帰りの美容院や飲み会など、私的行為の被災時は労災保険として認められないので注意が必要です。
第三者行為災害は業務遂行中・通勤時以外で、第三者によって生じた災害の際、加害者となった第三者に対して損害賠償責任が発生したときに認められる労災保険です。
労災保険の申請は会社が行ってくれる
本来、労災保険の申請は怪我・病気をした本人もしくは家族が行います。
ですが被災してしまった本人の負担を軽減するために、企業や事業主が代理で手続きすることが一般的です。
もし仕事中や通勤時などに怪我・病気にあったら、まずは会社の保険業務担当者に相談してみましょう。
中には「会社に迷惑をかけたくないから申請したくないな」なんて思う人も多いはずです。
しかし、企業は従業員を守る立場にあり、労災保険を申請しなければ労災隠しとして会社側の責任が疑われてしまいます。
そのため、「労災かな?」と少しでも感じたら、遠慮せずに必ず会社へ相談しましょう。
もし労災保険を担当する担当が社内で定まっていない場合は、本人で申請手続きを行わなければいけません。
労働者としても労災や保証制度は欠かせない 知識です。
そこで、個人・法人ともに労災保険の申請手続きの流れを紹介していきます。
労災保険の申請から給付までの流れ
労災保険の申請から給付までの流れは以下のとおりです。
- 労災が発生
- 労災指定医療機関で受診
- 請求書類の作成・提出
- 労基署が書類を受託
- 労基署の審査
- 給付
労災保険を利用する場合は、基本的に労災指定医療機関で受診するよう注意をします。
事業所の労災保険を担当する人は、万が一労災が発生したときのために、近隣の労災指定医療機関をリストアップしておくことをオススメします。
仮に労災病院もしくは労災指定医療機関ではない一般の病院で受診した場合、被災者本人が受診料を一時的に建て替えなければいけないので注意が必要です。
後日労災保険の申請を行うことで、立て替えた分の医療費は還元されますが、怪我の重さによっては高額の医療費を負担しなければいけません。事務的な手続きも発生しますので、被災者本人や従業員の負担を軽減するためにも事業所は労災指定の病院を把握しておきましょう。
なお、厚生労働省公式ページにて労災保険の指定医療機関を検索することが可能です。
また、医療機関へ届出する内容が実際の診療科目等と異なることがあるので、具体的な医療機関の情報については各医療機関まで問い合わせましょう。
必要書類
労災保険を適用するには、 「給付請求書」に 事業所と医療機関がそれぞれ必要事項を記入する必要があります。
労災保険の申請時に必要な書類は
・申請する給付の種類 / ・発生した労災の種類
によって分けられ、 厚生労働省のホームページもしくは各都道府県の労働基準監督署から入手できます。
提出後、機械で読み込みを行うため、提出や郵送を行う際に折り曲げや糊付けされないよう取り扱ってください。
注意したいのが、用意した書類の提出先です。労災指定医療機関での受診とそれ以外の医療機関で受診したのでは書類の提出先・請求する署局が異なります。
また領収書や診断書といった添付書類についても必要となる様式や記載内容が異なりますので、病院側へ先に依頼しておくとスムーズに行うことができます。
手続きに必要な書類、提出先は厚労省発行の各給付パンフレットに詳細が掲載されています。
| 給付金の種類 | 提出先 |
| 療養給付(指定病院で受診した場合) | 治療を行なった病院 |
| 療養給付(指定病院以外で受診した場合) | 労基署 |
| 障害給付 | |
| 遺族給付 | |
| 休業給付 | |
| 葬祭料 | |
| 介護給付 | |
| 二次健康診断等給付 | 受診した病院 |
通院費は支給の対象?
労災で負った傷病の治療のために、何回か通院しなければならない場合
・被災者の自宅、または勤務先から片道2㎞以上ある
・治療に適した、最も通院しやすい」病院への通院
以上の2点が当てはまれば、通院にかかった費用も支給対象となります。
片道2㎞以内に医療機関がある場合でも、使用しなければならない交通手段や状況によっては支給の対象となるものがあります。
労働基準監督署へ相談してみましょう。
請求には時効があるので注意!
療養給付や遺族(補償)給付介護(補償)給付二次健康診断等給付などには申請期限・給付について時効が設けられています。
各給付ごとに設定された時効までの日数は異なりますが、どれも労災が発生したり、被災者の症状が安定し手続きが可能になり次第、すぐに手続きを行えば問題はありません。
なるべく速やかに手続きをすますためにも、日頃からどんな書類・どんな情報が必要になるのか把握を心がけましょう。
事業所が知っておくべき労災保険の3つの注意点
事業所が知っておくべき労災保険の注意点には以下の3つがあります。
- 病院の受診時は健康保険証を提示してはいけない
- 労災保険の未加入は罰則がある
- 労災で休業中の労働者は解雇できない
病院の受診時は健康保険証を提示してはいけない
労災の請求を行う際、一番耳にするトラブルは「労災保険を適用されるのに、健康保険証を提示(健康保険に請求)してしまった」です。
労災で病院を受診するときは健康保険証を提示してはいけません。
仮に従業員が何も知らずに健康保険証を提示してしまった場合、改めて労災保険に切り替えなければなりません。
早い時点で気が付けば、請求時に労働保険に切り替えることが可能ですが、健康保険先に請求をしてしまった場合、被災者が治療費を立て替えた上でその金額を労災に請求しなくてはいけません。
郵送での書類のやり取りなど複雑で時間の書かる手続きが必要になります。
そのため、従業員には被災したときに利用する病院や、健康保険証を使ってはいけないことをしっかりと説明しておきましょう。
また、健康保険証で受診してしまうと、事業所が従業員へ労災保険を使わせない「労災隠し」ではないかと疑われてしまいます。
「労災隠し」は企業が労災が発生した事実を隠匿し、労基署への報告を怠ったり、虚偽の報告を行う【犯罪】にあたります。厳しい処罰の対象となりえるため、従業員が誤って健康保険証で病院を受診したことが判明したら、速やかに病院へ連絡し労災保険への切り替えを行いましょう。
労災保険の未加入は罰則がある
一人でも従業員を雇う企業は労災保険へ加入する義務があり 、労働者を雇うときは事業を始めると同時に保険が労災保険が成立することになります。
労災保険に加入していない間に被災しても、手続き遅れや保険料未納という扱いで補償を受けることができるのです。
労災保険に未加入の事業所は 「以下のような罰則があるので注意が必要です。
- 未払いの保険料の徴収
- 労基署からの加入指導があったにも関わらず、故意的な未加入は
給付金の100%を取り立て - 労基署からの加入指導はないものの、未加入のまま
労働者を1年以上雇用した場合は給付金の40%を取り立て
また、故意的な未加入で被災者の申請を受け付けなかった場合も「労災隠し」として50万円以下の罰則、もしくは会社名の報道などが適用されます。
従業員を雇う事業所は労災保険に必ず加入しましょう。
労災で休業中の労働者は解雇できない
労災で休業中の労働者は解雇できません。
法律では、休業する被災者本人の精神的安定を保つために 「治療期間中および治療後30日間は解雇してはいけない」と 決められています。
しかしながら治療が3年以上続き、さらにその後治癒して職場に復帰できる見込みがない場合は、 平均賃金の1,200日分 となる補償料を支払っての解雇が認められます。
これらの補償料は「打切補償」と呼ばれ、事業所はそれ以上の補償責任を負うことはありません。
労災保険の手続きは本来被災者本人かその家族が行うものですが、被災者の負担を減らすために事業所で行うのが一般的です。
スムーズな受給のためにも、労災を受けるための手続きやポイントを労働者に対してもしっかり説明しておきましょう。
また労災保険の加入は事業所の義務です。
もしもの時、いざという時のために制度や手続きを把握し、手順を再確認しておきましょう。
| 初出:2019年8月20日 |