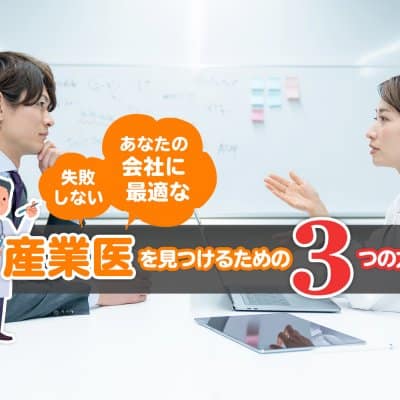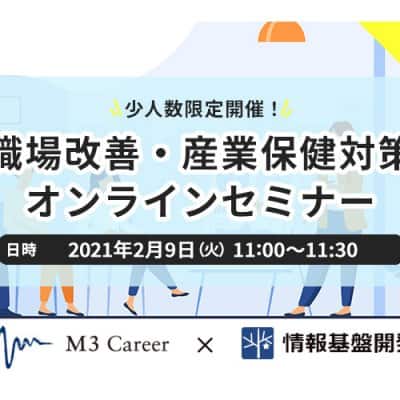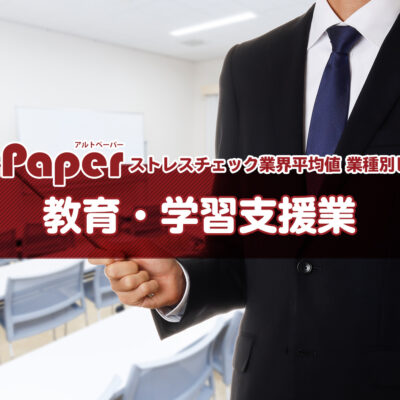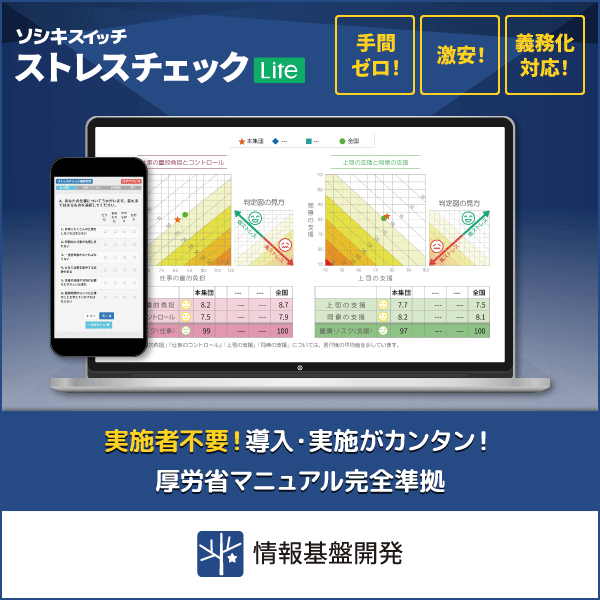ストレスチェックの実施時期
ストレスチェックはいつ実施すればよいのでしょうか?
労働安全衛生法では年に1回実施することとされていますが、時期についての指定はありません。健康診断と同じ時期にストレスチェックを実施する企業も多いと思われますが、ストレスチェックを実施する時期の設定にあたっては、以下の4つのポイントを考慮するとよいでしょう。
1. 繁忙期は避ける
繁忙期にストレスチェックを実施することは避けましょう。
仕事が忙しいとストレスが高まるのは当然です。ストレスチェックの目的は「高ストレスの人を見つけ出す」ことではなく、受検者本人が自分のストレス状態に気付き、改善のきっかけを見つけることです。
通常業務を通じてストレスをどの程度感じているのかを計れるよう、毎年決まった繁忙期がある企業では、その時期以外にストレスチェックを実施する方がよいでしょう。
2. 異動時期・決算時期(年度末)は避ける
異動して新しい環境に慣れるまでは誰しもストレスを感じるものなので、4月や10月などの異動時期は避けるようにしましょう。
また、年度末などの決算時期は間接部門では繁忙期にあたり、営業部門にとっては営業成績の締めの時期であるため、大きなプレッシャーがかかる時期です。こちらも繁忙期と同様にストレスが高まる時期ですので、ストレスチェックの実施は避けるようにしましょう。
3. 週半ばから配布、週半ばに提出期限を設ける
ストレスチェック受検者の大半は、チェックシートを受け取った日または提出締め切り日に回答します。したがって、チェックシートを週明けまたは週末に配布すると、週の中でもストレスが高まるタイミングに回答することになってしまいます。
また、週末を提出期限としてしまうと、その次の週明けに遅れて提出する受検者の対応等、管理上の負担が大きくなることが予想されるので、週半ばからチェックシートを配布し、週半ばに提出期限を設定するようにしましょう。
4. 午後に配布する
1日の中で最もストレスを感じやすいのは、午前中と残業時間帯といわれています。
また、昼食を食べたか否かも精神状態に影響を与えます。
午後にチェックシートを配布することで、潜在的なストレスを発見しやすくなります。
以上の4項目がストレスチェック実施時期の設定において考慮すべきポイントです。
ストレスチェックの目的の1つとして、従業員のパフォーマンスを高めて企業の生産性を高めるということがあります。
ストレスチェックをWebサイトで行う場合も、紙で行う場合も実施時期をよく考えて、ストレスチェックの効果を最大にするように心がけましょう。
| 初出:2016年10月6日 / 編集: 2023年04月13日 |