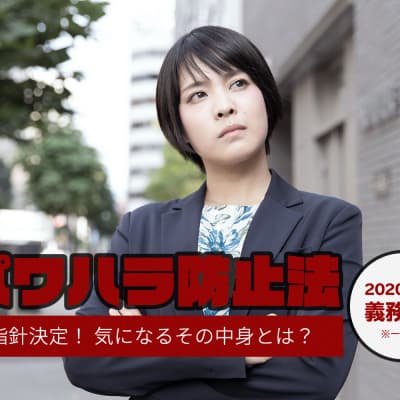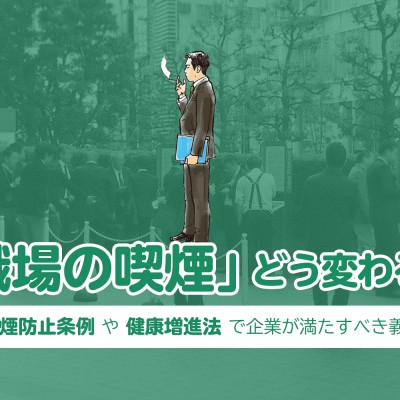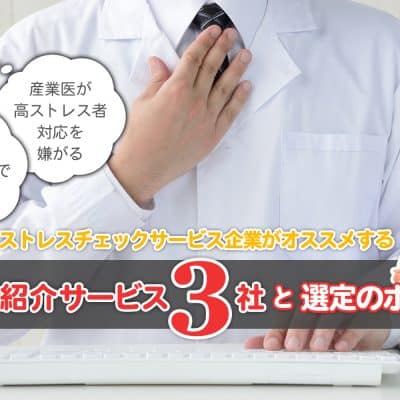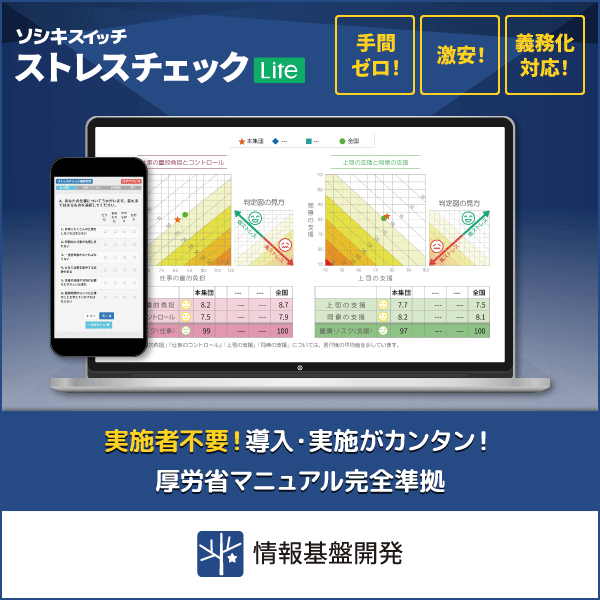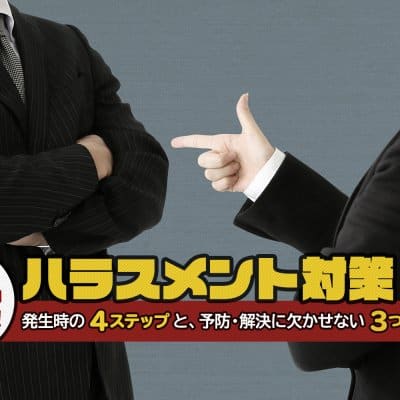企業には、従業員が安全で健康に働くための配慮をしなければならない「安全配慮義務」があります。それは「社内の危険」のみならず「社外からの危険」についても同じこと。
お客様からのハラスメント行為(カスタマーハラスメント)が原因で、従業員の安全や心身の健康にとって危険な状況があるならば、適切な対策を取らない場合には安全配慮義務違反となる場合もあります。
では、カスタマーハラスメントから従業員を守るために、具体的にはどのような対策をしておけばよいのでしょうか。
深刻化する問題へ対処するために、消費者庁が作成・活用を始めた「相談対応困難者(クレーマー)への標準相談対応マニュアル」や、厚生労働省が「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進」のために行った複数のヒアリング調査報告などをもとに、企業に必要な対策を考えていきましょう。
まずは、「カスタマーハラスメントの定義」を明確に
カスタマーハラスメント(「カスハラ」)とは「顧客・消費者からの度を超えた悪質なクレームや要求」を指しますが、この問題の難しいところは“悪質性の判断”の困難さです。明らかに刑法に触れるような行為もありますが、現行の法律上では明確な基準は設けられておらず、裁判などで違法と判断されるには至らないケースも数多くあります。
大きなトラブルに発展してしまう前に「まずはとにかく謝る」「仕方なく要求に応えてしまう」「責任者が出てきて謝る」など、その場しのぎの対応をとっていることも多いかもしれません。しかし、こうした対応はときに迷惑行為をエスカレートさせてしまったり、前例を作ってしまったりすることにもつながりかねません。他の多くの大切なお客様や従業員を守るためにも、企業内、できれば業界内で明確な基準を定め、その基準を超えるようなハラスメント行為には毅然とした態度で臨むことが求められます。

厚生労働省管轄下における現状の参考ガイドライン
カスタマーハラスメントが起こる背景には、同じ業界内でも「企業間で対応の差があること」も影響があると指摘されており、例えば、同業他社で対応・対処の方法に違いがあると「あそこの会社はやってくれたのに」とクレーム要求の基準を「一番対応してくれる会社」に合わせるよう強要する事例も報告されているようです。
そのため、業界団体や企業等が基準を共有すること、社会的事実としてルールや姿勢を示すことで、企業が対策検討や研修、マニュアルの整備等に取り組みやすくなる、と早期の対応が望まれています。
UAゼンセンが公表している「顧客からのハラスメントの定義とその対応に関するガイドライン第2版」(厚生労働省提供資料:「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」より)は、カスタマーハラスメントとなる顧客からの行為・要求を次のように類型化しています。
– 欠陥があった商品の代金より、高額な賠償を要求
– 謝罪として土下座を求める要求
– 従業員の解雇を求める要求
– 自社製品以外の要求
– 不当な返品を要求(返品期限を過ぎている返品など)
– 実現不可能な要求(法律を変える、子どもを泣き止ませるなど)
– 発生した事実に対して相応に対応したにもかかわらず、企業トップをだせという要求
– 暴力をふるう、身体を触るなどの行為
– 性的な発言をする、女性蔑視の発言をする行為
カスハラ対策は「明示」と「マニュアル」
企業に求められる悪質なクレームへの基本対応は 、「カスハラに過剰に対応しないこと」「何かあればすぐ上司に報告すること」などの【毅然とした態度をとることのできる体制づくり】です。
そのために最初にやるべきことは、「何がカスハラ(不当な要求)にあたるのか」、要求内容や態度が社会通念上、著しく不相当であるクレームや要求の基準を示すことです。
そして次に、いざその場面に直面した場合にどのように対応したらよいのか、対応・報告のフロー / マニュアルを作成しておくことが大切になってきます。実際にお客様と接し、対応する現場の従業員個々人のスキルに任せるのではなく、マニュアルによって共通の対応があることは、従業員自身の不安やストレスを減らすだけでなく、企業全体を守ることにもつながります。

企業に必要なカスハラ対策のポイントとは?
「顧客からのハラスメントの定義とその対応に関するガイドライン第2版」(UAゼンセン資料)では、企業がとるべき対応、および雇用管理上の措置(防止措置)のポイントについて以下の13項目を挙げています。
- ハラスメントの定義と判断基準の明確化について
- ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発について
- 相談窓口の設置
- 相談への適切な対応
- 事実確認
- 被害者への措置
- 行為者への措置
- 再発防止
- プライバシー保護
- 不利益取扱いの禁止
- 従業員への教育
- 企業トップのメッセージ
- 関係各所との連携
それぞれのポイントを詳しく見ていくとわかるのですが、上記の対策はパワハラやセクハラなどハラスメント全体に共通する部分が多く、「職場のハラスメント対策」としてカスタマーハラスメント対策も一体的に行うことが求められています。
ここで挙げられている従業員への教育の一環として、対応マニュアルの作成や研修を行うことがとても大切なポイントとなります。
また、企業のトップが企業として顧客からのハラスメントには毅然とした対応をとるという方針を明確に打ち出すことが重要です。これにより、従業員を悪質なクレームやカスハラの影響を受けるリスクから守り、対応の長期化を防ぐことにつながり、不安を軽減し「お客様と接する際の安心感を高めること」ができます。
行き過ぎた悪質なクレームに対しては、毅然とした態度と、場合によっては法的措置を取る旨の警告文を店内に掲示することも効果があるとしています。
また、特に店舗などの場合は、その地域や警察、保健所など関係各所とのコミュニケーションを日ごろから取ることにより、クレームが発生したときには適切な対応・相談ができるよう体制づくりを進めていくことも必要です。なかにはお店だけで対応するのが難しい悪質クレームや暴行・恐喝・強要といった法律に触れる迷惑行為・ハラスメントもあるため、大きなトラブルがあったときにすみやかに相談できる弁護士や専門家、通報先を決めておくというのもポイントとなります。

「カスハラ」に潰されないために…
ハラスメント対策と社内体制づくりを進めよう
カスハラ対策として、企業には次の対策が求められています。
- 悪質クレームなどに対する対応マニュアルの作成
- カスタマーハラスメントに関する研修・事例の共有
- ハラスメントに関する報告フロー・相談窓口の整備
「カスハラ」を受けてしまった従業員のフォローとして、ストレスを相談できるような窓口を整えておくことも有効です。ストレスだけでなく、ハラスメントが相談できる体制を作り、困ったときには相談窓口を利用することができるよう周知も徹底しましょう。
消費者庁の「相談対応困難者(クレーマー)への標準相談対応マニュアル」によると、悪質なクレームや迷惑行為、カスハラ行為に発展してしまう消費者(企業にとってはお客様)は、自らの要望が対応できない内容であったり、本人の予想とは異なる説明を相談員(店員など)からされたりすると、その不満の矛先・はけ口が相談員へ向かうことが多いといい、この段階になると当初の相談内容ではなく、消費生活センターや対応した相談員(企業自体や対応した従業員・スタッフ)に対する批判や罵倒する言葉の連呼となり、「対応困難者」となってしまうことが報告されています。
そうなってしまうと、当初の要求内容の解決よりも「要求を通すことができたことへの達成感、優越感、自己満足」を満たすことが目的となり、懸命に現実的な解決を目指した提案をしても、かえって対応困難者の怒りは増大することがあるといいます。
一方で、クレーム対応は適切な初期対応を行うことで事態が困難になる前に解決する場合や、管理者などに交代するだけで場が収まるケースも報告されています。
すぐに報告や相談ができる職場は、日頃の人間関係が大切です。信頼関係が構築できるよう日々のコミュニケーションを心掛ける管理者の対応や職場環境の整備も求められます。お客様を対応困難者や悪質クレーマーにしないためにも、そして従業員の安全と健康を守るためにも、カスタマーハラスメント対策が必要です。

「カスハラ」は企業にとっても従業員の時間をとられてしまい、場合によっては「せっかく育てた人材を失う可能性すらある」というマイナスの影響もあって、対応に悩まれている方も多いと思われます。
企業の利潤はお客様あってのこととはいえ、「企業と顧客 / 従業員とお客様」という立場はあれど「商品やサービスを間に挟んだ、対等な人間同士のやり取り」であることを忘れてはいけません。言いがかりに近い理不尽な要求や暴力、従業員の人格を否定するような暴言は、クレームではなく「ハラスメント」です。
リスクマネジメントのひとつとして、「組織全体の問題」として対応することが不可欠です。
企業の安全配慮義務違反とならないためにも、また、2022年4月~中小企業でも本格的な義務付けとなるハラスメント対策の一環としても、今回ご紹介したマニュアル等を参考に「カスタマーハラスメント対策」への取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。
〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省:顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議(UAゼンセン資料)
- 消費者庁:消費生活相談における相談対応困難者(いわゆるクレーマー)への対応マニュアル作成<事業実施報告書>
| 初出:2019年12月11日 / 編集:2021年12月14日 |