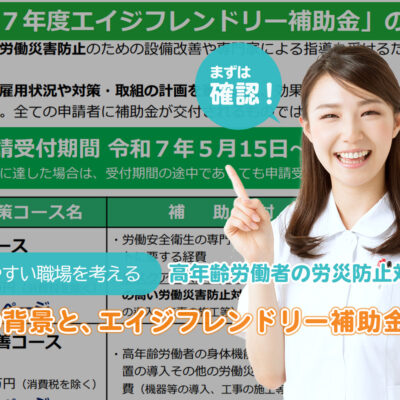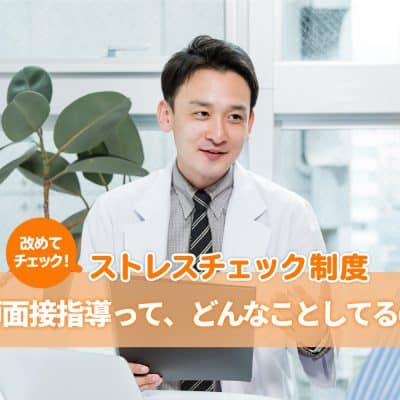働き方改革の中心的な施策の一つにある「同一労働同一賃金」とは、【同じ業務同じ付加価値を生む労働に対して契約や社内の立ち位置に関わらず同一の賃金・対価を支払うべき】という 考えです。「同一賃金」というと給与金額のみをクローズアップしてしまいがちですが、この言葉には「待遇」についても同様とされています。
これから改革の進む日本社会、 時間のかかる給与体制の見直しと並行して福利厚生や手当制度の増設・活用による「同一労働同一賃金」の達成を計画している企業の増加も見込まれるでしょう。
給与と違い、金銭以外の独自の形・サービスをもって行うことができる「福利厚生」や働く方の背景に合わせて支給できる「手当」は従業員満足度を上げ長期的な就労を促すほか、企業の人気度を向上させ人材不足に効果があるとされています。
では、実施する際に気になる「福利厚生」と「手当」 の違いとは一体何でしょうか?
福利厚生は“従業員全員”が対象となる
福利厚生とは、「 従業員全員を対象とした、従業員の生活の質を向上させる目的で通常の給与以外に支給する 非金銭的な報酬 」です。 対象は「その企業で働いている従業員」が主になりますが、内容によっては従業員の家族、あるいは退職者も対象とすることができます。
福利厚生を行う目的としては、従業員満足度・貢献意欲を高める、意欲や能力の向上機会を提供する、 離職率の低下や労働力の定着……といったものが挙げられます。 優秀な人材・長期の労働力の確保といった効果が期待でき、企業を長期的に成長させていくには欠かせない経費となります。
内容は大きく「 法定福利厚生 」と「法定外福利厚生」に分けられます。
☆法定福利厚生
企業が実施するよう義務付けられた福利厚生
雇用保健・健康保険を始めとする各種
★ 法定外福利厚生
企業が独自に行う、様々な生活のサポート。
日本経団連「 福利厚生費調査 」では 7種類にわけられる 。
・ 住宅関連
・ 医療・健康
・ ライフサポート
・ 慶弔関係
・ 文化・体育・レクリエーション
・ 福利厚生代行
・ 共済会 、その他
法定福利厚生は、「社会保険の費用の負担」が相当します。従業員を抱える企業には雇用保険・健康保険等の加入が義務付けられていますので、従業員の生活を支える最低限の「企業の福利厚生」として考えられるでしょう。
法定外福利厚生は 企業が独自に設けるものになります。会社の取組みごとに幅広く、自社で運営・提供するものの他に他社のサービス提供を支給することも該当します。
福利厚生の代表的なものと言えば、昔から現在に至るまで「社宅・食堂の設置」「医療、保健施設の運営・ ワクチン代金の補助 」ほか従業員の生活や健康をサポートするものが主流ですね。近年にはいって、人材確保・生活の質向上のための「社員旅行等の レジャー計画・運営」などレクリエーション提供、「慶弔関係の費用補助」といったものも登場し、一般化しました。
また、高齢化社会の影響を受けて「介護サービスや保育所の提供」といったものも人気を集めています。
諸手当とは?
一方「手当」とは、「 特定の条件に当てはまる労働者を対象にした、 基本の給料のほかに支払われる賃金」です。福利厚生との大きな違いは「支給に条件があること(従業員全員ではないこと)」「賃金として支払われること」となります。
各種手当についてはその企業の就業規則で定められることとなっています。手当の有無や条件、支給額などを定めた法律などはなく、それぞれの企業ごとで異なっています。 公務員については一般職の職員の給与に関する法律やその他規則、各地方自治体の条例 で定められているようです。
なお、ボーナスと呼ばれる「賞与」は手当とは別枠とみなす場合が一般的です。
手当の内容は企業によるものですが、良く聞かれるのは職務・勤務条件によるもの(夜勤手当・ 時間外手当 )でしょう。特殊な業務に携わる方は資格手当、家族を持つ従業員には 扶養手当、通勤定期に使用する通勤手当……といった従業員のスキル・背景に合わせた各種手当を設けることはすでに一般的か思われます。
企業の規模や諸外国と比較した諸手当の比率
厚生労働省の「平成27年就労条件総合調査」によると、基本給と諸手当の比率は平均でそれぞれ86%、14%となっています。企業の規模別に諸手当の比率をみると、従業員数が1,000人以上の企業は11.6%なのに対し、従業員数が1,000人未満の企業では16.4%と、大企業ほど諸手当の比率が低く、中小企業ほど高くなっています。
具体的な諸手当の金額としては、「業績手当等」が平均5,7000円、「役付手当等」が平均3,8000円、「精皆勤手当等」が平均10, 000円となっています。高額なこれらの手当てが付くか否かで給与の総額は大きく変わってくるのです。「精皆勤手当」は、企業規模でみると大企業よりも中小企業の方が付けているところが多く、業種別にみるとサービス業よりも製造業や運輸業で付けているところが多いようです。一方、「生活手当」は大企業の方が中小企業よりも多くなっています。
国際間で比較をすると、手当の種類と額が多いのが日本の特徴です。
諸外国では通勤手当などの費用的な手当てを除き、その他の手当が存在しない企業も少なくありません。日本で当然のように発生している生活手当は仕事と関係なく「従業員の生活環境」「適応される契約の内容」によって決まるため、同じ仕事をしているのに給与の額が異なるという従業員間の格差が生じる要因となっています。
諸手当のメリット・デメリット
様々な状況に合わせて決められる手当は一見、従業員にメリットをもたらす親切な制度のように思われがちですが、見方を変えれば従業員間に給与格差が生じ、不公平感をもたらすことにつながりかねません。
また、多くの場合は一度手当の制度を設けてしまうと、手当をなくすことは従業員にとって不利益な変更となるために容易ではなく、結果として賃金体系をゆがめてしまうことになります。
手当を設けることが企業と従業員の両者にとって本当にメリットがあるのかどうか、しっかりと考えて設定することが大切です。
| 初出: 2015年10月29日 / 編集:2019年09月12日 |