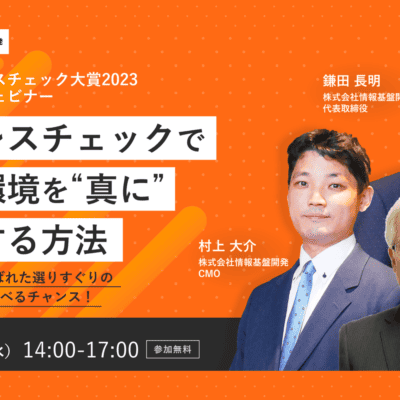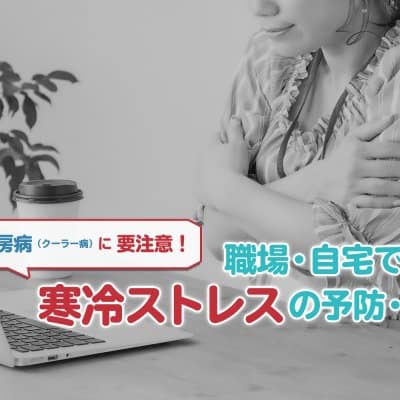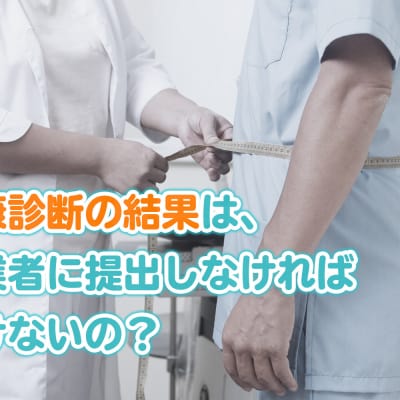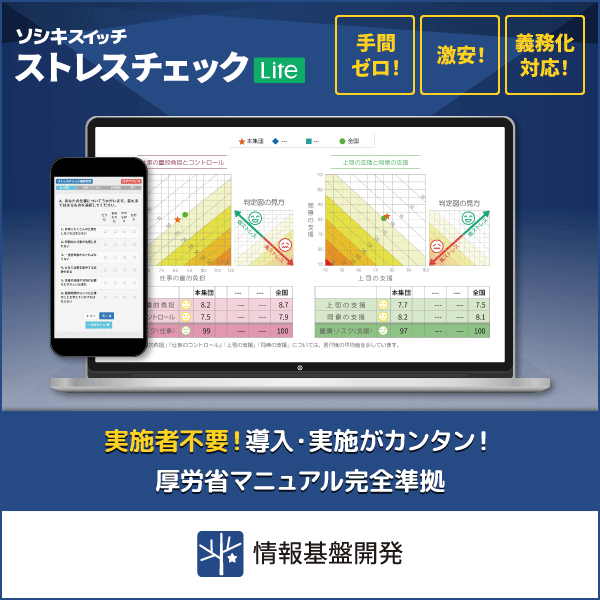子どもが突然風邪を引いたり、高齢の親の介護が必要になったりということは多くの人にあり得ることですよね。
労働者が子どもの看護や家族の介護のために仕事を休む権利は「育児・介護休業法」で守られています。
この記事では看護休暇・介護休暇・介護休業の内容や違いを見ていきます。
看護休暇・介護休暇・介護休業は法律で守られている労働者の権利ですので、制度導入をしていない企業もこれを機に社内制度の見直しをされてはいかがでしょう。
看護休暇は子どもの病気・怪我・健康診断・予防接種のために取得できる
看護休暇とは小学校就学までの子どもが病気や怪我になったときなどに取得できる休暇です。 自宅での看護や病院の付き添い、子どもが健康診断や予防接種を受けるときにも利用できます。
1年間で子ども1人につき5日、2人以上の場合は10日を上限に制度を利用できます。
子どもが2人以上いる場合に1人につき5日が上限というわけではなく、1人分で10日制度利用も可能です。
看護休暇を取得する単位は今までは1日または半日でしたが、法改正により令和3年1月1日より1時間単位でも利用できることになりました。
基本的には該当する子どものいる労働者が対象となります。
労使協定によって、継続した雇用期間が6か月未満の人や、1週間の所定労働時間が2日以下の人を対象外とすることもできます。その一方で、労働者の配偶者が専業主婦・主夫であることや労働者が契約社員であることを理由に、雇用側が制度利用を拒むことはできません。
看護休暇を取得した期間を有給か無給にするかは企業の判断に任せられていますが、利用促進のためにも一部補償する等の対応が望ましいです。
看護休暇の証明は「診断書」以外でもOK
子どもが病気になったり怪我をしたりするのは突然のことも多いため、看護休暇は会社側に時季変更権はありません。
急に必要になる・すぐに対応しなければならないことも多いので、休暇の申請に電話やメールなどの手段を用いることもできます。
急に休むことができて電話やメールでも申請できると「不正に使われるのではないか…」と心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、会社側は看護休暇が必要なことを証明する書類の提出を求められます。
ただし制度を使っている従業員は今子どもの怪我や病気の世話が必要となっているので、事後提出を可能にするといった配慮が必要です。
病気や怪我の種類に指定がないので、看護が必要なことを示す書類といっても必ずしも医師の診断書にこだわるのではなく、薬の領収書や 保育園の連絡帳の写しなどフレキシブルな対応がベターでしょう。
なお、子どもの対象年齢は6歳になる年度の3月31日までと法律では決められているものの、身体がしっかり成長していない子どもが体調を崩すことは少なくないため、企業によっては看護休暇制度を6歳以降も使えるようにしている場合もあります。
就業規則や労使協定などで、実情にあった制度・規定を設けましょう。
介護休暇は「要介護状態の家族の介護」に取得できる短い休暇
介護休暇は病気・怪我・高齢により家族に介護が必要な場合に利用できる休暇です。
介護対象者1人につき1年で5日、2人以上は10日を上限に制度を利用できます。子どもの看護休暇と同様に、今までは1日または半日単位での取得のみとなっていましたが、令和3年1月1日より1時間単位で取れるようになりました。
制度を利用できる「介護対象者」となる人は、以下のとおりです。
- 事実婚を含めた配偶者
- 自身及び配偶者の父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- 孫
そのうえで、要介護2以上またはいくつかの介護が必要な状態が見られる場合に制度の対象となります。
介護休暇は、基本的に労働者であれば全員制度の対象として取得できます。
ただし、労使協定によって継続して雇用された期間が半年未満の労働者や、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とすることも可能です。
他に介護できる人がいることを理由としたり、契約社員であることを理由としたりして介護休暇を取ることの拒否はできません。
介護休暇も有給にするか無給にするかは企業の判断に委ねられています。
ただし無給の場合、年次有給休暇を使用した方が損をしないことから、介護休暇を利用する人は少なくなってしまう可能性があります。
介護休暇の申請は口頭や電話・メールなどの手段も用いることができます。看護休暇と同様に、企業は介護休暇の対象となる家族がいることや家族が要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることが可能です。
介護休暇を取得した労働者は要介護状態の家族の世話をしているため、事後提出でも可能にするなどの配慮はしましょう。
介護休業は要介護状態の家族の介護のための長い休業
介護休業も要介護状態にある家族を介護するための休業制度です。
介護休暇との違いは、その期間の長さにあります。制度を利用できる対象の家族は、介護休暇と同様に「配偶者・家族とみられる関係のある介護対象者」「要介護2以上またはいくつかの介護が必要な状態がある人」が対象と考えられます。
休業を申請する際には、各企業によって詳細は異なるものとなりますが、主に
・企業の定める介護休業申出書
・介護対象者の情報と従業員との続柄が確認できる書類
・介護対象者の要介護状態にあること等を証明する書類
・介護休業給付金支給申請書
の用意があるとスムーズに手続きが行えるでしょう。
なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や、医師の診断書を制度利用の条件とはできないと定められているので注意しましょう。
介護休業できる従業員は以下の条件のとおりです。
- 1年以上雇用されている
- 介護休業取得予定日の93日後から6か月以内に労働契約期間が満了することが明らかでない
- 労使協定で決められた労働者以外
介護の対象となる家族1人について93日まで休業ができます。期間は3分割して取得することも可能です。
介護休業の申請は、その他の休業などと同様に原則として休業を始める2週間前までを目安に行います。
企業は介護休業にあたり介護をする家族が要介護状態であることを証明する書類の提出を要求できます。提出方法は書類だけでなく電子メールやFAXを用いても良いとされています。
介護休暇と異なり、介護休業には会社経由で申請できる給付金があります。
看護休暇・介護休暇・介護休業の比較
看護休暇・介護休暇・介護休業の違いを見ていきましょう。
| 看護休暇 | 介護休暇 | 介護休業 | |
| 制度の対象者 | 小学校就学までの子ども | 要介護状態の家族 | 要介護状態の家族 |
| 取得可能日数 | 1人につき5日/年 2人以上で上限10日/年 | 1人につき5日/年 2人以上で上限10日/年 | 1人につき93日 ( 3分割して取得も可) |
| 申請方法・ 対応 | 各企業による (口頭・メール可) | 各企業による (口頭・メール可) | 原則2週間前に申し出が必要 (介護休業給付金が利用できる) |
企業は従業員が制度をスムーズに利用できるよう整えておきましょう
子育てしやすい職場環境は人材流出を防ぎますし、介護については今後多くの従業員が直面する問題となるでしょう。
企業は労働者がこれらの制度が必要なときにスムーズに使えるための配慮が必要です。
制度の制定だけでなく、制度を広く従業員の皆さんに周知すること、必要になった時に申請しやすい職場の雰囲気や業務分担の制度づくりなども企業ができる「働きやすい職場作り」の方法です。
病気や体調不良は突然訪れるもの、必要な時にすぐ制度を利用できるよう日頃から周知しましょう。
「お互い様」の雰囲気作りをし、必要なときに制度が使いやすい職場環境を目指してみてはいかがでしょうか。
- 厚生労働省:育児・介護休業法のあらまし
- 厚生労働省:⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕
- 厚生労働省:就業規則における育児・介護休業等の取扱い
- 厚生労働省:仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~
| 初出:2021年01月21日 |