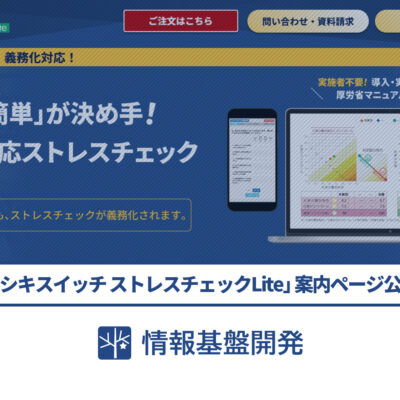企業には様々な義務があり、その義務を規定している法律も毎年何らかの変更や改正が加わっています。改定のすべてを把握するのは専門家でも難しいもの、知らず知らずのうちに法律違反をしている可能性もあります。
東京労働局による「 平成30年の定期監督等の実施結果 」をもとに、どんな労働関係の法律違反が起きやすいのか見てみましょう。
直近五年間で監督指導件数は年々増加
平成30年度(2018年)に東京都内で行われた 定期監督等 の結果をまとめた東京労働局のプレスリリースによれば、実施された 12,668 事業場のうち 9,188 事業場(全体の 72.5%) で何らかの 労働基準 に関する 法令違反が確認されました。
定期監督等とは?
労働災害の報告や その他の情報などを基に、労働基準監督 官が事業場に対して実施する検査や訪問のことを指します。 事業所や作業環境の労務管理・安全衛生の現状 を確認し、法令違反などが発見されれば是正・改善指導が行われます。
「建築現場について 墜落・転落防⽌を重点的に監督する」といった労基署独自の取り組みもありますが、 2013~2018年の5年間 監督指導件数は増加傾向にあります。
また、いずれの年も法律違反確認率は7割を超え「問題のある現場がくりかえしてしまう」というお話も聞かれました。
労働関係の法違反トップ5
過去5年分の監督指導件数・内容をまとめ、「労働関係の法違反トップ5」を独自に集計しました。
***
労働基準法分野では昨年に続いて【 労働時間 】に関連するが1位に。
関連した「割り増し賃金」「条件明示」についても件数は増加しており、いまだに時間外・長時間労働を前提とした働き方の問題が根深く残っていることを表しています。
労働安全衛生法分野では、作業環境にまつわる安全基準が1位となっています。衛生基準関連の件数が少ない部分を見ると、監督指導先に建築業界が多い分稼業環境・安全に対する指導が厳しく行われている影響でしょう。 次いで多いのが【 健康診断に関係する違反 】。報告もれ、実施なし、情報の取り扱いなど様々なものが含まれていますが2000件を超える違反が確認されています。
注目したいのが、「休憩時間に関する法律違反」です。2018年は昨年比増加率が高く、働き方改革で 長時間労働が規制された余波があらわれているのではないか、と推測されます。
また安衛法関連の違反は全体的に減少傾向にありますが、健康診断系の違反は逆に増加。安衛法全体の件数を増加させている原因とみられます。
| 安衛法違反の原因 | 労基法違反の原因 | |||
| 違反名 | 件数 | 違反名 | 件数 | |
| 1 | 安全基準 (20~25条) | 2,346 | 労働時間 (32・40条) | 2837 |
| 2 | 健康診断(66条) | 2,051 | 割増賃金 (37条) | 2470 |
| 3 | 安全衛生管理体制 (10~19条(14条を除く)) | 1,096 | 賃金台帳 (108条) | 1500 |
| 4 | 特定元方事業者・注文者 (30・31条) | 699 | 労働条件明示 (15条) | 1336 |
| 5 | 作業主任者 (14条) | 359 | 就業規則 (89条) | 1077 |
| 衛生基準(20~25条) | 304 | 賃金不払 (23・24条) | 541 | |
| 定期自主検査(45条) | 181 | 休憩 (34条) | 396 | |
| 作業環境測定(65条) | 163 | 休日 (35条) | 219 | |
| 合計 | 7,199 | 合計 | 10,376 |



引き続き「安全配慮義務」に対する注目アップの予想
この5年間の統計を通してみると、
・法違反件数の増加率はゆるやかに
・違反内容別で検証した際に、特徴的な増加が見られる
という傾向が確認できます。
働き方改革によって長時間労働問題の対策・従来の昼も夜もない働き方の見直しが急務として掲げられるとともに、契約社員や派遣社員といったいわゆる「正規雇用」でない方々やフレキシブルな働き方の推進が行われ、企業には新たな事務や制度に対する対応が迫られるタイミングが増加したこともあるでしょう。
また、新たに加わった「安全配慮義務」である【 社員の健康対策 】というのは明確に目に見える対策や結果が出るものではなく、風土自体から変えなければならない難しさもあって、長期間腰を据えて取り組む余力や計画を立てるためのデータ・調査ができない環境は日々の忙しさによって“今のまま”にされてしまうことが考えられます。
違反をくりかえしてしまう・法律を知らない環境は、その背後にある事情――「立ち止まれないほどの忙しさの原因」や「労働環境への無関心」から対応しなければならない問題です。
通常業務に加えて、就業規則や契約の見直しや知識のアップデートなどが求められる中、 “ 改革に間に合わない ”企業の対応が求められているのではないでしょうか。
- 東京労働局:平成30年の定期監督等の実施結果
| 初出:2019年10月16日 |