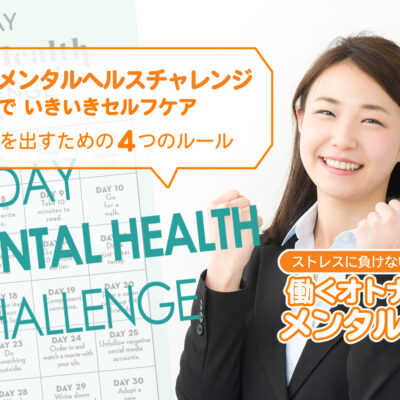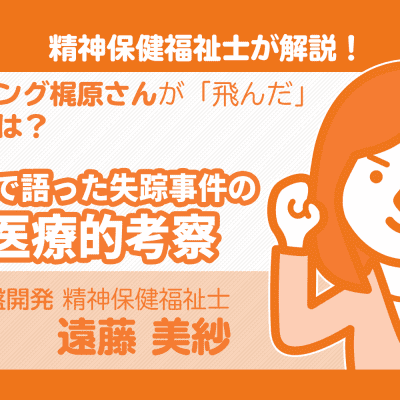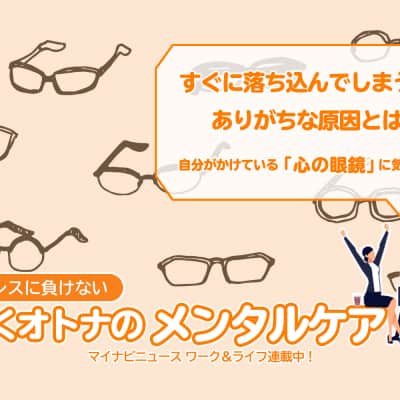2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」によって犠牲となられた方々へ、心よりお悔み申し上げます。
被災者ならびにそのご家族と関係者の皆さまに対してお見舞い申し上げると共に、皆さまの安全と被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
地震・津波・火災・台風・大雨洪水……
日本で暮らす私たちにとって、災害は決して他人ごとにはありません。
被災時はくれぐれも身の安全を第一に考え行動していただきたいのですが、命の危険に関わる経験は、強いストレスとしてその後の心身に大きな影響を与える場合があります。
その日、その場では冷静に対処できても、一週間・二週間と日が経ってから不調が表れてくることもあります。これからの生活への不安や、避難生活のストレス、もし持病や傷病があればそのつらさもあるでしょう。
心に大きな衝撃を受けるようなショッキングな出来事は、回復までに長い時間が必要です。自分が当事者になってしまったとき、または、大切な人が災害の被害に遭ったとき、自分の心を守りながらも、相手に寄り添うことができるように。
“災害時のメンタルヘルス”について、知っておいてほしい「こころの知識」があります。
もし災害の被害にあったら……
私たちの心と体に起こる“反応””
災害など強いストレスとなる出来事を体験すると、私たちの心身は自らの身を守るために、緊張や混乱、否認などさまざまな反応を引き起こすことがあります。
血圧や脈拍が変動したり、筋肉の緊張が取れなかったり……
突然感情の揺り返しが起こったり、悪夢やフラッシュバックに悩んだり……
被災直後から数カ月にわたって起こるこのような現象は【ごく正常な反応】です。
まずは、安全・安心・安眠が確保できる環境へ、可能な限り早くアクセスすることが必要です。
- 安 全 … 災害の影響を避け、風雨をしのぎ安心して体を休める時間・場所
- 安 心 … 公的なスタッフや医療従事者、支援者がきちんと機能していて、 “守られている”と感じることのできる空間や関係性
- 安 眠 … 体を横たえることができるスペース、体温を保つ寝具や静かな環境など、一定時間以上の睡眠がとれること

トラウマティックストレスとは?
通常の日常生活ではめったに経験することのないほど悲惨で恐ろしく、強烈な体験をしたことが原因で起こる強いストレスによって、心に重い傷を負ってしまった状態をトラウマ(心的外傷)と呼び、このトラウマ(心的外傷)を引き起こす出来事のことを「トラウマティックストレス」といいます。トラウマティックストレスは、経験した人に精神的に大きな衝撃・ダメージを与えます。多くの場合、自分や身近な人の身が危険にさらされること、命の危機に関わることと関係しています。例えば、大きな災害や事件、事故のほか、戦争やテロ、性的暴行、誘拐や監禁、精神的・身体的な暴力などを自分が直接的に体験した場合、もしくは、身近な人や他人が被害に遭っているのを目撃した場合などが挙げられます。
命の危機を感じるような状況・経験からくる緊張は、簡単にほどけるものではありません。
また、身近な人を喪失する体験は、誰にとってもつらく慣れることはないでしょう。
大事なのは、
「自分の心身にどのような反応が起こっているのかを知る」
「心や体に不調を感じるのは正常なこと。時間がかかるかもしれないがいつかは回復する・受け止められるようになる」
この2点をしっかり心に留めておくことです。
トラウマティックストレスに起因した心身の反応には、次のようなものがあります。
トラウマティックストレスによって起こる心身の反応とは?
①感情・思考の変化
ストレスとなった出来事について考えることができない・拒否してしまう時期と、そのことばかり考えてしまう・自責してしまう時期が繰り返すことがあります。
・現実を受け入れられずに、 茫然自失・感情がマヒしたような状態になる。
・強い落ち込みやストレス対象に対しての強い怒り、いらいら、何を感じているのかわからず混乱する。
・突然涙が出てきたり、怒りが抑えきれず言動を自分でコントロールできない。
・自分自身を責める、自分に原因があるのではないかと思う。
②身体の変化
特に気を付けていただきたい身体反応のシグナルは次の5つです。
不眠:不安、恐怖のために眠れなくなる、夜中に起きてしまう、悪夢を見る
内臓や消化器官の不調:腹痛、喉の渇き、吐き気、 嘔吐
体の痛みや不調:胸の痛み、筋肉の震え、歯ぎしり、けいれん、息苦しさ、過度の肩こり
皮膚や感覚の異常: 湿疹、視力聴力の低下、しびれた感覚がとれない、
自律神経の乱れ:頭痛、寒気、発汗、めまい、高血圧、動悸
これ以外の症状でも災害によるストレスが原因の不調が起こることがあります。
③認知・感覚の変化
知っている道や作業でも混乱したり、集中したり何かを楽しむことに困難を感じます。
小さな変化や物音に過敏になったり、優柔不断になった、うまく雑談ができない等「物事に反応するのが難しい・怖い・緊張する」と感じることがあります。
④行動の変化
食欲不振や不眠といった反応以外にも
・逆にたくさん食べたくなる、お腹がすいていないのに食べてしまう
・夜型、朝型など普段と違う睡眠リズムになった
・痛み止めやその他の薬、アルコールなどに依存してしまう
・直った癖や依存がぶり返す
感覚的な変化も併せて、行動がスムーズにできなくなったり、以前の人間関係から遠ざかる・引きこもるなども注意です。
もし、紹介したような「被災時の強いストレスから来る反応」が一か月以上続くような場合は注意しましょう。
症状によっては、いち早く専門家に相談することも必要
一か月未満であっても、状態が悪く、回復やコミュニケーションに支障をきたすような症状がある場合は、なるべく早く専門家へ相談してください。
強いストレスを感じた後の緊張や反応は誰にでも起こる「普通のこと」ですが、苦痛や怒りで自分や他人を傷つけてしまうときには何らかの対応が必要です。状態によっては、自身を客観視することがままならなくなっている可能性も。
以下のような自覚症状がある、あるいは周囲の人でこのような症状が見られる場合には、なるべく早く精神科医・心療内科医やカウンセラーなど心の専門家に相談しましょう。
● 1週間以上不眠が続いている。
● 1か月以上強い緊張や興奮が取れない、続いている。
● 言動が不穏で、周囲に対して被害的な言動が目立つ。
● 表情が全くない。受け答えが過度に端的・機械的になった
● ストレスによる身体症状・身体反応が深刻
● ひどく落ち込んでいたり、自殺の恐れが感じられたりする。
災害や恐ろしい体験をしたときに受けるストレスは、その人の人生に長い間大きな影響を残します。
災害や事件から1ヶ月以上経過しても緊張や些細なことにも過敏になる状態が続き、つらい経験が自分の意思に反して思い起こされ、再体験されるような状態を心的外傷後ストレス障害(PTSD)といいます。
PTSDの多くは3ヶ月以内、正しい治療や心身のケアを受けることができればより短い期間に回復することが多いです。
しかし、受けたストレスの強さによってはそれ以上症状が続く場合もあります。
自分を守る・大事な人に寄り添うために
知っておいてほしい5つの約束

避難中など限られた環境では、医療機関にかかることは難しいかもしれません。それでも、必ずきちんとしたケアを受けられる環境が戻ってきます。
安心して暮らせるそのときへつなげるために、「災害から心を守るメンタルケア」5つの約束を普段から理解してほしいと思います。
1:「動揺するのはあたりまえ」だと理解しましょう
災害や非日常的な事件を経験したら、体調不良・動揺・不安による行動や感情は【ごく自然な、誰にでも起こりうる反応】です。
この反応は直後に起こることもあれば数か月後に襲ってくることもあります。
もし取り乱してしまった人や不安で混乱している人を目にすることがあったら、「あぁ、つらいんだな」と理解して一緒に安心なところまで避難する・医療につなぐことが第一です。
2:しばらくは一人にならない / 一人にしないように注意を
不安な状況で一番精神に負荷のかかることは、「周囲とのつながりを失う」ことです。被災やショックを受けることがあったらしばらくは極力一人になることを避け、親しい仲間や家族など安心できる人たちと過ごすようにしましょう。
気持ちを共有できること、お互いの信頼感、連帯感が感じられることが肝心です。
これは、災害後に起こる窃盗や犯罪といった「二次被害」から身を守るためでもあります。小さなお子さんや高齢者などが一人でいるようでしたら、明るく優しく挨拶をしてあげてください。
3:飲酒を控え、体の健康・衛生状態に気を付けて
緊急事態では、さらなる避難や移動がいつ起きても不思議ではありません。飲酒は避け、常に衣服・靴・携帯電話などの連絡手段は手の届くところに置いておきましょう。
また、緊急事態の中で体調を崩すと心細くより不安感・被害的な感情を掻き立てます。食事・睡眠の機会はなるべく確保し、規則正しい生活と定期的な運動で体力を衰えさせないよう過ごしてください。
持ち出し袋にトランプや愛用のぬいぐるみなど一つ娯楽用品を足しておくと心の余裕につながります。自然災害であれば普段接することのない菌や汚染の中活動することも想定できます。眼鏡やマスク、長袖長ズボンは外に出るとき必ず身につけてください。
4:元に戻るまでには「時間」が必要です
ひと段落したら、心身に強い反応が起きてくることもあります。また、正常な反応でも数カ月にわたって症状が続くことも起こりえます。回復する過程で、恐怖や不安がぶり返すことも往々にして見られます。
元に戻らないのではないかと投げやりになったり、一人で抱え込んだりせずに、まずは誰かに相談してみてください。
相談も、うまく伝えられずに焦ったり、言葉にできない自分にいら立つこともあるかもしれません。決して急がずにゆっくりと自分のペースでお話してください。
5:配慮はしても、無理や我慢はしないように
責任ある大人として緊急事態に直面しているとき、その場では落ち着いて対応ができていても、そのとき感じたストレスや感情を受け止める時間がどこかで必要になります。
安心して話せる場所ができたとき、または生活が安定し気持ちに余裕ができ始めたとき、自然に湧いてきてしまう感情は「素直に表現していい」と自分に許しましょう。
悲しいことや辛いことがあっても、ずっと悲しんでいなければならないわけではありません。生活の中の楽しいこと、笑ったり怒ったりといった感情の動きを一つずつ取り戻していくことが「こころの復旧」です。
また、被災した人々を支えるスタッフとしても、「支えている・ケアを提供している」ことで無理な約束をのんだり、必要ないところまで自分の感情を抑えることはありません。
悲しい気持ちの真っ只中にいる人に寄り添うばかりでなく、ショックを受けた当事者・支えたいと思う関係者・安全や生活を守るスタッフそれぞれが自身の心や楽しみを大事にし、新たな活力を養うひと時を大事にしましょう。

災害をはじめ、事件や事故など強いストレスを感じることがあれば、さまざまな症状や行動・感情の変化は当然起こりえます。それは自分が弱いわけでも、おかしいわけでもありません。
そのことをきちんと知っておき、自分を責め過ぎないよう、誰かを責めてしまわないようにしましょう。
災害時やその後の避難生活で一番気を付けてもらいたいのは「休息をとる」ことです。
緊張や活動時間が長時間続いてしまうと、脳はストレス物質を吐き出すことができず、より緊張感や不安感を高めてしまい、それが体にも影響を及ぼします。眠れない場合でも、一日活動をしたら必ず「目を閉じて横になる時間」をどこかで設けてほしいと思います。
〔参考文献・関連リンク〕
- こころの耳:被災者に対するこころのケア(被災者やその家族、支援者などの方へ)
- 防災リテラシーを身につけるための 学習プログラム整理・体系化サイト「 防災リテラシーハブ 」
- 社団法人 農協共済総合研究所 : 震災による自殺 ~直接被害と間接被害、被害の広範化~
- 厚生労働省:厚生労働科学研究費補助金「PTSD及びうつ病等の環境要因等の分析及び介入手法の開発と向上に資する研究」
- 東京都保健局:災害時の「こころのケア」の手引き
- 独立行政法人労働者健康福祉機構 :職場における災害時の こころのケアマニュアル

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
| 初出:2020年09月15日 / 編集:2024年02月08日 |