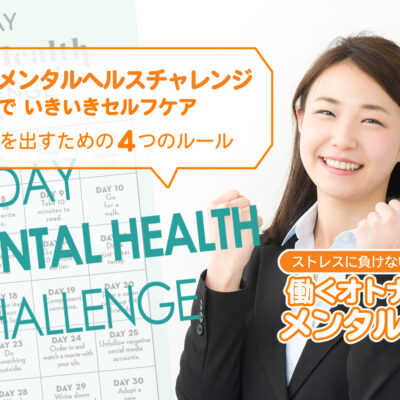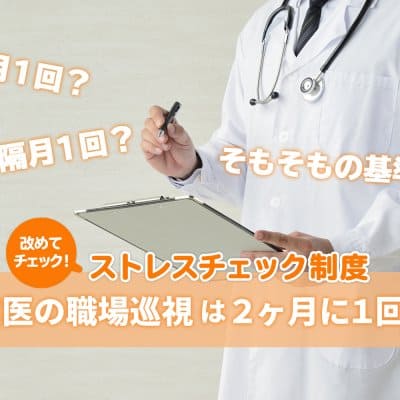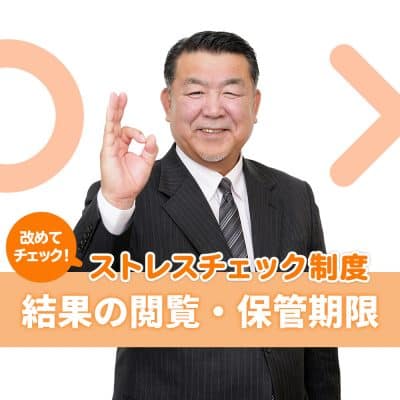健全な精神=健全な肉体?
「健全な精神は健全な肉体に宿る」と言われているように、メンタルヘルスの向上には健康的な生活習慣が欠かせません…と言いたいところですが、実は「健全な精神は健全な肉体に宿る」という言葉は誤訳であると言われています。
「健全な精神は健全な肉体に宿る」という言葉は、古代ローマの風刺作家で弁護士でもあったデキムス・ユウニウス・ユウェナリス(Decimus Junius Juvenalis, AC60- 128)が風刺詩集に書き記した
「You ought to pray for a healthy mind in healthy body.」 (原文ラテン語の英訳)
という言葉が由来となっています。
専門家によれば、この言葉が含まれている詩では人間の欲しいものがどれだけ分不相応であるか、神様に誰もがお願いする「富・権力」「長寿」「美貌」をあげその不毛さを嘆くものだといいます。
前後の文脈や内容を踏まえると、この言葉は「願うならば、心身ともに健康であることを願う程度にしておきなさい」と訳すべきである、というのです(下記参照)。
人々は間違ったことばかりを神様にお願いしている。
例えば金持ちになること、 例えば長生き、例えば美貌。
花房友一訳『第10歌 願い事はほどほどに』※「世界の古典つまみ食い」掲載
しかし、これらはなかなか手に入りにくいだけでなく、手に入ったところで決して持ち主を幸福にはしない。
金持ちになっても泥棒の心配が増えるだけ。長生きしても、もうろくした人生にいいことはない。美人になっても不倫に陥って苦しむだけだ。
「心身ともに健康であること」。願うならこの程度にしておきなさい。
これなら誰でも自分の力で達成できるし、それが手に入ったことによって不幸になることもない。しかし、けっしてそれ以上の大きな願いを抱いてはいけない。
「健全な精神は健全な肉体に宿る」とは言わなかったユウェナリス
心身共に健康に!……と思うくらいがいい、らしい。
すなわち、「You ought to pray for a healthy mind in healthy body.」という言葉の本当の意味は、「健全な精神を手に入れるために、しっかり体を鍛えるべきである」ということではなく、「神に願うなら、心身ともに健康であることだけを願うのが望ましい」ということです。

※写真はローマにある「トレヴィの泉」の彫刻
この間違いはどうやら、もともとのラテン語から英訳される際に、抜き出されたフレーズが独り歩きしてしまったことが原因のようです。
確かに 日本で現在使われている「健全な精神は健全な肉体に宿る」 の元となったのは英語のことわざ “A sound mind in a sound body’‘ ですが、 これだけでは「健全な身体の中の、健全な精神」 というセンテンスだけ。とても覚えやすいですが、主語や意味、「それが何なのか」は含まれていません。
だからこそ、使う人が自由に解釈できるわけですね。
今日では前者の誤訳が一つの解釈になってしまっている感があり、多くの人が(たとえそれが誤訳であるとしても)「健全な精神は健全な肉体に宿る」ということを信じたり、実感したりしているのもまた事実です。
本来の詩文でも「健康な肉体」や「健康な精神」は神様に願うほど手に入らなかった貴重なもの、古代ローマでも現代でも過ぎた欲を持たない方が健康を保つより簡単だったのかもしれません。
あながち間違いではなかった「誤訳」
ですが、最近の研究では、メンタルヘルスの向上には健康的な生活習慣が欠かせないということが明らかにされています。

朝起きて日光を浴びるなど、規則正しい生活はうつや不安障害等の治療にも有用であることは研究や統計データでもはっきりと示されています。
また健康的な生活習慣には、定期的な運動〔有酸素運動(ウォーキング、水泳等)、ストレッチ等〕、栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠等といった要素がありますが、これらの生活習慣を保つことで高血圧や生活習慣病の予防に加えて、ストレス耐性の強化や気持ちの切り替えのスムーズさにいい影響を与えていることがわかってきています。
「健全な精神は健全な肉体に宿る」というのは誤訳ではありますが、殊にメンタルヘルスの観点から言えば、核心を突いた言葉なのかも知れません。
〔参考文献・関連リンク〕
- 大阪市立大学看護学雑誌 第5巻(2009年):「健全なる身体に健全なる精神:ユウェナーリスの 『風刺詩』第10編について」
- 花房友一『世界の古典つまみ食い』:「健全な精神は健全な肉体に宿る」とは言わなかったユウェナリス
| 初出:2016年3月23日 / 編集:2019年09月30日 |