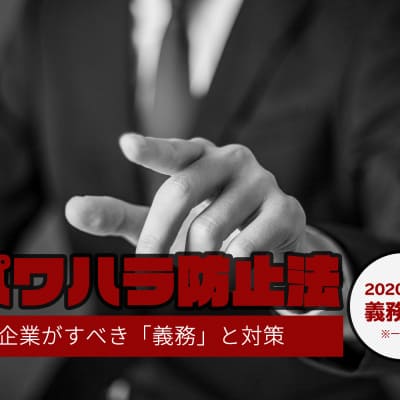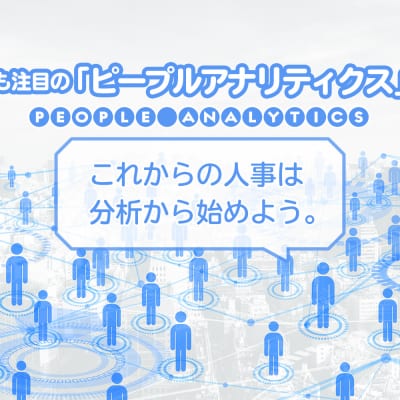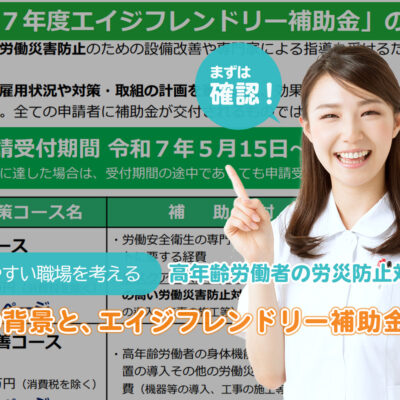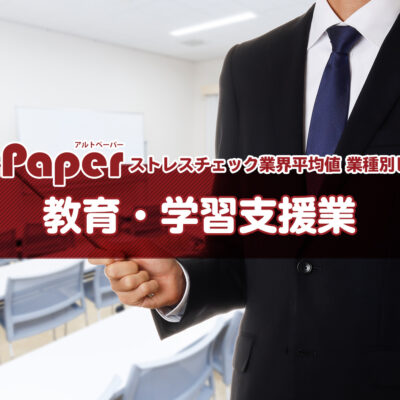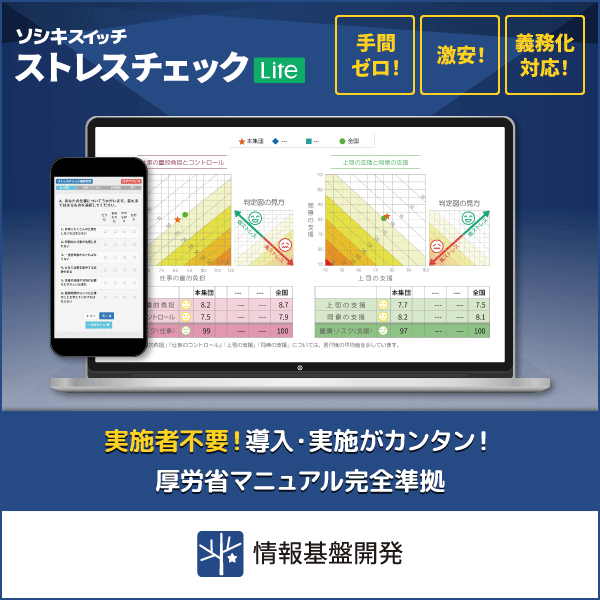皆さんは【 ワークエンゲージメント 】という言葉をご存知でしょうか。
「バーン・アウト」(燃え尽き症候群) の提唱でも名高いウィルマー・B・シャウフェリ教授は、それらの研究から「働く」ことに対するモチベーションに認知・感情・身体の3要素が深く関わっていることを示しました。
それら3要素がうまく作用しポジティブで充実した心理を維持している状態――つまり「働きたい!」という仕事に関連する肯定的な心理と姿勢の概念が「ワークエンゲージメント」なのです。
仕事に対する肯定的な心理状態を持ってもらうことで労働者の心の健康・パフォーマンスの向上、増進を目指す「根本的」な取り組みとして、今「ワークエンゲージメントの向上」が注目を集めています。
ワークエンゲージメントを高める3つの要素
ワークエンゲージメントが高いと、企業全体としての生産性が向上することが確認されています。
ワークエンゲージメントを高めるためには、それを構成する3つの要素を総合的に充実させることが必要です。
- 活力
活力とは、仕事に対する積極的な取り組みによって生まれるエネルギーを指します。やりたくない仕事に対してエネルギーをもって取り組むことは、誰でも難しいでしょう。仕事の割り振りや、適切な人員配置などにより、労働者が積極的に仕事に取り組むことのできる環境を整備することが活力の向上につながります。
- 熱意
熱意とは、自分の仕事に対して誇りを持つことです。自分にしかできない仕事、自分の学んだことを活用できる仕事の方が熱意をもって取り組むことができるでしょう。また、興味のある分野や成長したい分野の業務であれば、積極性をもって取り組むことができます。熱意があると、現在取り組んでいる業務内容だけでなく、関連する分野についても同様に関心が高まるとともに学習効率がアップします。スキルの向上を図ることができれば、サービスや製品の質がおのずと向上し企業と労働者双方にとって非常に有益でしょう。
- 没頭
没頭とは、他のことを忘れてしまうくらいに集中して取り組んでいる状態です。没頭して仕事に取り組んでいる状態は人為的なミスが生じにくく、作業の工程や動作の無駄が少なくなる傾向があります。また、「今の業務」に集中している状態になると、より効率的な作業の方法はないか、無駄な工程はないか注意を配るようになり自発的に作業効率が高まることが期待されます。
メンタルヘルスに対するワークエンゲージメントの効果
ワークエンゲージメントが高まると、労働者のメンタルヘルスに関連して以下のような効果をもたらすことが期待されます。
- ストレスを感じることが少なくなる
ワークエンゲージメントが高まった状態というのは、興味のある仕事に対して熱心に取り組んでいる状態です。誰でも嫌々ながら仕事に取り組むよりは、自分の興味のある分野に取り組みたいものです。仕事に対して肯定的な考えを持って取り組むことができれば、もし問題が生じたとしてもポジティブな考え方で解決することができます。この結果、仕事によるストレスを感じる度合いが減少します。
- 根本的なメンタルヘルス対策を行うことができる
近年のメンタルヘルス対策の重要性の高まりからストレスチェック制度導入が義務付けられることとなりましたが、対処療法的な側面があることは否めません。高ストレス者を発見して要な人に面接指導を行うことや、集団分析を行うことにより職場環境の改善に取り組むことは確かに重要なことです。しかし、これは職場にストレスがあることを前提とした取り組みになります。
ストレスチェックの結果を活かして職場環境が改善されれば、ストレスを感じる人は減るかも知れません。職場環境によるストレスに着目し、その原因となる事項を改善していくという考え方も重要です。
しかし、それと同様に心の健康の増進を図り、ストレスに対して強い状態へと持っていくことも重要なのです。
ワークエンゲージメントを高めることによって個々の労働者が働きがいを感じ、自発的に業務に取り組むことこそが根本的なメンタルヘルス不調の対策といえるのではないでしょうか。
〔参考文献・関連リンク〕
- 島津明人(2014)「ワーク・エンゲイジメント―ポジティブ・メンタルヘルスで活力ある毎日を―」(労働調査会)
- Schaufeli, W. B., Shimazu, A., & Taris, T. W. (2009) “Being driven to work excessiveiy hard: The evaluation of a two-factor measure of workaholism in The Netherlands and Japan”. Cross-Cultural Reseach, 43: 320-348.
- Locke, E. A. (1976) “The nature and causes of job satisfaction. In: M. D. Dunnette. (Ed.)”. Handbook of
- Industrial and Organizational Psychology. pp.1297-1349, Chicago: Rand. McNally.
| 初出:2019年1月31日 / 編集:2023年06月12日 |