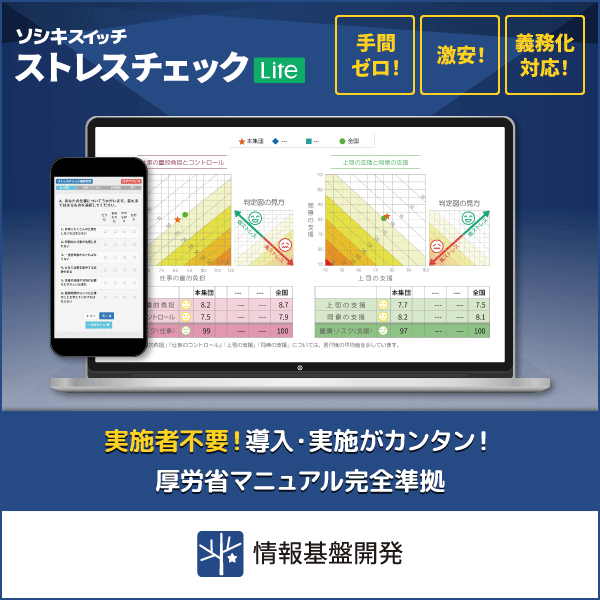抱えている仕事や自分の体調、人間関係の悩みなどのストレスが積み重なり、ささいなことにカッとなり言い返してしまう、部下や同僚、家族などに強くあたってしまいあとから後悔……といった経験は、多かれ少なかれ誰にでもあるのではないでしょうか。
忙しいとどうしても余裕がなくなってしまうのは、仕方のないこと。
ですが、ついつい出てしまった怒りの感情が、仮に「悪気はなかった」「本心ではない」「しまった…と思い訂正した」としても、それを受けた相手をひどく傷つけてしまったり、大きなトラブルに発展してしまう場合もあります。
職場ではハラスメントにもつながりかねず、家庭生活でも家族との関係によくない影響を及ぼしかねません。
そんなときに覚えておきたい、アンガーマネジメントの「6秒ルール」を簡単にご紹介します。
怒りのメカニズムを知り、乗り切る!
「アンガーマネジメント」をご存じの方も多いと思います。
2020年に施行したいわゆる「パワハラ防止法」(中小企業は2021年4月~義務化)の影響もあり、最近は特に注目を集めるようになりました。
リスクマネジメントの観点からも、研修などを導入する企業が増えています。
私たち人間の脳は、強い怒りや感情を感じるとアドレナリンを大量に分泌します。
すると興奮状態になり、冷静な判断ができなくなってしまいます。
ここで衝動的に行動してしまうと、攻撃的な言動や相手を傷つける行動をとってしまうことも。
しかし、アドレナリン分泌のピークは「カッとしてから6秒まで」と言われています。

つまりこの6秒を乗り切れば、冷静な自分に戻ることはできます。
ただ、この6秒が結構厄介で、どんなに自分を律しコントロールできると自信をお持ちのツワモノだとしても、なかなか簡単なことではありません。
この6秒間に起こる衝動は、熱いものに触れたときに無意識に手を引っ込めるのと同じ「反射」のようなもの。本来は、自分を守る役割をしているのです。
この6秒をやり過ごす方法には、例えば、次のようなものがあります。
・ ゆっくり数を数える
・ 深呼吸をする
・ 体のどこかを動かす
・「自分は何にイライラしているのか」「何が頭にきているのか」を指を使って手のひらに書く
このほか、もうその場から離れてしまおう!という「タイムアウト」などの方法があります。
大切なのは意識をそらすこと。
そして、冷静な自分に戻ってから、状況に対処することでトラブルやギスギスした関係に発展してしまうのを未然に防ぐことができるのではないでしょうか。
なので、自分なりに6秒を乗り切れる方法を考えておくことがおすすめです。
怒りと上手く付き合い、適切に伝えるために
アンガーマネジメントと聞くと、怒りを抑える・コントロールするという印象が強いかもしれませんが、本来は適切に表現できるようになること・感情と上手く付き合うための練習です。
人前で感情を表に出すのはよくない、目上の人や相手を立てるべき、「空気を読む」という言葉が暗黙のルールとして存在する……日本人は昔から、個人の感情や意見を抑えることを求められてきたように感じます。
しかし、怒りも大切な、なくすことのできない感情の一つです。
一口に怒りと言っても、さまざまな状況で、感じ方も表れる形もその程度も違います。
まず大事なのは、怒りを知るということ。
そして上手く付き合っていくことが大切です。
怒りに限らず、不安な感情なども含めて、自分の意見を適切に相手に伝える術を身につけることで、むやみにストレスをため込みすぎず、もう少し余裕をもってとらえることができるかもしれません。
〔参考文献・関連リンク〕
| 初出:2021年11月12日 |