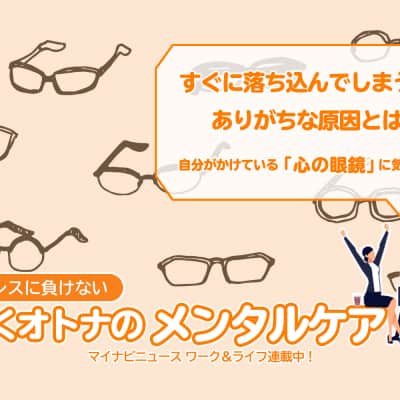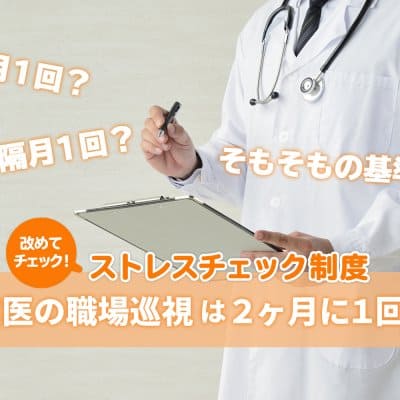テレワークの普及やライフスタイル、働き方の変化などで「家族みんながずっと家にいること」も珍しくなくなりました。
最も人との距離が近い場所である「家庭、家族」。一緒にいる時間が長くなると、親しい間柄であっても、わずらわしさやもやもやを感じてしまうこともあるかもしれません。
また、ネットや電話が普及しコミュニケーションの回数や密度が上がっているにもかかわらず、より一人であること、孤独感を感じてしまう……というお声も耳にします。
「なんだか家にいるのがしんどい」と思うときに、できることは何でしょう?
家族でも「当たり前」は一人ひとり違う
近しい人との間に生じるイライラは、その背後に「当たり前」のズレがあることがほとんどです。
例えば買い物や家事の方法・分担、ものを頼むときの話し方などもイライラの原因としてよく聞かれますね。実際、家族という集まりに対して「心のつながり・安らぎ」といった働きを期待する半面、「家族に対する不満度」が高いと孤独感を感じることが多いという研究結果も確認されています。
家族・親子といえど、不満を感じるラインは人それぞれ。特に生活習慣やに関わる部分は嫌悪感の感じ方の差もあって我慢がしにくい面が強いです。また一緒にいると「言わなくてもこれくらいわかるでしょ」と思いがちで、親しい相手ほどコミュニケーションがおざなりになってしまうという声も聞かれます。
家の中や生活習慣はどうしても外から見えません。自分では「これが常識」「この方法が当たり前」と思うことこそ、「本当は違うのかも……」と疑ってみると、新しい発見があるのではないでしょうか。家族になったからといって相手の「当たり前」が変わったり、「何も言わなくても伝わる」ということになったりはしません。
例えば、コロナ禍で経験した、衛生観念や感性症対策の「当たり前」には、皆少しずつズレが生じていたこと。振り返ってみるとしっくりくる方もいるのでは?今後も人それぞれ認識の違いにより、差を感じたり、もやもやしたりと、何かしら「当たり前の差」を感じる機会が増えてくるかもしれませんね。そこで、今一度、大事な人と「一緒に過ごすルール」を見直してみてはいかがですか。
一人で過ごす寂しさを「心の不調」にしないために
一人暮らしをされている方が、お家にいることが増えると、人とのコミュニケーションがガクッと減ってしまいます。私自身も、ここ数年で働き方や生活スタイルが変わり、仕事場やちょっとした外出で交わしていた会話が減ってしまい、一日中誰とも話さなかったということも珍しくなくなりました。
そうなってくると「なんとなく満足感がない」「やることはあるのに手が付かない」といった状態になりがちだと感じています。
「人と直接会う」「コミュニケーションをとる」ということの影響力は思うよりも大きく、話の内容に関わらず顔を合わせて話をするだけで人間の生得的な欲求のいくつかを満たすことができます。
逆に言えば、直接会う以外のコミュニケーションでは満たすことが難しい欲求があるということ。通信技術の発達した現在では、チャットや電子掲示板、音声電話、Webミーティングなど特色あるコミュニケーション手段が手軽に利用できます。目的やライフスタイルに合ったコミュニケーション手段をいくつか試してみて、それぞれの「いいところ」を体感してみてはいかがですか。
それと、人に会う機会が限られているときこそ「コミュニケーションの瞬発力」を磨くチャンスです。「ありがとう」「すみません」「お願いします」といった挨拶は、普段気にしていないからこそおろそかになりがち。機会を逃さないで対応できるように、宅配便の配達員や外出先の店員さんに「ありがとう」を伝えることを意識してみましょう。
一人でも、誰かと一緒にいても、孤独感を感じることはある
孤独感とは?
孤独感とは、実際に一人であるかどうかに関係なく、独りぼっちだと感じる気持ちのことを指します。社会とつながっていても、周りに家族や友人がいても、孤独感を感じることはあります。実際に周りとの交流がほとんどない状態・孤立している状況にはなくても、主観的に「自分は独りぼっちだ」と感じ、不安に陥ることは起こりえるのです。
孤独を感じるのは自然なことですが、孤独感に襲われ不安な状態が続くと、心や体に大きな負担がかかるだけでなく、心身の不調につながる恐れがありますので、そのままにせず対処できる方法を考えることが大切です。
では、孤独感を解消するためにはどうしたらよいのでしょうか。
孤独感でつらいときの対処法
例えば、次の方法を試してみるのはいかがでしょう。
- 孤独感を受け止め、自分の感情に目を向ける
- SNSから離れる
- 地域や趣味のサークルなど所属できるコミュニティを見つける
- 趣味や仕事、勉強に没頭する
- 運動など体を動かす機会をつくる
- ペットや植物を育ててみる
- 一人でも楽しめる趣味を見つける
まずは孤独を感じている自分を受け止めること。そして、なぜ、いつから孤独感を抱えているのか、何かきっかけはなかったかを振り返ってみることで、見えてくるものがあるかもしれません。
また、SNSを通じて流れてくる情報は、自分と他人を比べてしまいやすくなるため、思い切って一度離れてみることをお勧めします。
趣味や好きなことのために時間を使う、ペットや園芸など生き物に触れる経験は、それを通じて他の人と関わるきっかけも生まれるので、新しい世界やつながりが広がる可能性もあります。
体を動かすことによって、ストレスの解消や前向きな気持ちになる効果も期待できますので、感情だけでなく体の健康を気遣うことから始めるのもよいでしょう。
すると、一人で家にいる時間、自分自身と向き合う時間がつらいことばかりではなく、貴重で大切なものに変わるかもしれません。
どうしてもつらければ、早めに相談を
コロナ禍で提唱された「ソーシャル・ディスタンス」は、人と人との距離を2メートルあけることを推奨したものでした。実はこの2メートルという距離は、「パーソナルスペースを十分に守って会話がしやすい距離」でもあります。2メートルを実際に測ってみるとそこまで離れているとは感じません。「ダイニングテーブルを挟んで向かい合う」くらいの間隔というのがちょうどそれくらいでしょうか。家族や近しい人ときちんと心地よい距離を保って暮らしていけたらいいですね。
人間のパーソナルスペースは、相手をどう感じるかによって日々変わってきます。昨日は気持ちよく過ごせても、どちらかの体調が悪かったり嫌なことがあったりすれば、今日や明日は一緒にいるのがつらいというのもうなずけます。
「家族なのに一緒の部屋にいられないなんて」と思うかもしれませんが、これは人間の心理的な作用として正しいものです。無理に否定せずその感情を受け止めてみましょう。
「どうしてもつらい」「ダメになってしまいそう」と感じるなら、なるべく早く外部の人に相談を。内閣府男女共同参画局や厚生労働省「こころの耳」、市区町村やNPOなど各種団体が相談窓口を設けています。
「相談するのは恥ずかしい」「こんなことで相談してもいいのかな……」と深く考えすぎず、まずは気軽に、誰かに話してみませんか。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳:働く人の「こころの耳電話相談」
内閣府 男女共同参画局:「相談機関一覧」
厚生労働省:電話相談

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
| 初出:2020年05月04日/編集:2025年06月23日 |