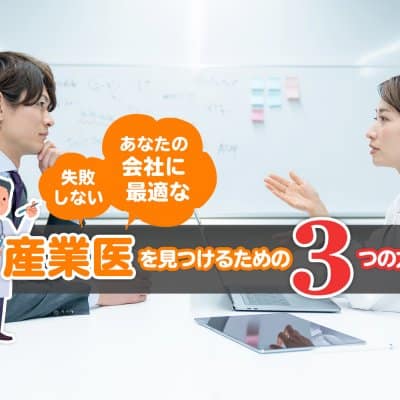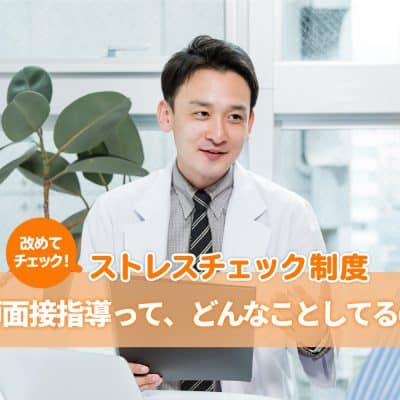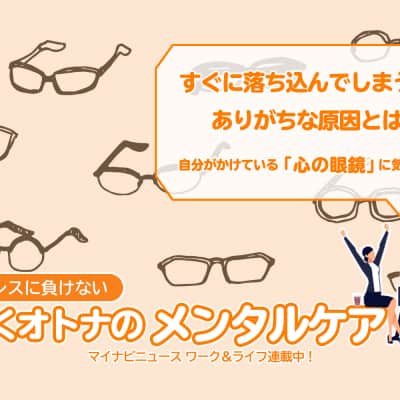障害者手帳はさまざまな障害によって支援が必要な方に交付される手帳です。
障害の内容別に「身体障害者手帳」「精神障害者福祉保健手帳」「療育手帳」の3種類に分けられ、それぞれの手帳取得者は福祉サービスや助成が受けられます。
どんな疾患が障害者手帳の取得対象となり、具体的にどのような福祉サービスが受けられるのでしょうか。
当事者や身の回りに障害を持った人がいる方はもちろんですが、障害者雇用率の引き上げに伴い、人事労務担当者も障害者手帳の制度について理解しておく必要があるでしょう。
障害者雇用促進法の改正に合わせて、これから注目度の高まる障害者雇用。
今回は、障害者手帳の種類から対象疾患、プライバシーへの配慮の必要について、障害者雇用に関わる担当者として知っておきたい内容について解説していきます。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、障害があると認められる人に交付される手帳です。
障害者総合支援法の対象である証明として、自治体のサービスや支援制度を利用するためには手帳の提示が求められることとなります。
障害者手帳の取得は任意です。障害が認められる方であっても、必ずしも手帳を取得しなければならないというものではありません。
ですが、障害者手帳を取得することで医療費の助成などさまざまな福祉サービス・制度の対象となることが可能です。また、企業への就職時に障害者雇用枠が利用できるなど一般雇用とは異なる応募が可能であることも特徴です。
手帳の取得や障害の開示を行うかどうかは「本人の意思」が尊重されます。雇用条件などを鑑みて、障害者手帳取得者でも一般採用枠で募集することも可能です。
障害者手帳の3つの種類
障害者手帳には以下3つの種類があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
どの種類の手帳も申し込みは各都道府県で行いますが、それぞれ対象となる疾患に違いがあります。
ここからはそれぞれの障害者手帳の対象疾患や概要について解説していきます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の方が取得できる手帳です。
具体的には、「対象の疾患だと診断される」かつ「その疾患による障害が一定以上あり、永続する(障害が固定され、身体機能が健康な状態まで回復する可能性が極めて低い状態)」を条件として設けています。
身体障害者手帳の対象となる疾患は以下のとおりです。
【対象疾患】
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
※参考:厚生労働省 「身体障害者手帳関連通知集」
身体障害者手帳はその条件上、大きな障害の状態変化が起こらない限り一度交付されると更新はありません。
疾患状態によって1級〜7級までの等級があり、各等級によって受けられる支援やサービスが異なります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、「精神障害の状態が一定程度にある」ために日常生活又は社会生活を送るうえで制約がある方を対象としています。
長期間その障害によって支障があることを要件としていますので、申請可能な期間に「その精神障害による初診日から6か月以上経過していること」という条件が設けられています。
認定の対象となるのは「全ての精神障害」と幅広く、うつ病や高次脳機能障害、依存症やストレスに起因する各精神障害、自閉症やADHD・学習障害などを含む発達障害などが含まれます。
対象となる障害の状況によって1級〜3級の等級に分かれていますが、精神障害の内容は人それぞれであること、ストレスを感じる・環境が合わないなど本人だけで解決できない要因に状態が左右されることもあり、手帳の情報だけでなく本人の状態や環境を踏まえる必要があります。
環境によっては就労が難しいケースもありますので、雇用時には業務内容・環境が本人に合うかどうか、コーディネーターなどを挟んで検討しましょう。
※参考:知ることからはじめよう「こころの情報サイト」精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
療育手帳の交付は主に児童相談所、知的障害者更生相談所で「知的障害あり」と判定された場合が対象となります。知的障害のある方が療育や援護を一貫して受けられるメリットのある制度です。
ただ療育手帳は他2種類の手帳とは異なり、運用方法は交付先である各自治体が定め実施されています。
手帳を利用して受けられるサービスや取得基準なども各地方によって違いがあるので、具体的な内容は住んでいる地域に確認が必要です。
※参考:厚生労働省 「障害者手帳 療育手帳」
障害者手帳によって受けられる支援とは?
各種障害者手帳を所持・提示することによって、各種助成や支援が受けられます。
車椅子や補聴器の補助金、障害者求人への応募、生活保護の障害者加算など生活に必要な支援から交通機関や博物館・映画館など公共施設の利用料の減免などサービスとして受けられるものもあります。
手帳の種類、障害の等級や対応の地方自治体によっても支援の内容や程度は異なります。
障害者手帳による支援を利用する際は、各地方自治体・施設、および事業者に確認することが必要です。
※なお、障害者雇用率の算定の対象となるのは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持っていることが条件です。障害者手帳を持っていない場合は、障害者雇用枠としての採用および障害者雇用率の対象にはならないため、注意しましょう。
障害者の雇用義務とプライバシーへの配慮について
「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用安定を目指すために法定雇用率を定め、事業主に対して障害者の雇用義務を課しています。そして達成状況について、事業主は毎年1回、6月1日現在の状況について、厚生労働大臣に報告しなければならないこととなっています。
企業が障害者を雇用する上で、以下のルールが定められています。
- 障害者雇用率(法定雇用率)
事業主に、下記の計算で算出する数の障害者を雇用することが義務付けられています。

※厚生労働省:障害者雇用率制度の概要より引用
- 障害者雇用納付金制度
法定雇用率を満たしていない事業主は、不足1人につき毎月50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます。
徴収された納付金は法定雇用率を達成している企業へ調整金・報奨金・助成金として支給されます。
- 障害者の差別禁止および合理的配慮の提供義務
事業主は募集や採用、賃金などの待遇において、障害の有無にかかわらず分け隔てない均等な機会・対応を行わなければなりません。
このように、事業主は、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金又は報奨金の申請に当たって、雇用している労働者の中から、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認する必要があります。これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正な取得、利用等を行うことが求められています。
障害のある方の新規雇用はもちろんですが、すでに雇用している社員の中に手帳を持っている方がいれば、新たに雇用率の算定の対象となることもあります。特に、精神障害者については、企業に採用された後に障害者となった・精神障害者手帳の取得をした方も少なくないと考えられることから、特にこのような方の把握・確認に当たってはプライバシーに配慮する必要があるとして、注意喚起がなされています。このような状況を踏まえ、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用等が行われないよう、精神障害者だけでなく、身体障害者及び知的障害者にも共通するものとして、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認の在り方についてガイドライン」が策定・公表されていますので、ご確認ください。
※事業主の区分(民間企業/国・地方公共団体等/都道府県等の教育委員会)によって法定雇用率は異なります。また、雇用率は今後も段階的に引き上げられる予定です。各最新情報については、厚生労働省等のホームページでご確認ください。
なお、下記の記事でも解説していますので、併せて参考にしていただければと思います。
〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省:
障害者手帳
身体障害者手帳関連通知集 - 知ることからはじめよう「こころの情報サイト」:
精神障害者保健福祉手帳 - 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構:
Q 障害を有していると思われる社員がいます。本人に障害者手帳などの有無を確認してもよいですか?
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要- 事業主の皆様へ -
企業において雇用率を算出する際の障害者の算定方法
| 初出:2019年09月26日 / 編集:2024年04月12日 |