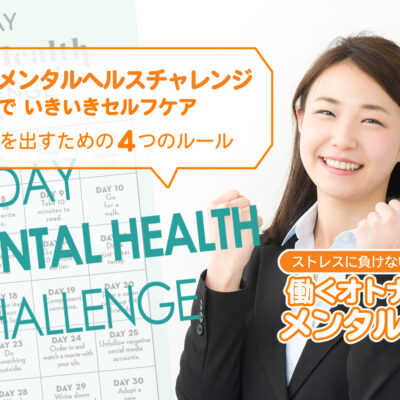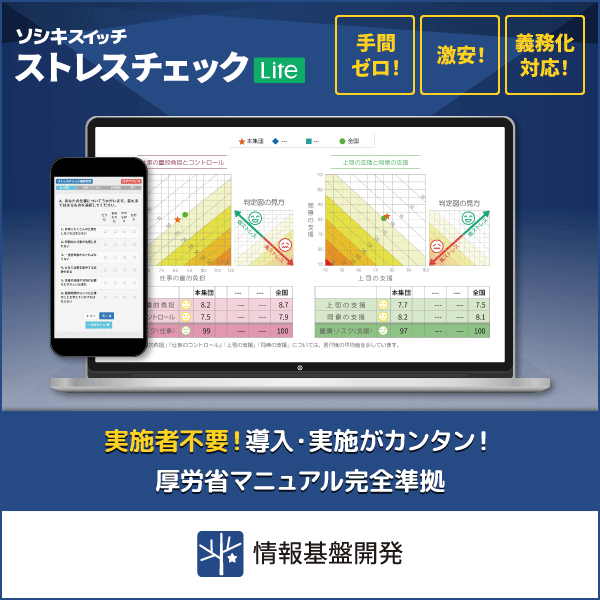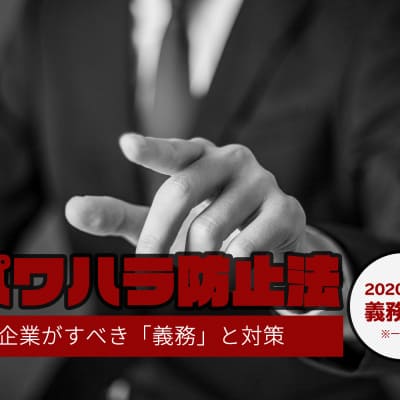新年を迎え、仕事始めから「さぁがんばろう!」と思っても、朝起きるのが辛かったり、体がしんどかったり、なんだかモチベーションが上がらない…
このような症状を、正式な医学用語ではありませんが、「正月病」「正月うつ」などと呼ぶことがあります。
正月病とは
正月病は、年末年始の長期休暇後に生じる心身の不調を指す俗称です。
主な症状には以下のようなものがあります。
- 疲労感や倦怠感
- 食欲不振
- 頭痛やめまい
- 集中力やモチベーションの低下
- 気分の落ち込み
これらの症状は、休暇中の生活リズムの乱れや、仕事への復帰によるストレスが原因となって引き起こされます。

「なんとなくやる気が出ない」
体内時計の重要性
正月病の主な原因の一つに、体内時計の乱れがあります。
体内時計は、主に脳と肝臓に存在し、私たちの生理機能や行動のリズムを調整しています。
体内時計が乱れると、睡眠障害やホルモンバランスの崩れ、食欲不振または過食、体温調整の乱れ、集中力や作業効率の低下といった状態になる可能性があります。
正月病と「冬季うつ」の違い
正月病と似た症状を示す「冬季うつ」について理解することも重要です。
冬季うつは、季節性情動障害の一種で、主に秋から冬にかけて症状が現れ、春になると改善する気分障害です。
特徴として、抗うつ気分になったり、喜びや興味の喪失、睡眠過多、体重増加、疲労感や気力の低下といった症状が見られます。正月病が主に年末年始の生活リズムの乱れによって引き起こされるのに対し、冬季うつはより長期的な季節の変化に関連しています。冬季うつの原因は、日照時間の減少による体内時計の乱れやセロトニンの減少とされ、正月病は通常数日から数週間で改善しますが、冬季うつは春までの数か月間続くことがあります。
体内時計を整える3つのポイント
正月病を予防・改善するためには、体内時計を整えることが重要です。
少しでも早く生活リズムを戻し、新年に健康的にスタートためには、「体内時計」を整えるのが何よりの近道です。
- 日光を浴びる
朝、カーテンを開けて太陽の光を浴びることで、目から入った刺激が脳に伝わり、体内時計をリセットします。可能であれば、朝の散歩や通勤時に意識的に日光を浴びるようにしましょう。
- 食事のタイミングを意識する
食事をすると血糖値が上がり、インスリンというホルモンが分泌されます。このインスリンが体内時計を調節する役割を果たします。特に朝食は重要で、炭水化物(糖質)とたんぱく質を一緒に摂取することで、体内時計のリセット効果が高まります。
- 適切な睡眠習慣を心がける
質の良い睡眠を十分にとることは、体内時計の調整に不可欠です。睡眠不足はインスリンの働きを鈍らせ、食欲に関わるホルモン分泌を乱すため、過食や肥満のリスクが高まります。体内時計が狂って臓器間に「時差ぼけ」状態が発生し、このズレが負担となりさまざまな不調につながるのです。

日光を浴びる・食事のタイミングや睡眠時間など「体内時計」を意識する
正月病を解消するセルフケア5選
正月病の症状を和らげ、早期に回復するためのセルフケア方法を5つ紹介します。
1. 規則正しい生活リズムを取り戻す
休暇中に乱れた生活リズムを、できるだけ早く平常時に戻すことが重要です。
まずは以下の点に注意し、生活のリズムを整えてください。
- 決まった時間に起床・就寝する
- 食事の時間を一定に保つ
- 休日も平日と同じようなリズムを維持する
2. 適度な運動を取り入れる
運動は体内時計の調整や気分の改善に効果的です。
以下のような運動に日々取り組みましょう。
- 朝の軽いストレッチや散歩
- 昼休みのウォーキング
- 帰宅後のジョギングやヨガ
ただし、就寝直前の激しい運動は避け、体を冷やさないよう注意しましょう。
3. バランスの良い食事を心がける
正月太りの解消と体調管理のため、以下のような食事を心がけましょう。
- 朝食はしっかり摂る(炭水化物とたんぱく質を含む)
- 野菜を多く摂取し、ビタミンやミネラルを補給する
- 過度の糖質制限は避け、適度な炭水化物を摂取する
- 水分をこまめに補給する
4. リラックス法を実践する
ストレス解消と心身のリラックスのため、以下のような方法を試してみましょう。
- 深呼吸やメディテーション(瞑想)
- 入浴時のストレッチ
- アロマセラピー
- 趣味の時間を確保する
5. 社会的つながりを大切にする
孤独感は正月病やうつ症状を悪化させる可能性があります。
以下のような方法で、社会的つながりを維持しましょう。
- 家族や友人との定期的な連絡
- 職場の同僚とのコミュニケーション
- 地域のイベントやボランティア活動への参加
正月病(五月病や「ブルーマンデー」も同義)は多くの社会人が経験するとされますが、適切な対策を取ることで早期に回復することが可能です。長期休暇明けで体調がすぐれないときは、体内時計を整えることを中心に、生活リズムの調整、適度な運動、バランスの良い食事、リラックス法の実践、社会的つながりの維持など、総合的なアプローチが効果的です。
それでも不調が長く続くようなら、冬季うつの可能性も考慮して心療内科や職場の産業保健スタッフなど専門家に躊躇なく相談してみることをお勧めします。
新たな一年のはじまりに限らず、皆さまがより健康的に、日々の業務に従事できることをお祈り申し上げます。

従業員向けの電話・メールによるメンタル相談やハラスメント対策の外部相談窓口代行、管理職・人事・総務ご担当者様を対象としたラインケア研修や新入社員向けのメンタルヘルス研修などの法人サポートサービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」を是非ご提案させてください。
まずは以下のお問い合わせ・資料ダウンロードフォームより、お気軽にご一報ください。
| 初出:2022年01月05日 / 編集:2026年01月05日 |