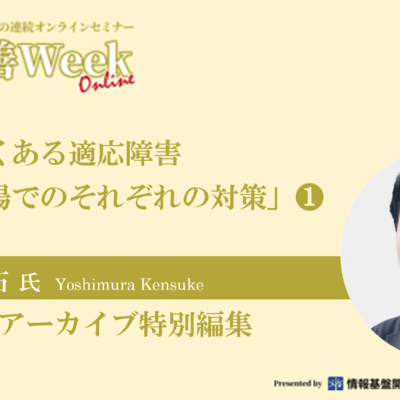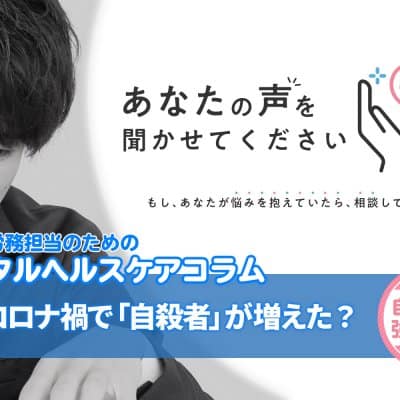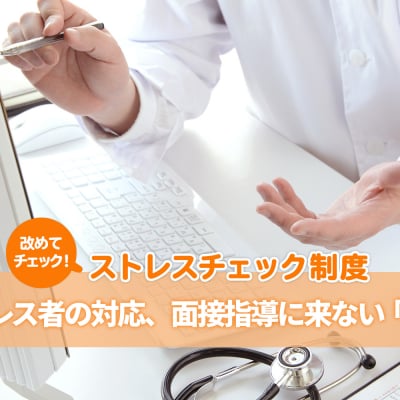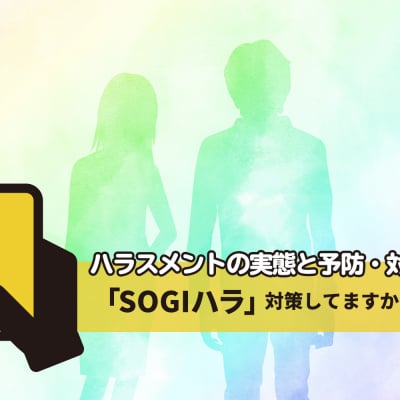2015年12月1日にストレスチェック制度が施行されてから3年になろうとしています。3回目のストレスチェックを完了した企業も多いと思いますが、継続的にストレスチェックを実施することで、経年的な変化が見えてきたのではないでしょうか。
2015年12月1日にストレスチェック制度が施行されてから3年になろうとしています。3回目のストレスチェックを完了した企業も多いと思いますが、継続的にストレスチェックを実施することで、経年的な変化が見えてきたのではないでしょうか。
ストレスチェック制度の実施状況等について、平成29年労働安全衛生調査(実態調査)の結果を以下にまとめました。また、ストレスチェック制度を効果的なものにするためにはどうしたらよいかについても簡単にまとめましたので、再確認してみてください。
◎ストレスチェック制度の実施状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、労働者のストレス状況等について調査票を用いて調査(ストレスチェック)を行った事業所は、平成28年は62.3%でしたが平成29年の実態調査では64.3%となっています。
実施しているストレスチェックの種類としては、2015年12月1日に施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェックが平成28年は79.3%であったのに対し、平成29年は93.8%となっており、ストレスチェック制度が少しずつ浸透していることがうかがわれます。
ストレスチェックの実施時期については、定期健康診断の機会に実施した事業所が26.1%、定期健康診断以外の機会に実施した事業所が73.6%となっています。
ストレスチェックの結果に基づいて事業所が指定した医師等の専門家による面談等を実施した事業所は、平成28年は33.6%でしたが平成29年は47.0%と10%以上増加しています。しかしながら、面談等を実施した労働者の割合階級別にみると「5%未満」が77.5%と最も多いという状況で、ストレスチェックの結果に基づいて実際に面接指導が行われるのは依然として少ないようです。
ストレスチェックの結果の集団分析を実施した事業場は、平成28年は43.8%でしたが平成29年は58.3%と10%以上増加しています。従業員のメンタルヘルス対策として集団分析の必要性を認識する企業が多くなってきたのではないでしょうか。
◎メンタルヘルス対策の必要性
過去1年間(平成28年11月1日~平成29年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く)の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.3%となっています。
事業所の規模別にみると、連続1ヵ月以上休業した労働者は「1,000人以上の規模の事業所」が0.8%と最も高く、退職した労働者は「10~29人の規模の事業所」が0.4%と最も高くなっています。中小企業では復職支援の体制等が整っていないことが多いため、メンタルヘルス不調によって退職する労働者の割合が高くなっているのではないでしょうか。


(厚生労働省 平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 第1図をもとに情報基盤開発で作図)
産業別にみると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業した労働者は「情報通信業」と「金融業・保険業」が1.2%と最も高く、退職した労働者は「運輸業・郵便業」が0.5%と最も高くなっています。
精神障害による労災認定件数は年々増加していますが、実際にメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は58.4%であり、取り組みの内容としては「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)が64.3%と最も多く、「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が40.6%、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が39.4%となっています。


(厚生労働省 平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況 第3図をもとに情報基盤開発で作図)
メンタルヘルス対策の必要性は認識していても、実際に取り組んでいる事業所の割合はここ数年あまり変化がなく、費用面等から難しいと考えている企業が多いことがうかがわれますが、ストレスチェックは制度として法令で定められているメンタルヘルス対策なので、有効活用するとよいでしょう。
◎ストレスチェック制度を効果的なものにするために
ストレスチェック制度では労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。本制度においては、ストレスチェックを実施してその結果を労働者に通知することによって自分のストレス状況について気付くことを促し、セルフケアにつなげることが第一の目的となりますが、高ストレス者への対応も重要なポイントとなります。
ストレスチェックの結果で面接指導が必要な高ストレス者と判定された人から申出があると医師による面接指導が行われますが、実際に面接指導を申出る人はほんの僅かであるというのが現状です。しかし、高ストレス状態を低減させるためには、カウンセリングや就業上の措置を必要とすることが多いのです。医師による面接指導の申出をしない高ストレス者に対しては、そのまま放置しないで積極的に申出の勧奨をするようにしましょう。
ストレスチェック制度における面接指導を希望しない場合は、通常の産業保健相談につなげたり、身近な地域・医療機関への相談を勧めるなど、有用な情報を提供するようにしましょう。
また、労働者のメンタルヘルス不調を防ぐためには、ストレスチェックの結果に基づいて集団分析を実施し、職場環境改善活動を行うことが重要なポイントとなります。集団分析は現時点では努力義務ですが、メンタルヘルス不調者が生じることを防ぐためには職場環境を改善することによって働きやすい職場づくりをする必要があります。職場環境の改善に向けてのツールとしては、以下の一覧を参考にしてみてください。
・職場環境改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクションチェックリスト)
・職場の快適度チェック
・メンタルヘルス改善意識調査票(MIRROR)を用いた職場改善の取り組み
・いきいき職場づくりのための参加型 職場改善の手引き【改訂版】~仕事のストレスを改善する 職場環境改善のすすめ方~
★ポイント★
例えば、じん肺は古くから知られている職業性疾病ですが、1960年に「じん肺法」が制定され、防塵マスクの使用等による一次予防の結果が表れるまでには10年以上かかっています。
近年の精神疾患患者の増加および精神疾患による労災認定の増加により、ストレスチェック制度がスタートしましたが、その効果が明確に示されるまでにはまだ時間がかかるでしょう。従業員の心身の健康の保持・増進を図ることは、企業の生産性を上げるためにも大切です。ストレスチェック制度を有効活用して健康経営につなげましょう。
| 初出:2018年10月19日 |