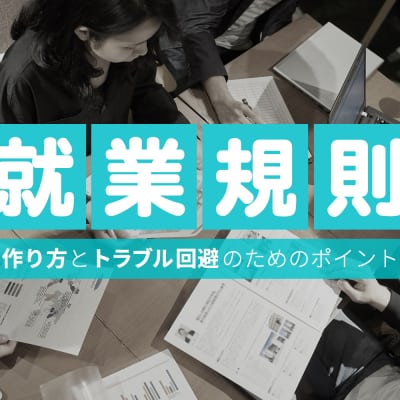働き方改革の成立から労働安全衛生法が改正され、2019年4月から「健康情報取扱規程」の策定・労働基準監督署への届け出がすべての企業を対象に義務付けとなりました。
ストレスチェックの実施が義務付けられた従業員50人以上の法人事業者であれば、衛生委員会や安全衛生委員会での審議が求められ、労使間協議を実施するなどして対策済みのところが大半と思われます。
衛生委員会の設置が義務化されていない従業員50人未満の事業場やスタートアップ企業の場合には、従業員の健康状態についてしっかりと協議を進めてこなかった、というケースがあるかもしれません。
当記事では企業の労務・人事担当の方々に向け、健康情報取扱の規程の概要から規程の策定方法まで紹介します。
この機会に、従業員の健康管理上の制度と手続きを今一度確認していただけたらと思います。
「健康情報取扱規程」とは?
健康情報取扱規程とは、従業員の健康情報を取得および管理するための規程のことです。
健康情報とは、従業員個人の心と体にまつわる情報です。健康診断やストレスチェックの結果、産業医との面談に関わる情報などが当たります。
規程は個人情報保護法に基づいて作成され、従業員の健康情報が第三者などに漏洩するのを防いだりなど、従業員の健康情報を適切かつ有効に取り扱うために定められます。
厚生労働省が公表したモデル規程では、従業員の健康情報は産業医しか取り扱うことができなくなり、社長は産業医などが加工した情報しか閲覧できません。従業員の心身の状態に関する情報を収集等するに当たって、健康確保に必要な範囲内で収集し、保管・使用しなければなりません。
規程の策定において、モデル規程を改変して社長や役員などが健康情報を閲覧できるようにすることは可能ですが、規程の策定は労使間で行う必要があります。
健康情報をどの立場の人間がどこまで管理するか、またどのように管理するのか。
しっかりと労使間で協議して決定しなければいけません。

健康情報の管理方法
健康情報の管理方法は事業者と労働者の協議のうえ、策定によって決められます。
たとえば厚生労働省が2019年3月に公表した健康情報取扱規程のモデルでは、健康情報が不利益な取り扱いにつながらないよう、「健康情報を取り扱う範囲」として情報を取り扱うことができる人を以下の4種類に分類しています。
【 健康情報等の取扱いを担当する者 】
- 社長・役員・人事部門の長など 人事権、監督権のある人
- 産業医・保健師・介護師・衛生管理者・衛生推進者
- 労働者本人の所属長
- 人事部門の長以外の事務担当者
厚労省のモデル規程では、それぞれの取扱者の権限が情報の種類ごとに「◎・◯・△」の3段階で区分されており、基本的に「△」に該当する取扱者は、直接的に情報の収集・保管・使用ができません。たとえば社長や役員などが保健指導の内容を扱うことはできませんが、指導の実施や加工された統計情報の閲覧については認められています。
健康情報の管理方法は策定した規程によって異なりますが、厚労省のモデル規程は完成度が高く、ほとんどの企業で同じ内容を策定しても十分に問題ない・安全性が高いものです。基本的にはそのモデルどおりの策定を行うところが多くなることが予想されます。
“社長や役員が従業員の健康情報を管理できない”ことがスタンダードになるでしょう。
健康情報取扱規程の策定方法
規程の策定は衛生委員会などを活用し、労使が関与している上で行います。
会社側の一方的な内容にならないよう注意が必要です。
一方で、従業員数が少ないなどで衛生委員会を設置していない事業場の場合は、労働者の意見を聴取する機会を設けることが必要です。その上で労働者の意見を反映し、実情にあった規程を策定します。就業規則の作成と同様に、意見書の提出をお願いしたり過半数の労働者の賛同が得られたことを記録しておくと後々の証拠となります。
また、規程を策定するだけでなく、規程文書を作業場に掲示したり、イントラネットに掲載するなどして、労働者に対して周知させることも必要とされています。
健康情報の中には本人の同意を得られないと閲覧ができないものもあるので、「本人の同意取得の方法」「情報の利用目的・利用方法」については全従業員が知らなければならない情報です。そのため規程を策定する際は、労働者の意見を反映させ、どのように周知させるかまで協議しなくてはいけません。
規程策定において定めるべきこと
厚生労働省が発表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号」によれば、規程策定において主に以下9つのことを定めるよう推奨しています。
- 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
- 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う 心身の状態の 情報の範囲
- 心身の状態の 情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
- 心身の状態の 情報の適正管理の方法
- 心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。以下同じ。)の方法
- 心身の状態の情報の第三者提供の方法
- 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
- 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
- 取扱規程の労働者への周知の方法
※引用:
厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号」
2 心身の状態の情報の取扱いに関する原則(3)取扱規程に定めるべき事項
また厚生労働省では同様に、規程を策定するための「手引き」も公表しています。
実際に規程を策定するときには参考にすることをオススメします。
今回説明した、健康情報取扱規程の概要をまとめると以下のとおりです。
- 2019年4月より健康情報取扱規程の策定の義務化
- 規程を定めるのは労働者の健康確保措置の徹底が目的
- 規程では健康情報の取扱方法やその範囲を定める
- 規程の策定は労使で協議して行う
- 規程の策定後は周知させる
健康情報取扱規程の策定義務は、労働時間をはじめとした労働環境の問題を改善する一つの方法です。企業の労務や人事を担当している方であれば、必ず頭に入れておかなければいけません。
働き方改革にともなっていろいろと手続きや考えなければならないことが発生しましたが、どれも従業員・企業双方の「健康」を守るためのものです。健康情報取扱規程と併せてその他の会社の規程について見直してみてください。
〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省:労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第2号 ※2022年3月31日改定
- 厚生労働省:事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き ※2019年3月
- 日本医師会:事業場における労働者の健康情報等の取扱いについて
| 初出:2019年09月20日 / 編集:2023年08月31日 |