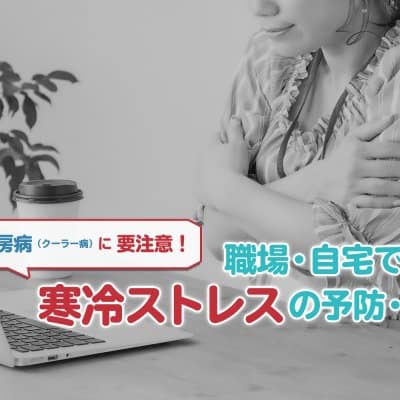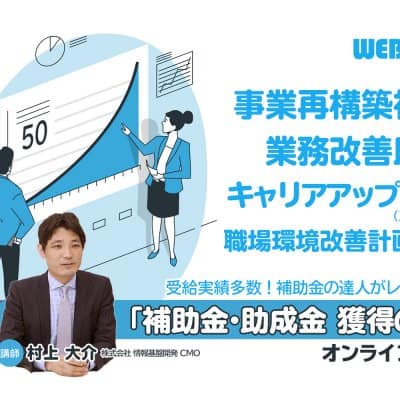ストレスチェックが企業の義務となってからは一応毎年実施しているし、自分も受検している。
「ストレスチェックをやってはいるけれど、これのどこがどうメンタルヘルスに効くんだろう?」
……そんな素朴な疑問を感じたことはありませんか?
ストレスチェックはメンタルヘルスの不調から生活を守る、「予防医学のセオリー」によって作られています。
ストレスチェックはメンタルヘルスにどう効くの?
ストレスチェックとは、「心身のストレス反応」と「職場のストレス要因」について調査できる簡単な検査です。実施方法もストレスに関する質問票に回答し、それを集計・分析するだけの簡単なものです。労働安全衛生法によって50人以上の労働者を雇用する事業場では年1回ストレスチェックを行うことが義務化されています。一度は受けたことがある! という方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックを適切に運用すれば、
・従業員が自分のストレス状態を知ることによってセルフケアを行ったり……
・高ストレス者と判定された場合は医師面接で助言を受けたり……
・ 事業者が必要な措置や職場環境の改善・検討を行ったり……
することで「うつ状態」等のメンタルヘルス不調を未然に防止することができます。
つまり、ストレスチェックの最大の目的は「不調の防止」なのです!
ストレスチェック制度は労働者のメンタルヘルス対策の柱の一つとして策定されました。この時、対策の基本的な考えとして注目されたのが「予防医学」。
「病気になって、それから治すより、 病気にならない・なりにくい方が負担やコストが少ない」という考えから生まれた予防医学は、「疾病の発生を一次予防で防ぐ」・「疾病の悪化を二次予防で防ぐ」・「後遺症や障害による疾病の悪影響を三次予防で防ぐ」の三つの視点で 病気を予防し、健康増進を図っています。
ストレスチェックは、メンタル不調の「一次予防」として重要な役割を担っています。
一次予防、二次予防、三次予防とは?
一次予防は病気にならない「環境」を作ること
一般的な意味での「一次予防」とは、病気になる前の健康な人に対して「病気にならない・なりにくい環境」を整えることで病気の発生防止を目指します。
一次予防で対象となる「環境」は幅広く、職場や家庭など目的に応じた快適な環境を整えることから、生活習慣の改善・健康教育、予防接種等を行うことで病気に弱い人々を守る社会を築くところまで含まれます。
二次予防は「早期発見・早期治療」で重症化をストップ
「二次予防」とは、病気の進行を抑制して重篤化するのを防ぐことを目的とした活動を指します。特に早期発見・早期治療は後遺症の防止や健康寿命の増進につながります。健康診断等で病気になった人をできるだけ早く発見する・日常の体調の悩みを相談できるよう窓口を設けるといった、不調が疾病になる前に医療ケアへつなげる環境の整備の他に、何が適切な医療か本人が考えられるような知識の提供・教育の支援も二次予防とされます。
三次予防で病後の復帰や回復を支援
「三次予防」とは、病気が発症・進行した後に続く「再発防止」や「社会復帰」を促すことです。 直接的には治療後の保健指導、リハビリテーションの実施などが当たります。
企業や私たちができる三次予防としては、再発防止のために生活習慣の改善を図ったり、通院しやすいよう配慮する、身体の不自由など困難なことがあっても快適に暮らせるデザインや設計を行うなど様々です。
メンタル不調の難しさは「回復」にあり……
予防で未然に防ぐことが最重要!
近年、労働者のメンタルヘルス対策の重要性が強調されることが多くなりました。
長時間労働による循環器疾患と並んで語られることが多いのがメンタルヘルスの不調ですが、なぜこの二つは「予防が大事」といわれるのでしょうか。
それはこの二つの疾病が「発見・治療が難しい」・「重症化やすい」という共通の特徴を持っているからです。
循環器疾患は心臓や脳といった生命維持に重要な臓器に深刻なダメージを与えますが、メンタルヘルスの不調は「気分」「体調」に続いて「回復力」を支える日々の生活にハンデを与えるケースがあります。一度発症すると、疾病の長期化とともにその人の「これから先」にマイナスの影響を与える可能性が高いのです。
そのため、政府は企業の力を借りて「病気に陥らない」環境の整備に力を入れています。
労働者がメンタルヘルス不調に陥ることを防ぐためのプロセスとしての一次予防、二次予防、三次予防とは、それぞれどのようなものがあるでしょうか。
まず一次予防とは、労働者自身のストレスへの気づき、および対処の支援、並びに職場環境の改善を通してメンタルヘルス不調になることを未然に防止するものです。
ストレスチェックはこの「気づきのきっかけ」になるものとして、一次予防を目的に掲げています。
二次予防とは、メンタルヘルスに不調が生じてしまった労働者を早期に発見し、医療機関の受診を勧めたり、仕事の内容を再検討するなど、適切な対応を行うことです。三次予防では、うつ状態等のメンタルヘルス不調になって休業した労働者の職場復帰を支援したり、再発の予防に努める取り組みが考えられます。
ささいな「要因」を放っておかない、が一番の近道
「1つの重大事故の背景には29の軽微な事故があり、さらにその背景には300のヒヤリとする事故が存在する」というハインリッヒの法則があります。
「重大な事故は軽微な事故を防いでいれば発生しない」ものであり、「軽微な事故はヒヤリとするような事故を防いでいれば発生しない」ものだという考えは安全衛生を学ぶ上で必ず習う大事な教訓です。
労働者のメンタルヘルス不調を「重大な事故」と仮定すると、その背景には多くのささいなストレス要因が存在しています。
「ちょっと言いにくい」「気にするほどではないけど、しんどい」というのは立派なストレス。日常の中で気づかずストレスが積み重なっていると、ほんの少しの不調やトラブルが大きな病気へと連鎖します。
ストレスチェックは単純な仕組みの調査ですが、職場でのストレスの有無や「今つらいと感じている人」をピックアップできる優秀なツールです。もちろん実施後の改善や医療的なケアは必要となりますが、定期的にメンタルヘルス不調の原因となりうるストレス要因を早期に発見し一つ一つに向き合ってケアをしていけば、メンタルヘルス不調を確実に防止できます。
ストレスチェックという「ストレスのリトマス試験紙」を活用して、一次予防としてのセルフケア・職場環境改善を進めましょう!
| 初出:2015年9月17日 / 編集:2023年04月13日 |